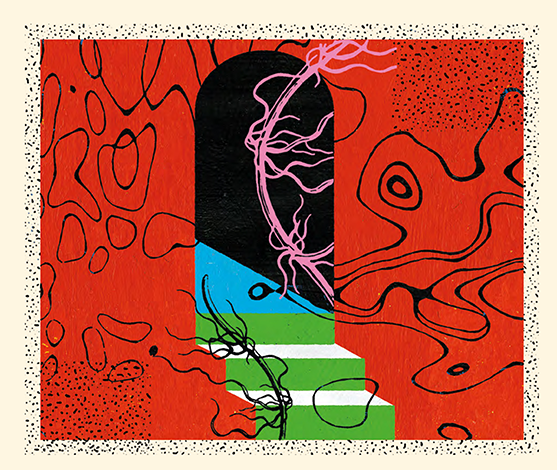仏デザイナー連盟(Alliance française des designers)の定めた定義によれば、「デザインとは知的かつ創造的で、かつ分野横断的なリベラルアーツに基づくひとつのプロセスによって作られるもの、およびそのプロセスそれ自体を指すものである。その目的とは[...]人々の送る日常生活において生じるさまざまな問題に対し、考えられ得るいくつかの解決策を提供すること[...]ならびに経済、社会、環境において生じる課題に関して、何らかの打開策を提案することにあるとする。[...]またデザインは、空間の創造や、視覚的・音響的メッセージの伝達[...]さまざまな製品やサービスの創出に寄与しつつ、これを通して、それらに意味や感情、アイデンティティを与えるとともに、アクセシビリティの改善や体験の向上を目指すものとする」。
つまり、デザインとは審美性、機能性、そして現代性に関わるものであると、そう要約することができるだろう。この3つの属性が家具や建築といった分野に当てはまることは容易に想像がつくが、果たして香りにもそれが言えるのだろうか? つまりデザインという概念は香りに対しても適用可能なのだろうか?「まさに調香師こそが最初に挙げられるべき嗅覚デザイナーと言えるでしょう。調香師たちはマーケティングの声にも耳を傾けながら、最新のテクノロジーを駆使し、これまでになかった香りの形態を創造します」。そう語るのは自らも調香師を務めるかたわら、オズモアート・エージェンシーを立ち上げたピエール・ベナールだ。「デザイナーという存在はファインアートと名のつくあらゆる芸術分野を総動員します。そしてその目的は、日常生活をより良いものにすることにあります。まさにこの点にこそ、芸術家とのちがいがあると言えます。芸術家はただ自らの表現欲求に従って作品を作るだけであって、そこに社会的な目的や機能は存在しません」。
いっぽうで、デザインという用語が香水という分野にも持ちこまれることに対し違和感を覚えるものもいる。独立系調香師のジャン=クロード・エレナもそのひとりだ。「デザインの意図するところとは、クライアントからの指示や要望に合致した製品を提示することです。つまり発注された時点でそのデザインの方向性はほとんど定まっていると言えます」と、ジャン=クロード・エレナは先ほどとはまたちがったデザインの定義を当てはめてみせる。「それゆえデザインの起源をさかのぼると、やがてはマーケティングに行き着くことになるのです。私が思うに香水とは、装飾芸術(arts décoratifs)のひとつに属する分野です。この装飾芸術という表現は1870年代に生まれた用語になりますが、芸術的な作品の創造をその使命とする『美術・ファインアート』に近いものとして位置づけられていました。つまり、装飾芸術たる香水には実用的な機能は想定されておりません。つまり機能性を志向するデザインとは本来相容れないものなのです。香水は人々からただ欲望され、喜びを与えるためだけに存在しているのです」。
調香師と美的自由
ホテル、店舗、展覧会や各種イベント。そうしたさまざまな場所に「嗅覚デザイン」が見出される。とはいえこれを指すために使われる言葉にはさまざまなものがあり、いまだ呼称が安定していない。「嗅覚的アイデンティティ」と呼ばれることもあれば「香りの痕跡」、あるいは「シグネチャー香水」という言葉の使用も見られる。このように確固とした正式名称を欠いていることからも容易に推察できるように、こうした「空間における香り」の市場は規模が小さく、かつ縮小傾向にあるという困難に直面している。高級香水や機能性香料に比べて圧倒的に消費量の少ないこの「アンビエント香水」は、そもそものところ経済モデルが確立されていないのである。香料会社の多くは開発中の作業自体には料金を課さず、納品した香水の販売実績に応じて報酬を得る仕組みになっているため、不特定多数の消費者に対し売上げが期待できる香水とはちがって、公共の場でのコミュニケーションツールという趣きが強いこのプロジェクトにはどの企業もあまりリソースを割きたがらない。だがそのいっぽうで、一部の調香師たちからは創作の原点に立ち返る思わぬ好機となったという声もあがっている。「イジプカ(香水・化粧品・食品香料国際高等学院)を卒業したばかりのころに、こうあるべきだ、と思い描いていたあの自由と喜びを、『空間的香り』の制作を通して思い出せたような気がします。そのあるべき自由とはすなわち、調香師の書いた処方の主人はただその調香師ひとりであるということです。そしてクライアントとは直接会って話すということです」。そう語るのは調香師のカロリーヌ・マレジャック=コルミエだ。彼女は嗅覚を始めとした五感を分析するマーケティング会社「マイ・アロマティック・ウィッシュ」を起業した。ここで彼女が述べている、仲介を挟まず直接話ができる関係、というのはまさにジャン=クロード・エレナが推奨していることでもある。「私は香水が企業の代表と直接やり取りされたうえで作られていた時代を知っています。つまりマーケティング部門も、エバリュエーターも介さずにです。マーケティングの台頭によって香水業界は商業主義に染まってしまいました。マーケティングが創作の場に介入するようなことはやはりあってはならないことだと思います。さもなくば調香師は単なる技術者になれ果ててしまいますし、創造者としての役割を忘却してしまうことでしょう」。
「マーケティングの台頭によって香水業界は商業主義に染まってしまいました。マーケティングが創作の場に介入するようなことはやはりあってはならないことだと思います。さもなくば調香師は単なる技術者になれ果ててしまいますし、創造者としての役割を忘却してしまうことでしょう」(ジャン=クロード・エレナ)
異なる感覚との出会い
美というものを追求し突き詰めるためには、ときとしてこれまで縁のなかったまったく新しい知識を学ぶ必要が出てくる。そしてそれが調香師である場合、それまで学んできた専門知識を一度リセットし、ほとんど生のままのような匂いをまっさらな状態で改めて検討し直すことで、これまで気づかなかったことが見えてきたりもする。フィルメニッヒの調香師ニコラ・ボヌヴィルの場合、それはガラス吹き職人のジェレミー・マクスウェルとの出会いであった。ふたりはすぐに意気投合し、そこから交流が始まった。あるときマクスウェルの個展会場に香らせる「空間香水」の制作を頼まれたボヌヴィルは、そこで改めて、これまで自分が高級香水を制作するために培ってきたノウハウを一度捨て去る必要性を感じた。香水を作るのとはまた「別のやりかた」で、それを構築する必要があった。自身の作品に好んで使っていた素材のひとつが砂であったので、マクスウェルはその砂を感じさせる香りを作ってほしいと要望していた。そうとあらば、と業界では砂浜を思わせる香りとしておなじみのサリチル酸エチルを使った試作をかいでもらったところ、マクスウェルからのコメントは実に素っ気ないものだった。「一度本物の砂の匂いをかぎに僕のアトリエに来たらどうだ!」。マーケティングというものに毒されていないものならではの反応であった。ここでボヌヴィルがしたような経験によって、調香師は匂いを分析するにあたってこれまで慣れ親しんできた予備知識や固定観念にとらわれたままでい続けることの危険性を学ぶ。そしてこうした真に探求的な取り組みを通じて、今一度自らの創意に刺激を与え、磨きをかけるのである。こうした異なる感覚や素材との出会いばかりでなく、言葉の持つ意味や響きといったものが香りのデザイナーたちに対し影響を与えることもある。「『チャペル14(第14礼拝堂)』という名前は私にとってとても印象的で、実際その場を訪ねる前からずっと気になっていました」。シムライズの調香師アレクサンドラ・カルランはそう回想する。それはパリ18区にあるギャラリーの名前だった。真っ白な壁面のところどころにくぼみが設けられ、そこにさまざまなデザイナーたちによるプロダクトがさながら神へと捧げられた供物のように安置されていた。「この空間に満ちていた無垢でスピリチュアルなイメージを増幅させるために、乳香と没薬をベースに香りを構成してみました。そして白というイメージを表現するためにそこへサンダルウッドのノートを加えました」とカルランは語る。色彩への言及からも分かるようにその香りは視覚的な要素を引き立てるものであったと言えたが、始めに調香師自身がそう述べていたように、実際の場から感じたイメージ以上にそこには何よりも言葉による刻印があった。実際カルラン自身、過去の経験から言葉というものが調香に与える影響には無視できないものがあるという確証を得ていた。そしてそれとは反対に、ときとして香りが言葉のような力を持つことがあるということにも……。シムライズ所属の調香師数名と、分野横断的なアートプロジェクト「ドゥブル・セジュール」によって招かれたアーティスト、そして旺盛な出版活動を行う嗅覚グループ「ジュルナル・ダン・アノスミック」とのコラボレーションとして、「伝言ゲーム」に着想した企画が行われたときのことだった。最初の調香師によってスタートとなる香りが作られ、それをかいだ次の参加者がその香りを再現した別の香りを作り、次の参加者へと渡す。こうしてリレーを行い、最後の香りが最初の香りをいかに再現できているか/いないかを検討する。まさに伝言ゲーム的にひとつの香りが別の参加者にインスピレーションを与え、それによって作られた香りがまた次の参加者にインスピレーションを与えていく、という過程のなかで、だんだん最初の香りから逸れていき、最後にはまったくちがう香りができあがる……はずだった。「何とその場で提示されたどの香りも、最初の香りが設定したトーンからそれなりの一貫性を保持していたのです。ちょっとした驚きでした」。
「肌につけるためのファインフレグランスがとにもかくにも『ユニーク』であることを志向するものであるとしたら、アンビエント香水は利用者に『安らぎくつろいでもらうこと』が念頭におかれている、といったそのようなちがいもあります」(マリア・アンヘレス・ロペス)
美と有用性
嗅覚デザインの基本は、依頼元であるブランドの持つ歴史を踏まえそのフィロソフィーに寄り添った香りを作ることだ。そのいっぽうで、ときに「その変化」を伝える役割も担う。「ブランドが伝えたいと考えているイメージは当然ながら過去の歴史ばかりではありません。ブランドが『今』発信したいと願っているイメージはそのときごとに変わるのですから」と、そうカロリーヌ・マレジャック=コルミエは強調する。マレジャック=コルミエはここ最近、某大手アウトドア用品チェーンの嗅覚アイデンティティを仕上げたところだった。彼女の洞察によればそのブランドの求めるイメージは、自然にあふれた田舎から都市へと移りつつあった。「そこで、都会のなかの自然をテーマに香りを作ることにしたのです。都市生活者の視点から感じられる、雨で濡れた土の上に太陽の光が降り注ぐ匂いをそこに表現しました」。こんな風にさまざまなものが日々目まぐるしく移り変わっていくのだから、この分野の関係者たちがさまざまに変わっていくというのもそう驚くに値することではないのかもしれない。かつては技術の開発と提供を行なっていた業者が今では「ラ・ギルド」のような、嗅覚マーケティングに特化したエージェンシーに方向転換したという話も聞く。その当の「ラ・ギルド」によれば香りとは、ブランドの世界観を表現するとともに人々の内から意図した感情を引き出すことのできる、新たなる次元として機能する可能性を秘めているということだ。「人間と同じように、ブランドもまたもっと研究され分析されるべきなのです。ブランドにもさまざまな性格や特質があります。例えば、強く堅牢なブランドもあれば、逆に繊細で脆弱なブランドもあるわけであって、攻撃的なブランド、とらえどころのない幽霊のようなブランド、あるいは異なる複数の価値が混ざり合ったブランドといったものも存在します」と同エージェンシーの創設者セバスチャン・エイリアールは語る。「インカンテーション(呪文)」という名のサンダルウッドの香りがIFF(インターナショナル・フレイバーズ・アンド・フレグランシズ)の調香師ジュリアン・ラスキネーによって作られ、リニューアルオープンを迎えたサマリテーヌ百貨店のシグネチャー香水として採用された。「パンデミックによってシグネチャー香水の意義も疑問視されるのではないか? という懸念もありましたが、そうはなりませんでした。実際にはむしろその逆だったのです。百貨店を訪れる人々が安心して買い物を楽しむことができるのは、彼らがその場所に入った瞬間に感じることになる、どこかほっとするような安心感を与えるその香りによってであるということがそこで証明されることになったのです」と、そうセバスチャン・エイリアールも認めている。
なるほど、確かにそうですね、とうなずいてみせるのはマリア・アンヘレス・ロペスだ。「確かにそんな風に、調香師にはどこか心理学者のような役割が期待されている節もあります。その香りで心地良くしてもらうことを、人々は彼らに期待しているのです」。スペイン人調香師である彼女は西・大手香料会社イベルケムで開発ディレクターを務める。そして作り出すその香りに対し、ブランドのイメージ、そして期待される効果との整合性を持たせるとともに、実際香りを拡散するその場所にそぐうものにするためには、その現場に存在し想定される「多くのパラメータを考慮に入れなければなりません」ということを同氏は強調する。その例としては、色や照明、温度、湿度など、多岐にわたるとのことだ。「そのため、弊社には温度と湿度を自在に調整できる実験室がありますので、まずはそちらで試験をすることになります。肌につけるためのファインフレグランスがとにもかくにも『ユニーク』であることを志向するものであるとしたら、アンビエント香水は利用者に『安らぎくつろいでもらうこと』が念頭に置かれている、といったそのようなちがいもあります。そのため空間香水を公共空間に導入しようとしている担当者は、さながら自分の家の色を選ぶときのような慎重さをもって、快適すぎてもっと長くその場で過ごしていたいと訪問者がそう感じざるを得ないような、そんな香りを選定し採用することが求められるのです」。空間香水はその場に居合わせたすべての人が、好むと好まざるとにかかわらず不可避的に浴びることになる。それゆえその導入にあたっては、文化的な差異も熟慮の対象となる。「例えば空港などの、さまざまな国の人々が行き交う場所を香らせるときです。私どもにもメキシコの空港での実績がありますが、その際にはあらゆる国籍の利用者を想定して香りを制作しました」。
そうした、どのような文化的背景を持つ人にも通じる、言わばユニバーサルな香りというものは実際成り立つものなのだろうか? 少なくとも、ジャン=クロード・エレナにとっては首を傾げざるを得ない問題のようだ。「映画の誕生以来、音響に関しては普遍的な文法が築かれてきました。例えばドアが閉まるのを聞いたとき、誰でもそれがドアの音だと分かるでしょう。ですが匂いにはそれが当てはまりません。フランスとベトナムの食卓では当然感じられる匂いはちがうでしょう。匂いが持つ意味というものも国や文化ごとに異なります。同じ匂いをかいだとしても、かぐ人の国籍がちがえばまったくちがう感じかたをするということだってざらにあるのですから」。
時代とともに創造すること
デザインという営みにおいてユニークな点は、各時代に現れた世界中のデザイナーたちの貢献を踏襲しつつ文化の移り変わりにも敏感に適応し、そうして自らを作り変えながら独自の進化を続けてきたという点だ。「ある物や人が、それが存在するのと同じ時代に属していると感じられるとき、人はそれを現代的だ、と呼びます。いっぽう香水が同時代を超え、置き去りにしたと感じられるとき、人はそれをクラシックだ、と呼びます。この点、『テール・デルメス』が発売からわずか1年足らずでクラシックだと評されたのは興味深いことだと思いました」と、その「テール・デルメス」を作ったジャン=クロード・エレナはそう回想する。
そして今、嗅覚は人々の感情を刺激するという新たな社会的役割を見出しつつある。そんな今日においては、この現代的であること、という主題はやはり感覚のありかたとは切っても切り離せない問題であるようだ。「私たちの使命とは新たなる感情と経験を提供するとともに、その普及と活性化に努めることなのです」と、そうセバスチャン・エイリアールは強調する。同氏が運営するエージェンシーは、近ごろパリ国立自然史博物館で開催された、視覚・聴覚・嗅覚といったすべての感覚に訴える没入型の舞台「センサリー・オデッセイ」の企画に協力したところだ。IFFとともに共同開発された約20種類の香りが来場者を包みこみ、森林、草原、サバンナなどで構成された壮大な嗅覚旅行へと誘った。
いっぽうドバイでも、これまでにはなかった珍しい嗅覚的試みが行われていた。2020年ドバイ万博でのスペイン館の香りはイベルケムによって担当された。パビリオンを進んでいくとやがて照明が暗く落とされたシアタールームへとたどり着く。暗闇のなかでぼんやりと輝くいくつものデジタルスクリーンの前を、人工的に発生させられた泡が漂う。映像にはスペイン北部のナバラ州と思われるシーンが映し出されている。山岳部で自然に富んだ地方ながらも、多くのスタートアップ企業が拠点を構える地域として知られる。「パチョリが香りながらも、非常に湿った苔のような質感を表現しました。そこへさらにアクア系のノートをつけ加えることで、パビリオン全体を支配していた、あの無機質なまでの未来的な雰囲気とのコントラストを試みたのです」と、イベルケム主任調香師のルス・ヴァケーロがそう自身の担当した空間香水を説明してくれる。「いかにもハイテクな装飾に彩られた近未来的空間にいるにもかかわらず、鼻のほうはリアルな森林を感じているという、そうした意外性のある異感覚を来場者には楽しんでもらえたと思います」。感覚ごとに異なるものを感じさせられて、さぞかし驚きが与えられたことだろう。
そして今、嗅覚は人々の感情を刺激するという新たな社会的役割を見出しつつある。そんな今日においては、この現代的であること、という主題はやはり感覚のありかたとは切っても切り離せない問題であるようだ。
新たな機能と、新たな使用法
取り扱う指にも目にも優しく安全な拡散方法が確立されたことで、私たちが日々親しんでいる香水の、その使いかたにも新たな変化が訪れつつある。テクノロジーの進化によって今や香水はエンターテイメントに近い分野に変わりつつあり、プロも個人も等しくそれを楽しめるようになった意義は大きい。近ごろではスピーカー型で、まるで音楽をかけるような感覚で香りを楽しめるデフューザー「コンポーズ(Compoz)」が話題を集めている。レトロモダンな、どこか懐かしさを感じさせるデザインだ。実際音楽プレイヤーを意識して作られているらしいことは実機を見ればひと目で分かるだろうが、同機はさまざまな機能を持つ。25種類のラインナップから5つを選び、香りのボリュームを調整することで自由にカスタマイズできたり、専用アプリを使って好みのブレンドを保存しておくこともできる。またプレイリストを再生したり有名調香師のセレクトをフォローしたりといった機能は、音楽配信サービスの「ディーザー」のモデルに近いものがあるかもしれない。「新たな技術が登場するところには、それを使うという、新たな動作・仕草も生まれます。それもまたデザインの一部として組みこまれるべきであって、もっと公けに向けて表現されるべきなのです」と、「コンポーズ」ブランドを立ち上げたエメリック・ウィダールはそう強調する。ここで同氏が挙げているこの「指先で再生ボタンを押す」という仕草は、センティス(Scentys)社がコンセプトとして掲げていることでもある。香りのカプセルをマシンに入れて「再生する」こちらは、むしろネスプレッソに似ていると言えるだろう。「おっしゃる通り、まさにネスプレッソからインスピレーションを受けているんです。カプセルで真空パックされた新鮮なコーヒーをたった数秒間で抽出することのできるネスプレッソは、今や世界中で大成功を収めています」と、そう語るのは同社ゼネラルマネージャーのデヴィッド・スイッサだ。「技術革新がめざましい今日にあっては、もはや声で香りをコントロールできる未来さえそう遠くないことでしょう。例えばAmazonのアレクサを使えば、読書中のソファの上から『集中力を高める香り』を拡散することも容易いでしょうし、料理中のキッチンに消臭効果のある香りを噴霧することもできるでしょう。このようなことが迅速に、かつ精密に操作できる未来がすぐそこで待っているのです」。こうしたテクノロジーが実用化されれば、日常生活のさまざまな場面において、これ以上ないほどの豊かな嗅覚体験が約束されることだろう。だが最後に紹介する例は、ともすれば人間に特有の創造という営み自体を揺るがしかねないという点で、普及のしかた次第では今後物議をかもすことになるかもしれない。香水調合ロボ「ノータ・ノータ(Nota Nota)」である。利用者の誰もがオリジナルの香りをデザインできるこのマシンの登場によって、これまで調香師たちが担ってきた役割が部分的に奪われるという可能性に思いをはせることはそこまで大げさなこととは言えぬであろう。ユーザーは思い思いの成分をセレクトしブレンドできるばかりでなく、自身が作ったその香りの配合を、やはり専用のアプリを用いて他のユーザーと遠隔でシェアできる。スキンフレグランス用だが、ディフューザーを取りつければ空間香水をデザインすることも可能だ。「新たなテクノロジーが到来するときに起こるのは、方法の刷新です。こうして香水を創造する方法が変わったのはもちろんのこと、その製造方法、さらには配布方法すらもこのように変革されていくのです」と、「ノータ・ノータ」社創業者のアブドゥラ・バハブリは語る。「香水はラグジュラリー産業のひとつですが、私たちはこのラグジュアリーな経験をより速く短い時間のなかで提供できないものかと考えていました。そしてその速さのなかでユーザー自身が各個人の創造性を発揮し、相互にシェアすることができないか、と。YouTubeのようなビデオ動画を思い浮かべていただくと分かりやすいかもしれません。YouTubeは爆発的な成功を収め今や世界にあまねく普及しておりますが、かといってそれが映画業界をおびやかしているわけではありませんし、予算数百万ドルの巨編映画作品と肩を並べて競い合っているわけでもありません。YouTubeはただ可能性を与えただけなのです。まだ日の目を見ぬ潜在的な映画作家やアーティストたちに、ただムーブメントに参加できる可能性を与えただけなのです」。
嗅覚デザインは嗅覚芸術たり得るか
このように香水と技術革新はともに手を取り合いながら発展してきたわけで、新たなテクノロジーが伝統的な香水に進化をもたらしたという寄与は大きいだろう。そのいっぽうで、近年よりデコラティブなものが好まれる傾向が高まりブームのきざしを見せ始めると、高いデザイン性と感覚体験とが同居した作品が数多く登場し始めた。建築家セルジュ・ビノットのデザインによるディプティックのゾイサイト鉱石製ディフューザーは、まさに機能性よりもスタイル美を重視した典型と言えるだろう。とはいえ冒頭に挙げたデザインの3大要素に関してはしっかりと抜け目なく押さえている。すなわちピレネー山脈産大理石の神々しいまでの美しさ、香りを吸収した石がゆっくりと時間をかけながらその香りを放つという機能性、そして何よりも、デザインの現代性だ。
ドルセーからは「フェティッシュ」という携帯可能なディフューザーが発売された。ポケットやハンドバッグに入れて持ち運べる小ささで、なかに入れた香水を普通に肌につけてスキンフレグランスとしても使えるし、あるいは空間に噴霧してアンビエント香水としても使えるというハイブリッド性が持ち味だ。だがここでわきあがってくるのは、空間に漂わせるのと同じ香りを自身の体にもつけたいと思うものだろうか? という疑問だ。「近年要望が高まってきているのがまさにそれなんです。空間にも肌にも使えるミックスフレグランスは、例えば枕用ミストなんかは肌にもつけられる香水と定義できると思いますが、このような需要の高まりとともに高級香水のノウハウをアンビエント香水に応用するといった試みも増えつつあります」とマリア・アンヘレス・ロペスはコメントする。
どちらも美的志向を有するという点ではデザインとアートとを隔てる境界はほとんどないものと言ってよいだろうが、実際にこの垣根を飛び越えようとする実験的試みが、調香師ダイアン・テルハイマー=クリーフの率いるプロジェクト「プロファイル・バイ」によって開かれた展覧会において見られた。同企画展ではIFFの調香師たちと各分野のアーティストがタッグを組み、香りをテーマにした6つの嗅覚アート作品が制作された。メインコンセプトとなる香りが各作品に付与されると、まるで魂が吹きこまれたかのように生き生きとした存在感を放ち始めるのであった。「作品の前を通り過ぎざまにふわりと感じる香りは、まるでそれを作ったアーティスト自身が目には見えないサインをこちらに送ってメッセージを投げかけてきているかのようでした」と主催のダイアン・テルハイマー=クリーフは感動的な様子でそう表現した。このような香りと芸術の融合、あるいは香りの具現化といったテーマは、アーティストたちに予期せぬひらめきや啓示をもたらしたのであった。「軽いながらも同時に堅牢さを合わせ持った、そんなオブジェを作りたいと思っていました。目には見えないものを表現するためには、それが空間のなかでどのような広がりかたをしているか意識する必要があったからです。オブジェというものが本来担うべき役割とは何だろうか、と改めて問い直してみて、ひとつの答えにたどりつきました。つまりオブジェは空気の流れを作り出し、その流れを活性化させることによって、そこに漂う香りをかぐわしく引き立たせるのです」とそう語るのはデザイナー・アーティストのパブロ・レイノソだ。彼もまた同プロジェクトの参加アーティストのひとりだった。そして新たな世代を教育し、後進を導くというのも芸術に課せられた重要な使命のひとつであろう。そしてその教育はまさにピエール・ベナールの信念でもあった。デザインについて教える教育のなかでも、この嗅覚という領域がほとんど扱われてこなかったという現状を憂いていたベナールは、そうした状況を打破すべく日々奮闘してきた人物だった。「教育と芸術というのは実はたいへん相性が良いのですよ。何かを学ぶ教材としては、芸術以上に適したものはないでしょう。たいへん残念なことですが、香りに宿る哲学的な側面はもう久しく見過ごされたままです。表現においても軽視されがちな嗅覚は、他の感覚が出尽くした後の最後になってようやく、いかにも変わり種的な添えものとして登場するにすぎないという不遇な扱いを受けています。若きデザイナーたちがまだ学校にいる段階でさまざまな領域に関心を持つよう教育しておく必要があると私が感じるのも、まさにこの点が関係しているのです」。このようなベナールの姿勢は、ナント木材学校で彼が受け持つ木材標本講座にもよく表れている。「昔から、木材が分析され記述されるのはもっぱらその色合いや密度だけでした。そして私はこれまで顧みられてこなかった匂いでそれをやっているのです! 環境や素材から発せられるこの匂いという次元が、建築においても有機的に統合される日が来ることを私は切に願っています」。
嗅覚デザインが今後ますます盛んになっていくとしたら、それはどのような変化を時代や社会にもたらすのだろうか? そこでは空間は、目に見える壁ではなく不可視の香りで区切られ区分されている、そんな未来が見えるような気がする。デザインされたオブジェはこれまでとはちがって色彩や形状だけではなく匂いによっても鑑賞者を感動させることになるのだろう。高性能ディフューザーによって望み通りの香りを現出させ、いつでもどこでも即座に瞑想状態に入ることができる、などといったことが実現する日も近いかもしれない。驚き、逃避、娯楽……などといったさまざまな感覚的体験を拡張する、そのような無限の可能性を香りは秘めているのである。ただし忘れてはならないのは、その香りを考えなしに無秩序に拡散するのではなくきちんと節度をもって、適切な形で扱うということだ。つまり香りが「うるさく」なるようなことはあってはならず、そこには一定の「静けさ」が確保されていなければならない。香りとは「沈黙」の芸術なのである。その点、ジャン=クロード・エレナの次のような言葉は非常に示唆的な響きを帯びている。「空間を香りで満たすことを私は好みません。そのような空間にあっては異なるそれぞれの匂いを私自身でよく味わい評価することはできないからです。適切に分析され検討された匂いをその名に値する香水へと昇華させること、それが私の仕事なのですから」。これはジャン=クロード・エレナの別の発言とも響き合う。空間やオブジェに対しデザインされた香りが公共的な喜びを与えるために機能するものだとしたら、あくまでも香水は「欲望の対象」として、ただ個人によって求められ偏愛されることがその本来のあるべき姿なのだから……。
「香りに宿る哲学的な側面はもう久しく見過ごされたままです。表現においても軽視されがちな嗅覚は、他の感覚が出尽くした後の最後になってようやく、いかにも変わり種的な添えものとして登場するにすぎないという不遇な扱いを受けています。若きデザイナーたちがまだ学校にいる段階でさまざまな領域に関心を持つよう教育しておく必要があると私が感じるのも、まさにこの点が関係しているのです」(ピエール・ベナール)