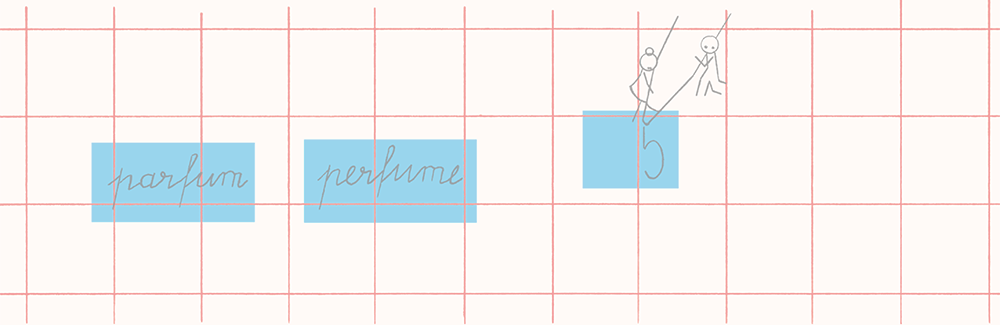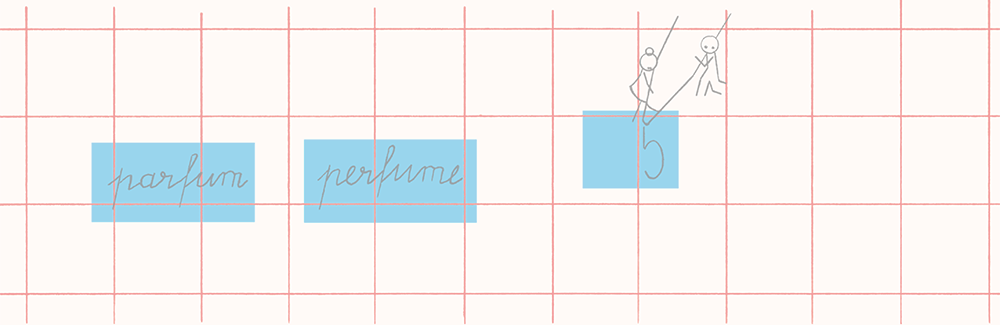彼はパキスタンから留学生としてパリにやって来ていた。学業を修めたあかつきには故郷のラホールへ帰らなければならない。ラホール、それはかのシャリマーの庭園がある地である。そして彼もまたこの庭園と同じ名を持つゲランの香水が好きだったし、この地名を見るたびにこの名香のことが思い出されることを好ましく思っていた。つい先ほど、姉のひとりからフランスからある香水を買って帰ってきてくれとワッツアップを通じて頼まれていたところだった。すると間髪入れず残りの3人の姉妹たちもそれとまったく同じことを頼んできたのだった。彼女たちが喉から手が出るほど欲しがっているその香水の名は何か?シャネルの「No.5」。まさに世界共通の普遍性を象徴する香水である。白地に黒い縁取りが施されたあのパッケージ。その白いキャンバスの上には世界中のあらゆる物語が投影されているのである。むろんラホールに住むその4姉妹の物語も……。香水は『千夜一夜物語』の国々で生まれたわけだが、しかし他ならぬその香水が世界に向けて語りかける言葉として選び取ったのはフランス語であった。だがそれはなぜなのか?そこにはやはり「グー«goût»」が関係しているのではないか?さまざまな意味を同時に含意する多義語であるが、もし「好み」という意味で使われるのだとしたら、その概念はきっと「ジャドール」や「ラヴィ・エ・ベル」によって具現化されるのであろう。「ふたつとも、世界で最も人気を博した香水と言えるでしょう」と、調合会社の高砂香料工業で消費者テスト責任者を務めるダミエンヌ・クヴランはそうコメントする。またこの語には「センス」という意味もある。となると必然的にセンスの「良さ」が含意されてくるわけだが、ここでもやはりフランスの独壇場となる。「シャネルとディオールは世界で最もその名が挙げられる2大ブランドです」とそう同氏も強調している。ロサンゼルス芸術嗅覚学院(The Institute for Art and Olfaction)創立者・校長のサスキア・ウィルソン=ブラウンもまたフランスが今なお世界で覇権を握っていることを認めている。「私たちのワークショップに参加する学生たちにとって、依然として『フランス風の』香水がデフォルトの基準であり続けています。それが彼らにとって馴染み深く、当たり前のものだからでしょう。だからこそ今も多くのアメリカのブランドが商品にフランス語の名前をつけているのではないでしょうか」。だがとどのつまり、このよく言われるフランス的な趣味の良さ、センスの良さとは、いったい何を意味しているのだろうか?ダミエンヌ・クヴランはこう答えてみせる。「『趣味の良さ』と言われるとき、そこには言外の意味としてある種の洗練さが含まれています。私は数多くの消費者テストをこなしてきましたので分かっているのですが、フランス人とは個性のある香水を好むものです。いささか奇妙に思われるくらいの、そんな独創性、あるいはちくりとするようなとがったところ、そしてある種の辛辣さ、エスプリ、それらが少しずつ集められ、その香水を唯一無二なものとするのです」。フランス人が独特な香りを追求するというこの傾向は、この消費者テストの専門家が指摘するように「その香水の外国市場での評価よりも、他者からどう見られているか?ということのほうが重要なのです」という、まさにそのようなことに大きな価値が置かれているからなのだろう。
したがってフランス的な趣味の良さとは、独特な香りをその身にまとい、他者と区別されることによって成り立つものなのである。しかし単に差別化されるのではなく、「君は本当に良い香りだね!」と言われるような、ある種の卓越性を保持したうえで区別されることが求められる。それとともに、「グー«goût»」の今ひとつの意味である「審美眼」を発揮できるかどうかということも問題となってくるだろう。すなわち良いものを、洗練されたものを区別し識別することのできる能力のことであるが、ここでもダミエンヌ・クヴランが見るように、フランスの消費者たちは香りをブラインドで嗅ぎ当てたり、記述したり、識別したりする能力に秀でているという。だがその一方で、底意地の悪い人々が口々に不満を述べたてるように、またある大手ブランドのマーケティング部門責任者も当てこすりのようにこう表現したように、フランス人の肌からは「けばけばしい香りがぷんぷんする」と、そう非難されることがこうも多いのはなぜなのか?つまり自分にとって良い趣味であると信じこんでいるものは、別のものにとっては悪趣味なものに他ならないということなのだろう。それについてはモード史研究家のオリヴィエ・サイヤールも次のように注意をうながしている。「その『趣味の良さ』というものに対しては慎重にならねばなりません。それはある時代のおける単なる慣習にすぎないのですから」。確かにそうだ。かつてはゴミ箱行きになっていたジャン・ポール・ゴルチエの缶詰め形の外箱が今ではアイコンそのものとなっているし、90年代に発売された当初はそのあまりのプラリネの甘ったるさに正統派たちから激しく糾弾された「エンジェル」も、今やほとんどクラシカルな香水と言っていいほどの貫禄を漂わせている……。ニッチブランドが生まれたのもこのフランスだということにも注意を向けるべきであろう。ニッチフレグランスとはすなわち、ある確固としたスタイルあるいは流儀(そしてそれもまた「グー«goût»」の意味のひとつなのである)によって貫かれ、大多数から区別されたいとそう願うものたちのために作られた作品の数々だ。換言すれば、「フレンチタッチ」を極限まで追求したもの、ということになる。
発信者としてのアマチュア
2000年代なかばごろからこうした新興ブランドがぞくぞくと増え始めることになる。フランス香水の黄金時代に立ち返ることを目指す、言わば懐古趣味的な彼らのメッセージが拡散されるのと期を同じくして、ブログや香水専門のディスカッションフォーラムが登場し、盛んに議論が交わされるようになった。一般大衆からは拒否された香りを含め、ガルバナムの青々しいノートからシベットの動物的な香り、そしてシプレやレザーの香りにいたるまで、そうしたある種熱狂的な愛好家たちの原動力となる香水知識は、上記のような言わば疑似的な「学校」によって幅広く形成されたのだった。個性的な香りを求める「フランス的」嗜好を持った人というのは「古風」な、したがって今の価値観で言えば「突飛な」特徴が際立った香水を好むものであり、それゆえいっそう彼ら自身も悪目立ちしてしまうものである。だがそのことは裏を返せば、差別化が図れるということでもある。「パフューミスタ」と呼ばれる人々がいるが、彼らを形容する言葉はさまざまだ。嗅覚版ヒップスター、香水という新たな芸術をめぐる批評家あるいは歴史家、自らも作品を作るクリエイター、などなど。いずれにせよ、彼らは歴史というゴミ箱のなかに捨て去られたクラシカルな香水を発掘することが大好きだ。ビンテージ香水を偏愛する一方で、新たなる個性豊かな香りを探し出しては賞賛し祭り上げるといったことも好み、ときにローカルで小規模なブランドが彼らの後押しによって一躍グローバル市場に躍り出るといったことさえあるほどだ(昨今の香水批評言説を作り上げたと言っても過言ではないルカ・トゥリンによって見出されたマレーシアのブランド、オーフォリーの「ミヤコ」が2016年度のアート・アンド・オルファクション・アワードを受賞したことは記憶に新しい)。
だが上記を見れば明らかなように、今ここに進行しつつある嗅覚の国際化においては、英語が新たな「共通言語」としてフランス語に取って代わりつつあるのだ。パリはもはや香水の首都であることをやめ、さまざまな趣味趣向や知識が毛細血管のごとく方々へ拡散されるなかでの結節点、中継地点のひとつにすぎないのである。それまで一部の専門家たちの専売特許であったものが次第に民主化され、グローバル化されていく。密やかに組織されたネットワークにより本来主流であるところの商業流通経路が迂回され、回避され、デカント(小分けにされた香水サンプル)の交換や売買が促進される。いくつかの企業は個人向けに少量の原材料を提供し始めている。かつてはただの愛好家にすぎなかったアマチュアたちが、今や自身がいっぱしの発信者として活動している。彼らは香水を論じる際にもしばしば文学や音楽や科学を混じえ、そうした分野横断的かつ、専門用語や造語を多用し(「突き刺すようなウッディ」あるいは「フルーティチュリ」などがその例だ)ほとんど内輪でしか理解できないような、そのような新たな言説を生み出しつつある。そんな風に今はただ文章を書いているだけの彼らのなかからも、例えばかつて『カイエ・デュ・シネマ』の若き書き手たちからいく人もの映画監督が輩出したように(ゴダール、トリュフォー、シャブロル、ロメールら)、自身でブランドを立ち上げ香水を作るようになったものたちもいる。
このような香水版ヌーヴェル・ヴァーグにおいても、その定義はやはりフランス的「クラシックな」スタイルとの比較のもとに把握される。だが一方でそれはまるで、1980年代のマーケティング革命が起こらずに業界全体が商業主義に陥ることもなかった、そのような別の宇宙から派生したもうひとつの黄金時代の復活を目の当たりにしているかのようなのだ。そしてそのような並行宇宙が本当にあったのだとしたら、ひょっとしたら以下に挙げるように、偉大なるフランスの香水産業はフランス国外からやって来た調香師たちによってフランス語以外の別の言語で表現され、理解されていたのかもしれない。まずはヴェロ・プロフーモを立ち上げたスイス人のヴェロ・カーンだが、彼女の作り出す作品は彼女自身の香水への深い造詣に裏打ちされながらも、まるで素朴派の芸術作品を目にしているかのような喜びに満ちたバイタリティを備えている。そしてパピヨン・アーティザン・パフュームスのリズ・ムーアはイギリス出身で、始めは独学で調香を学んでいたが後にフレグランス・ファウンデーションに学んだ。ヴェロ・カーン同様アロマテラピーを通じて香りの世界に入っており、彼女の最初の作品「アヌビス」は、ルカ・トゥリンをして「現代版『夜間飛行』」と言わしめた。シリアのカターニャからは元電気技師のアントニオ・アレッサンドリアが現れた。偉大なる黄金時代のスタイルに基づいた香りのオペラを作り出し、その壮大さはベッリーニの作曲したオペラに登場する歌姫たちにも引けを取らない。タイからパリへと移住し、始めはビンテージ香水のコレクターとして活動していたピサラ・ウマヴィジャニもまた同様にクラシックの時代から再出発し、自らのブランド、ドゥシタを携えグラースからバンコクへと、すなわち現在地であるフランスから自らの出自へと逆行するかのような道を模索した。彼女の作品「シヤージュ・ブラン」は、まさにジェルメーヌ・セリエが調香した「バンディ」が熱帯からやって来たかのような香りを持っている。
「パフューミスタ」は歴史というゴミ箱のなかに捨て去られたクラシックな香水を発掘することや、新しい個性的な香水を賞賛し祭り上げたりすることを好む。
アメリカン・メイカーズによる革命
1964年のヴェネツィア・ビエンナーレにおいてロバート・ラウシェンバーグが勝利をおさめたことで、アメリカの絵画によってパリの名は現代芸術の地図から完全に駆逐されたかのようだった。一方でアメリカ発の香水はと言えば、「インヴィクタス」や「ブラック・オピウム」を始めとしたフランスの名香を王座から引きずり下ろすという悲願をいまだ達成できずにいる。だがそれはそれとして、ケンタッキー州ルイヴィルにある香水ショップ、アメリカン・パフューマーのサイト上には、二十世紀のアヴァンギャルドたちの掲げたマニフェストよろしく、次のような宣言が声高に叫ばれているのを目にすることができる。「さあ、アメリカ香水革命の到来である。大手ブランドやマーケティングの命じるキャンペーン、消費者テストなどといったくびきから解放されたアメリカの調香師たちは、今なお果敢に世界最高峰への挑戦にその身を投じている。香水ボトルの『中身』だけを問題とするならば、旧世界の神殿騎士たちの敗北はもはや時間の問題であろう。[...]われらが調香師たちは香水の規則を学び、そしてその規則を破り侵犯することで驚嘆すべき成果を挙げている。こうして新たなる伝統が書き換えられ、古きパラダイムは音をたてて崩れ去るのである」。
初期のビール醸造家やナパヴァレーの先駆的なワイン葡萄栽培者、あるいは前衛的なシェフたち、権威や伝統に抗いながら奮闘する彼らの姿が目に浮かぶ。そんな文章だ。アメリカ香水の未来へと捧げられたこのマニフェストが暗黙のうちに前提としているのは、いわゆる「メイカーズ文化」である。ここで言う「メイカーズ«makers»」とはすなわち、単なるいち消費者であることに飽き足らず、それがロボット工学であれビールの醸造であれ、はたまた遺伝子工学であれダンスミュージックあれ、ガラクタいじりから始めて純然たるクリエーションを成し遂げてしまうような、そのような情熱に燃えた人々のことを指している。ジョン・ビーベルもそんな「メイカーズ」のうちの一人である。彼は画家であると同時に、ソフトウェア開発者であり、香水情報サイト「フレグランティカ」の寄稿者のひとりでもある。そして「ジャニュアリー・セント・プロジェクト」を立ち上げてからは、ひとりの立派な香水クリエイターでもあるというわけだ。「アマチュアの調香師や化学者であること、それこそが現代における刺激的な探検なのです。アメリカの香水のために未来へとつながる次なるステップを作ること、それこそがわれわれの目標に他なりません。われわれの香水が形式やスタイル、あるいは因習や社会階級といった制約から解き放たれ、いつの日かフランスやアラブのフレグランスと同じような響きを持つようになること、それこそがわれわれが願っていることなのです」、とそのようなコメントをビーベルは残している。ジョン・ペッグもまたアマチュア=発信者として、始めは「ケロセン(灯油)」というハンドルネームで動画配信者をしていた。そしてその名はそのまま、後に自身が立ち上げるブランド名となる。本来であれば、ジョン・ペッグは地元ミシガンに住む多くの人々と同じように自動車産業を一生の仕事にするはずであったが……。「私の行う行為、なすことのすべてにDIY精神が宿っています。ギターやベースを弾くことでも、曲や物語を書くことでも、あるいは最近夢中になっている香水制作もそうですが、何でも自分自身でやってみなくちゃ気がすまないんです」。完全なる独学であるにもかかわらず、現在彼の作品はパリで最も先鋭的なショップとして知られるドーヴァー・ストリート・パルファン・マーケットに並んでいる。「ブロークン・セオリー」「アンノウン・プレジャーズ」「ダーティ・フラワー・ファクトリー」などに対し興味を抱きこそすれど、もしかしたらフランス的香水に慣れ親しんだ人々の鼻にとっては、彼の作品は業界用語で言うところの「トゥイユ」、すなわち色々なものを考えなしにごちゃ混ぜにしたもの、まとまりがないもの、といった印象が拭えないかもしれない。一方で香水情報サイト「ベースノーツ」ではレッドネック・パフューミストのハンドルネームで知られるニール・スターンバーグは、そのような無教育な背景こそがジョン・ペッグの個性に他ならないのだと強調する。そのような点こそが彼をしていまだ誰も足を踏み入れたとのない道へと進ませているのだから、と。「とてもアメリカ的な香水だ、と私は思います。まるで初期のジャズみたいに、専門的な教育なんてどこ吹く風、しかし一方では途方もない魅力を備えた、『これから何かが起こる……』そう思わせてくれるような香水です」。
これは新たなる美学の到来なのか?
こうした新たなる動きが合衆国という枠内にとどまるものではないとしても、彼ら「メイカーズ」的調香師たちが最も活発に活動しているのがここアメリカの地であるという事実に変わりはない。そしてこの活気にわきたつシーンの中心に、まさに先のロサンゼルス嗅覚芸術学院があるわけだが、同学院では多様性を重視したアプローチが取られるとともに教材もオープンソースとなっている。こうした方針は何かと秘密主義に陥りがちなこの業界の伝統の対極を行くものであるが、おそらくはアメリカ的ハッカー文化にルーツを持つモデルなのだろう。「香水は閉ざされ密閉された空間のなかに生きているものではありません。香水は世界のなかに存在しているのであって、世界に向けて開かれるべきなのです。私個人としても、香水はあくまで大衆的なメディアであると思っています」と、そう校長のサスキア・ウィルソン=ブラウンは強調する。「決して『フランス的な』伝統的アプローチを批判したいわけではありません。しかしまだ試みられていない、別の伝統だってたくさんあるのではないでしょうか。専門知識とは、フランスのクラシックな手法を知っていることだけを意味するものではありません。自分が何をし、何を作っているかが分かること、材料、素材を適切に扱えること、それこそが真の専門性なのではないでしょうか。当学院としては、それがしっかりと熟慮され考え抜かれた方法である限り、何が良い方法で何が悪い方法かといった区別はありません」。
ある人々にとっては「トゥイユ」にすぎないものが、別の人々にとっては新たなる美学の到来に他ならないというわけだ。しかし彼ら独学の作家たちが、すなわち彼らの支持者同様ネット上で知識を得て教育を受けたものたちが、果たして旧来の支配的パラダイムから出てきたものと同じ土俵で評価・判断されてよいものなのだろうか?いや、だがそもそもこの現象における真の興味深さとは、彼ら嗅覚的ハッカーたちの自由さのなかに、そして公式的な言説から逃れ、独自の制作方法をわがものとするそんな彼らの姿のなかにこそあるのではなかったか?「知識は蓄積されていくとともに発展し、共有、交換されます。そしてその知識に今誰もがアクセスできるのです。未来はとても豊かなものになるでしょう!私たちは現在とは異なる新たな領域に足を踏み入れていくことでしょう。よりローカルな表現を、そしてその地域にしかない材料源を探し求めるようになるでしょう。もっと豊かなものを……と、そうどこへでも足を運ぶようになるでしょう。そうなることを私は願っています」と、ダミエンヌ・クヴラン。一方ルカ・トゥリンはこう断言する。「世界は広い。ウェブとフェデックスが出会ったことで、今や誰もが香水業界で成功できるチャンスを持っています」。トルコからタイにいたるまで、香水を語る際には今や英語でやり取りされるようになり、かくしてここに嗅覚版バベルの塔が築かれたのであった。イジプカ(香水・化粧品・食品・香料国際学院)で行われた「フランス式の」調香セミナーに上海から訪れていたひとりの若き化学者も、香水業界に忍び寄る多(他)言語状況について次のように予言していた。「私たちが自然を理解するしかたはまさにそれぞれでまったく異なるものなのです。それこそ言葉や文字にいたるまで。いつの日か香水は中国語を習得せざるを得なくなるでしょう」。ある賞の初の授賞式において中国のニッチブランドが選出された今日において、その言葉は今や現実のものとなっている。受賞作のひとつであるコン・バイの「インセクツ・アウェイクン」というその名は、中国の暦で言うところの、春先に轟く雷鳴によって冬眠から起こされる虫たちのことを指すのではなかったか?その雷が鳴るころにはきっと、30億の鼻がいっせいに目覚めるのだろう。
この現象における真の興味深さは、彼ら嗅覚的ハッカーたちの自由さのなかに、そして公式的な言説から逃れ、独自の制作方法をわがものとするそんな彼らの姿のなかにこそあるのではないか?