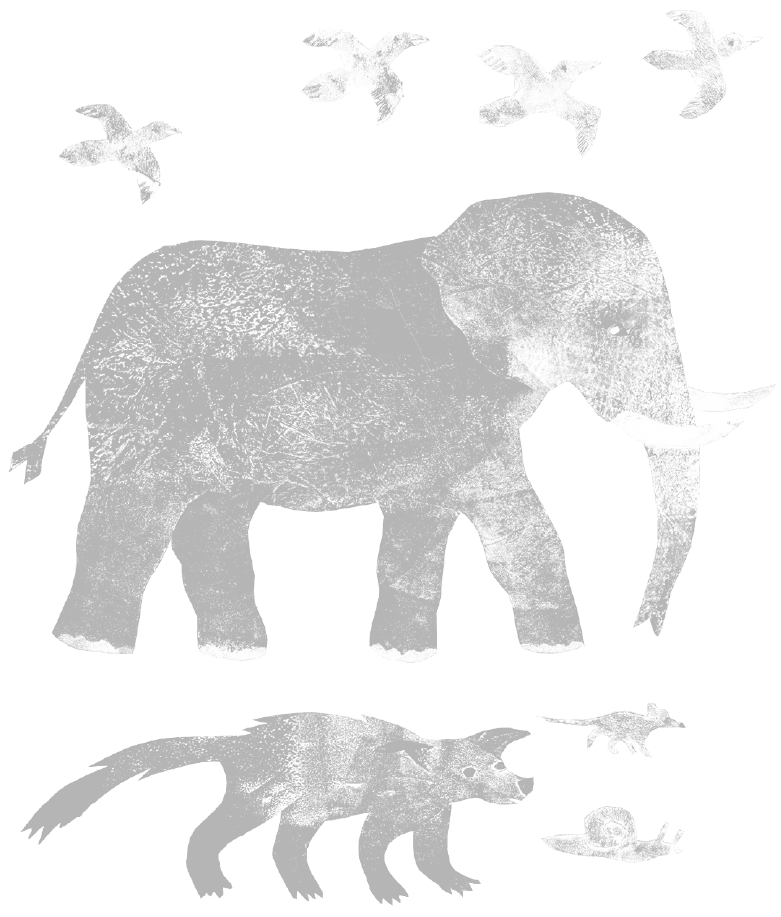動物には並はずれた嗅覚能力が備わっているとよく言われる。犬は人が立ち去ってから何時間が経過してもその跡を追跡することができるし、雄の夜蛾は何百メートルと離れた雌の匂いを見事にかぎ当てることができる。さらにサメはオリンピック規格のプールの水中に落ちたわずか一滴の血の匂いを感知できるという。そう考えると人間の嗅覚がいまいちぱっとしない感は否めないが、しかしこれはひとえに、動物的パフォーマンスを発揮するための訓練や教育が欠けているというだけの話なのである。非凡なる才能を持った調香師、ワイン醸造技術者、美食家たちを見ればそうと分かっていただけるはずだ。あるいは合衆国では最近こんな実験があった。そのなかで被験者たちは目隠しをされ耳をふさがれた状態でチョコレートの匂いの跡をたどるよう求められるのだが、彼らはその実験を犬と同じくらい首尾よくやりおおせたのである。さらに訓練を重ねるごとにその速度は向上したのであった。
生きとし生けるものたちが環境に適応するために編み出した方法は、尽きせぬ驚きの源泉である。ほとんど無限とも言えるほど外形や生態を異にする動物たちであるが、そうした多様性とは関係なく、いくつかの不可欠な生理的機能に関してはどの種にあっても確保されている必要がある。
触覚および化学的感覚(ここでは嗅覚・味覚を指す)は、(生存にとって欠くことができないゆえ、その原初から存在するという意味において)最も「原始的な」感覚であると言えるだろう。これらの感覚の働きによって、環境のなかで自身のいる場所を知り、あるいは食物を見つけたり、毒性のあるものを避けたりといったことが可能となるのである。これらは単細胞生物の段階からすでに存在していた。多細胞生物にあっては五感、あるいはそれ以上の感覚があるかどうかはまた別の議論が必要となるであろうが、いずれにせよこれらの感覚の機能は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚といった複数の「システム」によって支えられている。そしてその「システム」とは(光や音などの)物理的メッセージ、あるいは化学的メッセージを受け取り処理するための組織の総体を指している」。
魚類から鳥類、そして哺乳類にいたるまで、あらゆる脊椎動物において嗅覚のシステムは同一のコンセプトに基づき設計されており、繁殖や社会関係、環境での位置確認、食物の獲得など、個体や種が生存するために不可欠な事項に関わる機能がそのシステムによって保証される。食事のメニューが草食、肉食、魚食であるかに関わらず、動物たちは食糧が発する匂いのおかげでその食糧を見つけることができる。動物の鋭い嗅覚は、ときに驚くほど遠い距離からでも生存に必要な獲物や植物を見つけ出す。捕食動物や遊牧する動物たちもまた同様に、場所、同種の仲間、そして別の種から発される匂いを頼りに、自分が環境のなかにいる位置を確認する。
また嗅覚は交配と繁殖のプロセスにおけるさまざまな段階にも関わってくる。有性生殖は世代ごとに遺伝子を再配列するため、進化論の観点からは有利となる。刻々と変化し続ける条件に適応しやすくなるためだ。だがその有利さの反面、雌が繁殖期に入った時期に合わせて自らの伴侶を見つけ出す必要が生じてくる、といった労もある。雌から発される分泌物の匂いによって、その雌が繁殖に適した状態になっているのかを判断することが可能となる。このような方法はテリトリーへのマーキングにも使われ、これは主に雄によって行われる。そして出産の後は、母と子の相互識別は互いの体臭によって確認される。
同種間で発せられる多様なメッセージに対応するために、いくつかの脊椎動物は鼻腔内の嗅上皮から嗅球へと接続するいわゆる「主要な」嗅覚系に加え、ヤコブセン器官という名称でも知られる(人体には存在しないが、その名残りは認められる)鋤鼻器官など、ひとつないしそれ以上の別の嗅覚経路を持っている。
以下に紹介する動物たちは非常に優れた、しかも珍しい、予想外の嗅覚的特性を有しているため選ばれた。生きるためにそれぞれの生態環境を最大限利用する多様な生物たち、ここに挙げる動物たちはその格好の例であろう。

By Roland Salesse

「さまざまな嗅覚動物たち」
ロラン・サレス
仲間同士でのコミュニケーション、獲物や捕食者の存在を察知すること。多くの種にとって嗅覚は中心的な役割を果たしている。ここではそのなかでも並はずれた、驚くべき嗅覚的特徴を持つ種に焦点を当てる。
「カタツムリ」耳は聞こえない、視力も悪い、しかし途方もない嗅覚
子どもたちに対してはよく、カタツムリに生えている触角は目なんだよ、という風に語られる。実際カタツムリには2対4本の触角があり、確かに上側のツノには目が含まれているのだが、それは未発達で不完全なものである。これらの触角には鼻も組みこまれているのだが、この鼻というのが大変優れた機能を有している。庭師やその庭で作られるレタスにとっては災難と言う他ないだろう。腹足類は聴覚を持たず、食物を見つけたり、仲間のいる場所を特定したり、行くべき方向を決めたりする際には嗅覚に頼ることになる。カタツムリは脊椎動物ではないものの、その脊椎動物と同じように鼻腔内に上皮を有し、その上皮には嗅覚受容体を備えた嗅神経が含まれている。そしてこの神経細胞がさらに軸索と呼ばれる突起を、脊椎動物における嗅球に似た構造を持つ(そしてカタツムリにとっての脳に相当する)プロセレブロンに向けて伸ばすのである。カタツムリの有する全神経の実に80%が匂いの知覚と嗅覚情報の処理にあてられている。さらに触角には、再生可能という驚くべき特性がある。つまり鼻を切除されても、また生えてくるのである。
「犬」凄腕の探偵
嗅覚が発達した動物としてまず思い浮かぶのがこの犬なのではないか。何も大型犬に限った話ではなく、フォックステリアもまた異論の余地なく優れた狩猟犬である。犬の嗅覚は祖先である狼より受け継がれてきたものであるが、その優秀さは何よりもその解剖学的な特徴に起因する。犬が鼻をくんくんとさせるとき、鼻先で地面の匂いを含んだ空気を吸いこむ。一方で鼻腔の後ろから息が吐き出され、その吐気が表面のほこりを巻き上げることによって、検出の可能性が高まるのである。さらに彼らの鼻の形状、少なくとも長い鼻を持つ犬種のそれは、大きな嗅粘膜(最も大きな個体では200㎠にもおよぶ)のためのスペースを担保する。そしてその嗅粘膜には最大で200万個もの嗅覚ニューロンが含まれている。人間の嗅粘膜が5㎠、嗅覚ニューロンが5百万個であることを考えれば、この差は明白である。
これらのニューロンはそのそれぞれが、約800個ある嗅覚受容体遺伝子のうちひとつだけを発現する。これに対し人間の嗅覚受容体遺伝子は約400個にとどまる。極めつけは、この四足動物の嗅球は人間のそれよりわずかに大きくできていることだ。彼らの脳が人間のそれより6倍も小さいにもかかわらず。彼らの高い学習能力があってこそ、とりわけ猟獣や人の追跡に役立てられるなど、犬は私たちにとって最も古く最もかけがえのない友人であり続けているのであろう。犬はある場所を人が通ったことを検知できるだけでなく(その人を探し出すよう命じられたときなど、場合によっては誰が通ったかを識別することもでき)、たった5歩分の距離の匂いをかぐだけでその人がどの方向へ移動したのか特定することができる。だがいったいどうやって? 最初の1歩から5歩目までの、わずか数秒分の微細な匂いの濃度差から彼らはこの情報を導き出しているとでもいうのだろうか。実を言うとそれはまだ解明されていない。
「カエル」ふたつの世界のあいだで
魔女に仕える動物、美貌の王子に変ずるもの、気象予報の専門家など、そうした多様な呼称がカエルには付与されてきた。いずれにせよ確かなことは、この両生類が空気中でも水中でも匂いを知覚できるという非常に珍しい特性を有しているということだ。鼻腔内は2つの領域に分割されている。中心部に位置する主鼻腔は空気中で呼吸するためのもので、クラスⅡの受容体を持つ嗅覚ニューロンを備えている。このクラスⅡとは空中動物が持つ受容体である。そして最も低い位置にあり水中に浸かる側方鼻腔のニューロンには、魚類が持つ嗅覚受容体、すなわちクラスⅠの受容体が含まれている。カエルの鼻腔に見られるこのような二重性は、脳内での情報処理において鼻腔の次にメッセージが届けられることになる、嗅球においても見られる。そのメッセージを異なる鼻腔が異なる嗅球へと送るのである。
カエルはオタマジャクシからカエルになるわけだが、オタマジャクシはほぼ魚に近い存在である。この段階ではまだ主鼻腔しか持っておらず、そこに魚類の嗅覚受容体が備わっているという形となる。それからカエルへの変態にともない主鼻腔内の嗅覚ニューロンはこのタイプの受容体を放棄し、クラスⅡの受容体がこれに取って代わるのである。これと同時に、クラスⅠのみを搭載した側方鼻腔が現れる。そしてこれと対応する変化が嗅球においても起こる。初期の「水生動物的」嗅球はじょじょに退化し、空気中の匂いを検知するニューロンと受容体に接続された上部が現れじょじょに成長し、やがてそれが主要な部分となる。両生類の多くは幼生段階では鼻孔は閉じているが、変態とともに開く。
私たち人間は100%陸上動物であるが、まだ母親の胎内にいたときには羊水中の匂いを知覚できていたということをすっかり忘れてしまっている。そして成人してからも私たちは自分の鼻のなかに、ほぼすべての哺乳類と同じく魚の嗅覚受容体を持ち続けている。実に5億年以上の進化の過程を経てもこれは失われることはなかったのである。両生類はその生をもって、海上生活から陸上生活への進化論的移行を再現していると言えるかもしれない。
「ビントロング」歩くポップコーン
その見た目から「クマネコ」とも呼ばれるこの夜行性動物は東南アジアに生息し、主に樹の上で生活をする。巻きつく尾を持ち、肉食動物に分類されるにもかかわらず果物と植物を主な食糧とし、ときに卵も食べる。雌は雄よりも大きく、雄を支配する。そして雄雌ともに特徴的な匂いを発するのだが、それは何とポップコーンの匂いなのだ。この匂いはマーキングに使われる会陰腺の分泌液から来るもので、この分泌液は繁殖期になると増加する。2016年にアメリカの研究チームがこの物質を分析し、このスモーキーな、バターと焼けたような匂いの原因が2-アセチル-1-ピロリンという分子であることを明らかにした。この分子を、私たちはいつもキッチンで感じていて知っているはずである。つまりこの分子はメイラード反応によって生成されるのと同じものなのだ。私たちが食材を加熱するとき、(タンパク質や糖などの)無臭の化合物から美食家に好まれる芳香物質が生み出される。それがメイラード反応である。

「ネズミ」社会的感覚としての嗅覚
夜行性動物のネズミは居場所の把握や食糧獲得の多くを聴覚と触覚に負っている。つまり口ひげ(または震毛)を指のように使って、環境中の物体がどこにあるかを特定し、そしてそれが何であるかを識別する。ネズミの生きる社会生活は比較的豊かなものであるが、その多くは同種の仲間を見つけたり、その仲間の地位や性別を見定めたり、あるいは迫りくる脅威を察知するのに必要ないくつかの化学的信号に依存している。
例えば、ネズミは副嗅覚系に属するグリューネベルク神経節という名の器官を通じて、TMTと呼ばれる肉食動物特有の匂い成分を検知する。この成分を検知するとネズミはその場で動きを止め、毛を逆立てる。TMTは捕食者の糞や尿に多く含まれる。興味深いことに、ネズミが発する警告フェロモンにもこのTMTが含まれ、それによってコロニー内の他のメンバーが逃走や防御といった反応を取ることができるのである。
主嗅覚系もまた捕食者の認識に重要な役割を果たしている。これについては日本の研究チームによって行われた実験が明らかにしており、通常この小さな哺乳動物は猫を巧みに避けながら生きるものだが、嗅覚ニューロンの一部を切除すると、猫が近くまで寄ってきても以後まったく気にしなくなったという。この結論はあの権威ある『ネイチャー』誌に写真つきで発表され、その写真のなかではネズミたちは猫の足もとに身を寄せ丸くなっているのだった。この写真を撮るために最も苦労したのは、猫をおとなしくさせておくことだったという。
「北極熊」比類なきハンター
この白熊は同じ進化系統の茶色熊に由来するが、約10万年前に北方へ移住したことによりこの分岐が起こった。以降完全な肉食動物となり、主にアザラシやその他の脊椎動物を捕食する。最も大きな陸生肉食動物の一種である。
あらゆるハンターがそうであるように、北極熊もまた優れて発達した感覚を有し、特に嗅覚に秀でている。匂いを頼りに10km先の氷上で休んでいるアザラシを見つけることができる。景色に溶けこみながら接近し、獲物に飛びかかる。そんな彼らの鼻は水中での狩りにおいても有効だ。アザラシが呼吸をするために氷にあけた穴の付近で何時間ものあいだ虎視眈々とチャンスをうかがい、検知可能な水深1mから1.5mまでアザラシが近づいてきたのをその匂いで感じ取ると、強力な足と爪を使って不意を突くのである。またこの鋭敏な嗅覚をもってすれば、30km離れたところにある死骸を見つけることも可能である。
この大型哺乳動物は先ほどの犬と同様の進化論的変化を恩恵として受けている。鼻先が伸びていることによって鼻腔内に位置する鼻甲介の面積が増大する。鼻甲介は骨に分類される構造物で、主に鼻腔内の空気の流れに影響を与える組織に覆われ、(吸入した空気を温め湿らせるという、寒冷環境下では重要となってくる役割を果たす)呼吸上皮と、数百㎠にもおよぶ嗅上皮を持つ。北極熊は鼻に数千万もの嗅覚神経細胞を有しており、これは彼らにとって大変なメリットとなる。食糧が少ない環境下では遠くから、かつ確実に獲物を見つけることが肝要となるからだ。
「海鳥」鼻に導かれて
鳥類の嗅覚についてはほとんど注目されてこなかった。いくつかの種は嗅覚自体を持っていないとさえ考えられていたほどだ。しかし2004年にニワトリのゲノムが解析され、ニワトリが283の嗅覚受容体遺伝子を持ち、うち218が同一の遺伝子ファミリーに属するものであることが明らかになった。なおこのファミリーに属する遺伝子をニワトリが218持っているのに対し、人間はたったひとつしか持っていない。
海鳥は地上の目印なしに数百、いやときに数千km飛んで戻るべき巣を見つける。そのような芸当が可能なのは地球の磁場を感知しているためだと長いあいだ考えられてきた。しかしカンムリウミツバメ(学名:カロネクトリス・ディオメデーア)の頭に地球の磁場よりも強力な磁石を取りつけたところ、その鳥はイタリア西方に浮かぶピアノサ島にある自身の巣を難なく見つけ出したのだった。一方、リヨン湾内で鼻をふさがれた状態で放たれたところ、巣を見つけるのに大いに苦労している様子が見られた。なかには海岸線を頼りに島までたどり着いた個体もいたが、いずれにせよ鼻をふさがれていない他の仲間たちに比べかなりの時間がかかった。
その嗅覚がデメリットとなることもある。海鳥たちが海に浮かぶプラスチックごみを飲みこみ死んでしまうというケースがあるのである。どうしてそんなごみを食べてしまうのだろうか。ごみに付着している海洋プランクトンが二酸化ジメチルという匂いを発しているのだが、この匂いは人間にとっては不快に感じられるが、プランクトンを食べ、またそのプランクトンを食べる魚も食糧とする鳥たちにとっては、とても魅力的に感じられる匂いだからだ。
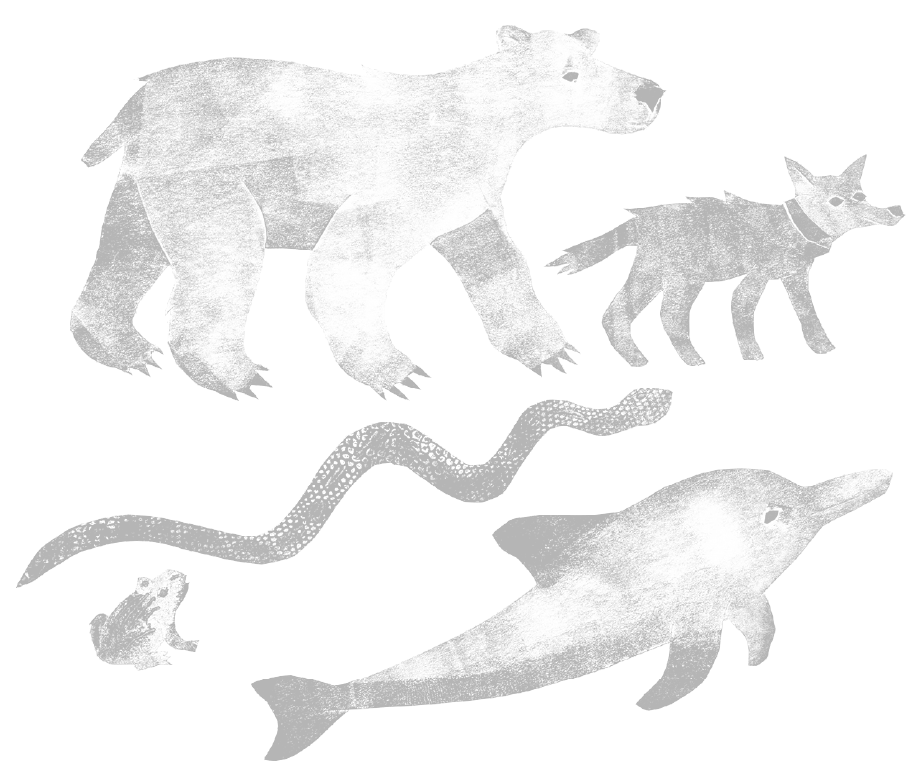
「ゾウ」成熟の香り
ゾウの鼻は長さが1.5mから2mにもおよぶがその実、鼻そのものは嗅覚器官の付属物にすぎない。他の哺乳類と同様、ゾウの嗅覚器官もまた鼻腔内に位置している。それぞれの鼻腔には37の鼻甲介があり、鋤鼻器は10cmに達する。鋤鼻器はフェロモンの検知を可能にする器官であるが、これに刺激を与え活性化させるために、この厚皮動物は「フレーメン反応」を取り入れる。すなわち上唇をめくり上げ、そこから空気を吸いこむ。この方法によって赤ちゃんゾウは生後6ヶ月で母親の尿の匂いを認識できるようになるのである。この匂いは赤ちゃんゾウの記憶に残り続け、その後成体となり、母親と離れて27年たった後もその匂いを識別できるという。
雄の成体は、雌の発情を示すフェロモンを検知するためにこの「フレーメン反応」を利用する。雌のゾウがこの発情状態にあることは稀で、というのも長い排卵前期間に対し、排卵期間はごく短いからだ。フェロモンは雄を引き寄せ、交尾をうながす。このフェロモンは揮発性の脂肪酸の一種で、126種の昆虫が発するフェロモンの組成にも含まれているものである。蝶がときどき雌のゾウの周りに群がっている光景が見られるのはこのためである。
アジアゾウの雌は娘や未成熟の息子とともに母系の群れで生活する。雄は12歳から15歳ごろ独立する。群れから離れ一匹だけで自活するか、一時的な小グループを作るかで分かれるが、しかし成体として成熟するのはもう少し先の20歳ごろである。思春期が近づくと、「ムスト」と呼ばれる期間に入る。雄が断続的な性的活動に手を染め始める時期を指す。この期間中、側頭腺からは花や蜂蜜のような香りの分泌物(実際そこに含まれている成分は蜂蜜の成分と似たものがあり、またミツバチの警告フェロモンの一部成分とも類似性がある)が出ている。この分泌物は年上の雄に対し、若い雄が自分は競争相手ではないと示すものである。そして雄が成年に達したとき、この分泌物は変質し、臭いものとなる。そこに含まれる成分の一部は、米国の松に寄生する甲虫「デンドロクトヌス・テネブランス」のフェロモンにも含まれている。大人のゾウの発するその匂いは年下の雄を遠ざけ、雌を引き寄せる。なおムスト期の匂いが強いほど、その雄は支配的になる傾向があるという。
「ヘビ」口のなかの鼻
ヘビは主嗅覚系を有しているが、鋤鼻器系も発達している。その鋤鼻器への経路として哺乳類の場合は鼻腔を通過するのに対し、ヘビにおいては口のなかを通る。このメカニズムをヘビは性的メッセージを受け取ることに役立てるだけでなく、獲物を探すことにも使うのだが、以下に紹介するようにそこにはかなりの独創性が見られる。
獲物は地面に、匂い分子、そしてタンパク質を始めとしたその他の非揮発性分子をその痕跡として残す。ヘビは地面を這って進みながら、そのフォークのような二又の舌を揺らし、痕跡として残された化学成分を収集する。そして舌の両端を鋤鼻器に差しこみ、関心を寄せるに値する物質を受容体ニューロンに接触させるのである。またこのシステムは仲間同士が集まる際(交尾をするために多数のヘビが「結び目のように絡まり合う」あの有名な現象)、そこで発される化学的メッセージを読み取ることにも利用される。
「イルカ」無嗅覚って、本当に?
哺乳類のなかには、約5千万から6千万年前に適応様式のちがいから海中生活に「戻っていった」とそう不当にも言われている3つの主要なグループがある。海牛目(マナティー、ジュゴン)、鰭脚目(アザラシ、アシカ)、そして鯨目である。
この鯨目に分類される動物たちは彼らに最も近い「親戚」の反芻動物が採用していた菜食主義を放棄し、それにともない彼らの食糧探知の能力も変化したのだった。クジラの上顎に備わるヒゲ状の繊維は海水といっしょに飲みこんだ小さい獲物を濾過するフィルターの機能を有しているが、このクジラには嗅覚が残された。それに対しあの有名な水中ソナーで食糧となる魚やイカ、タコを検知するイルカからは嗅覚が失われたと見られている。そしてそのイルカにはさらに、顔の部位に大きな解剖学的変化も起こった。人体では上側の歯から鼻の位置に相当する上顎骨がイルカにあっては後方へ向かって大きく伸び、その結果ただひとつあった鼻孔(噴気孔)が頭頂部まで押しやられたのだった。これにより鼻腔の機能もただ呼吸をするためだけのものに縮減され、それにともない嗅皮も消失したものと見られている。さらに咽頭においては呼気経路と消化経路が交差する位置に2枚の軟骨の薄板があり、これが2つの経路を分断することでレトロネーザル(鼻腔ではなく口腔から匂いを感知すること)が起こることを妨げている。
以上がイルカに嗅覚があるとは考えにくいとされる理由であるが、近年フランス国立科学研究センターの研究チームが行った調査では、何頭かのイルカが化学物質として拡散された食物の匂いに引き寄せられているという結果が観察された。そのことはイルカが必ずしもソナーだけには頼っていないということを示している。またこの研究ではイルカの鼻腔、そして舌の付け根の部分に陸生脊椎動物が有しているものと似た嗅覚受容体が存在することが確かに確認されたのであった。もしかしたらその効果範囲は近距離に限られたものであるかもしれないが、この受容体が存在するということは、イルカが獲物から発される匂いを検知しているという説に対する説得力のある説明になっていると思われる。