花々、葉っぱ、樹脂、材木。古来、新石器時代より、人類は香りを持つ素材を神々に捧げて感謝の意を表してきた。古代エジプト人、ギリシャ人たちは植物を燃やし、香油を神像に塗ることによってその美しさと力強さを称揚した。以来匂い物質の使用は増加の一途をたどるとともに、その用途は多様化し(葬儀を始めとした祭祀、医療および公衆衛生、あるいはその他の世俗的使用など)、配合は複雑化した。植物性の天然原料が主流であったが、十九世紀における有機化学の発展とともに合成成分がじょじょにこれに取って代わるようになった。毒性、原料としての稀少性、生産上の制約、コスト高といった、これまで天然原料につきまとっていたさまざまな問題がこうした合成成分の登場によって解消された。こうして、人類の遺産として継承されてきた多くの香料植物が忘却の彼方に失われていったのだった。それでは、その失われた香りの庭園を散策してみよう。
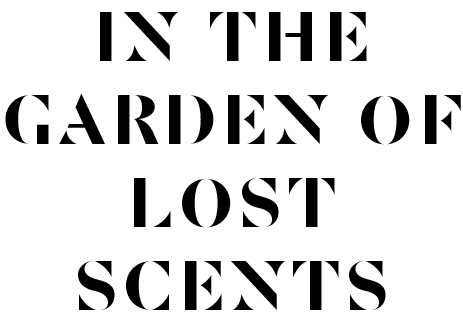
By Anne-Sophie Bouville and Xavier Fernandez

失われた香りの庭にて
アンヌ=ソフィ・ブーヴィル、グザヴィエ・フェルナンデス
供給困難、高価格、有毒性、あるいは単に趣味が変わったためか。こうしたさまざまな理由により、なかには古代より使われてきたものさえあったいくつかの植物性原料が調香師たちの香りのパレットから消えていった。そのいくつかは代替品に置き換えられたが、残りは失われたままである。この失われた植物の多くを、あなたたちはグラースの国際香水博物館の庭園のなかで発見することができるだろう(p.136のスケジュールも合わせて確認されたい)。

カラムス
古代において多用されていたカラムスの根茎(学名:アコールス・カラムス、または芳香性アコール [カール・フォン・リンネにより命名])は当時より神聖なものとされていた。甘い、力強くウッディな、それでいてスパイシー、かつ土っぽくカンファーな香りもするこの素材は、エジプトで供物として用いられていた固形香料キフィを作るためのレシピの、そのすべてのバージョンに含まれている。『出エジプト記』のなかで塗油されるオイルにもこのカラムスが含まれているとの記載がある。そしてその聖油は現代でも一部の儀式で用いられている。中世に入り黒死病が流行した時期にもカラムスはよく用いられた。「四盗賊の酢」という有名な解毒剤の成分として使われ、疫病に倒れた犠牲者たちの所有する物品を略奪して回った盗賊団にちなんで名づけられたこの酢は、盗賊たちを感染から守ったと言われている。今日においてカラムスの使用は規制上の理由から厳しく制限されている。事実、その精油の主成分であるアルファアサロン(約1%)とベータアサロン(最大で96%)には神経毒性と発がん性が確認されているため、その使用は国際香料協会(IFRA: International Fragrance Association. 業界を主導する機関である)によって管理指導されている。完成品における総濃度が0.01%を超過することは認められない。

ヒヤシンス
1920年代にはヒヤシンス(学名:ヒヤシンスス・オリエンタリス [カール・フォン・リンネにより命名])はフランス南東部でさかんに栽培され、力強いというよりかは攻撃的な印象さえ与える、グリーンかつフローラルな香りを持つアブソリュートが生産されていた。その目的のために最初に採用されたのは(精製脂に花びらを長時間浸し香りを吸着させる)アンフルラージュの技法であったが、しかし早々に、労働力コストのより低かった揮発性溶媒抽出法に取って代わられた。が、非常に低い収率から(コンクリート0.13%から0.22%。アブソリュートは10%から14%)ヒヤシンスのアブソリュートは高価であった。1960年にはその価格は1キログラム12,000ドルを超えたという。そのためヒヤシンスの香りは合成成分に置き換えられるようになっていった。現代いくつかのフレグランスにおいて強調されているヒヤシンスのノートは、さまざまな素材の組み合わせから構成されている。例えば1930年代におけるあるレシピには、ジャスミン(アブソリュートとベンジルアセテートから)、天然イランイラン、合成ローズ(フェニルエチルアルコールから)、バニラ(ヘリオトロピンとバニリンから)、スパイス(オイゲノールおよび/またはイソオイゲノールから)といった香りから構成されたアコードを見ることができる。さらに1943年に「ヒヤシンス・ボディ」(IFFが商品化)のような人工分子も開発された。
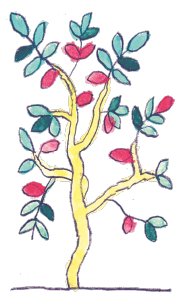
ユダヤ・バルサム
ゴム樹脂、樹脂、そしてバルサムは、古代より固定剤や原材料として香水に使用されてきた。なかでもユダヤ・バルサムは同名の低木(学名:コムミフォーラ・オポバルサムム [カール・フォン・リンネにより命名])から採取され、その匂いはレモンのエッセンスと松脂の持つウッディな側面を合わせたものに近い。「真正なるバルサム」とも呼ばれるこの粘度のある液体は、古代では高貴なる香水のなかに、特にパルティア王国の王室の香りを作る成分として用いられた。バルサムの木にはさまざまな伝説があり、なかでも有名なのはキリストの十字架がこの木で作られたというものだ。また別の伝説によれば、ユダヤ人はユダヤ戦争(紀元66年から70年)にてローマ人に敗れた後、エルサレムが略奪されるなかでその植林地を破壊し、その後残された数少ない現物の使用を王室と聖職者のみに限ったという。十九世紀になるとユダヤ・バルサムは再び香水に使われ始める。「肌を新鮮に保ち、しわを消すことに優れている」という記述が C・F・ベルトラン著『帝国の調香師』(1809年刊)のなかに見られるが、その後調香師たちのパレットからは消えていった。

イチジク
新たな素材を求める旅の途中にあった調香師たちがイチジク(学名:フィクス・カリカ [カール・フォン・リンネにより命名])の葉の持つ香りに魅了されたのは、ようやく二十世紀も半ばを過ぎてからのことだった。グリーンでウッディ、かつ乳液のニュアンスもある、フルーティーな香りである。とはいえこの果樹の歴史は古く、地中海地域で最も古くから(紀元前4000年ごろから)栽培されていた種のひとつである。その後、揮発性溶媒抽出でイチジクのアブソリュートが生産されるようになる。この粘度のある液体からはクマリンやタバコを思わせるグリーンなノートが長く香り、湿った木の香りがラストノートとして残る。しかしこのアブソリュートのなかに含まれるベルガプテン、プソラレン、キサントトキシンといった(無香性の)フロクマリン類が感作性、刺激性、光毒性を有しているため、香水への使用は1980年ごろよりIFRAから禁止されている。これによって天然のイチジクの葉の香りは分子の組み合わせによる合成香料によって代替されるようになった。しわくちゃになった葉っぱやイチジクの実、ガルバナムの香りを持った「ステモン」(ジボダン)や、フルーティーかつミルキー、クマリンやココナッツの香りもするガンマオクタラクトンなどがその例である。

ガーデニア
ガーデニアが香水に使われた期間は短く、せいぜい一世紀といったところだった。アジア原産のこの小さな低木(学名:ガルデニア・ヤスミノイデス [J.エリスらにより命名])の花から、石油エーテル抽出法によりアブソリュートが精製された。しかし1キログラムの原料を得るためには実に3,000から5,000キログラムのガーデニアが必要であった。したがって(チュベローズを彷彿とさせるような)豊かな白い花の香りを持ち、グリーンなニュアンスをも兼ね備えたこの物質は大変高価であった。1950年ごろにはその使用は稀なものとなり、すぐに合成成分がこれに取って代わることとなった。グリーン、フルーティー、フローラルといった香り的特徴を持つ酢酸スチラリルがガーデニアのそれと近く、一部の調合のなかで代用された。また、ローズ、ジャスミン、チュベローズ、そして他のいくつかの合成分子(アルデヒド、テルピネオール、イオノン)などを組み合わせた種々のアコードによりこの香りを再現することもできた。

ナード
「香り豊かなハーブ」とも呼びならわされたナードは古代よりさまざまな祭祀や療治に用いられた。紀元一世紀には大プリニウスが原産の異なる10種類ものナードを記録し、そのうちインド原産のものに最も多くの記述が割かれている。このインド産のバレリアン(学名:ナルドスタシス・ヤタマンシー[デヴィッド・ドン、およびド・キャンドルにより命名])の根茎は、エジプトのキュフィ、パルティア王国の王室の香り、ローマのナルディヌムなど、当時の有名な香りのなかに調合された。ナードは宗教的な象徴性を担う側面が強く、特に聖書には何度も繰り返し言及されている。ベタニアのマリアがイエスの足(頭であったという説もある)に塗油し捧げたのがこのナードであったという。中世からルネサンスにかけても重宝され、特に王政期にはマリー・アントワネットの寵愛を受けたことでも知られている。2007年にはラルチザン・パフュームが自然素材から調香した「ロード・ジャタマンシィ」をリリース。ナードから抽出される精油の香りの特徴としては、グリーン、スパイシー、ウッディ、土っぽく、そして動物的、と描写されることが多い。しかし今日西洋においてはこの素材の使用は大変稀なものとなり、一部の特別な香水にのみ限定されている。
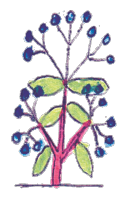
ヘンナ
ヘンナは現代でも消費者からよく認知された素材であるが、とはいえそれは香料としてではなく、葉から抽出された粉末で作られた染料としてである。この棘つきの低木(学名:ラウソニア・イネルミス [カール・フォン・リンネにより命名])に咲く花は早くも古代から高く評価され、パルテア王国の王室の香りやキフィを含む、オイルや軟膏を調合するために用いられた。プルニウスはその白い花の持つ官能的で動物的な香りを指し、かいだすべての人間を蘇らせるだろうと記しているほどで、しかるにその香りの力強さがうかがい知れよう。またヘンナは治療薬として知られる「クプリノン」のレシピにも含まれていた。ヘンナ以外の組成物としては、香草をベースに、ルイボス、カラムス、ミルラ、カルダモン、古酒、オリーブオイル、雨水などが挙げられる。ヘンナ入りの香水は重宝されたが、その価格はローマの貨幣で1ポンドあたり5デナリウス(1枚
あたり3から4グラムの銀貨5枚)と比較的安価であった。このように古代においてはポピュラーだったこの素材も、現在では使用されていない。1974年にヘンナの花や葉から揮発性溶剤法で抽出する試みが行われたが、商業化にはいたらなかった。
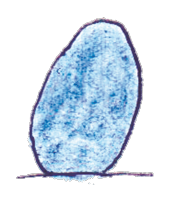
オニキス
聖書には匂いや香料に関する用語が多く登場するにもかかわらず、その組成が詳細に記述されている香りはわずか二例のみである。エルサレム神殿の香炉で焚かれていた物質がこれにあたり、薫香とも呼ばれていたこの物質は現在も香水に使われているゴム樹脂とは異なるものである。『出エジプト記』のなかにそのレシピが記されている。「香料を取りなさい。すなわちスタクテ、香貝、ガルバナム、純粋な乳香を取りなさい。すべて同じ比率でなければなりません。これらをもって薫香とし、調香の技に従ってこれを作りなさい。塩を加え、純にして聖なるものとしなさい」。このなかの「スタクテ」という語はミルラの一種、もしくはスティラックス、ユダヤ・バルサムを指すものとされているが、それらの説にはいずれも植物学的根拠はない。また「香貝」はオニキス、オニチャと呼ばれることもあるが、それが動物性の素材を指しているのか(香りのある貝殻のふたの部分)、それとも植物性の素材のことを意味しているのか(人間の爪に似た外観の花から得られる香り)は解釈が分かれる。あるいはよく知られた鉱物を指しているのだとも言われている。いずれにせよ、これらの成分についてはいまだ多くの謎が残っている。






