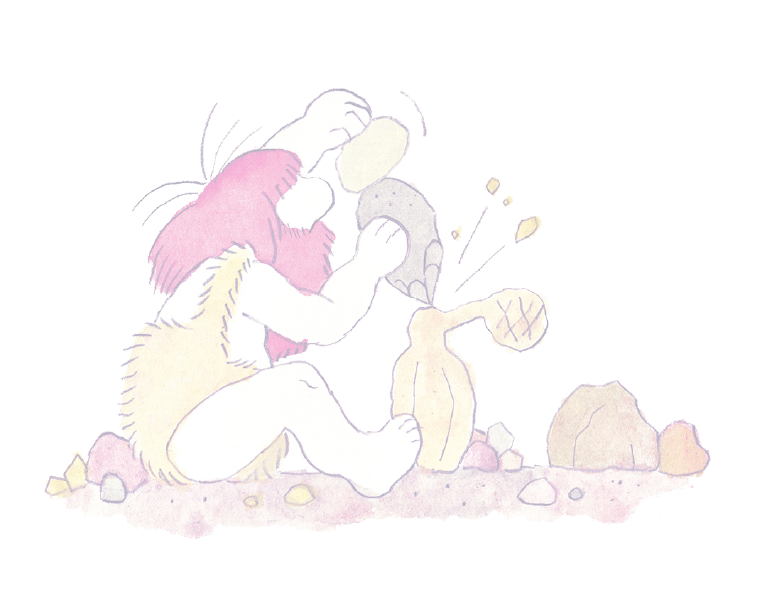十九世紀末、新たな原材料が加えられたことにより調香師たちのレパートリーは豊かになった。そしてそれはアンフルラージュ(冷浸法)や真空蒸留といった抽出技術の改善、さらには揮発性溶剤抽出など新たに開発された技術の結果であった。こうした技術革新の最前線にあったのが「人工香料」である。この呼びかたは当時一般的に用いられていた名称を踏襲したものであるが、これによりフレグランスの配合が根底から覆されることになったのだ。化学者たちの手によりこれらの匂い分子は1860年代終わりごろから本格的に合成され始めた。彼らの研究は十九世紀初頭に開始された精油の分析に基礎を置いていた。分子を人工的に再生産すること。それを実現するためにはまずはその分子が含まれる精油の成分、場合によっては特性、そして可能ならその構造までをも熟知することが求められたからだ。かくしてオーギュスト・カウール、シャルル・ゲルハルト、そして少し時をおいてにオットー・ワラッハらのなした研究成果をもとに、以下のような新しい原料が合成されるようになったのだった。すなわち(時系列順に挙げるとすれば)、苦いアーモンドの匂いを持ったニトロベンゼン(1834年エイハルト・ミッチャーリヒによって)、刈り取られた干し草のような匂いのクマリン(1868 年ウィリアム・パーキンによって)、ヘリオトロープの香りが特徴のヘリオトロピンあるいはピペロナール(1869年ルドルフ・フィティッヒおよび W. H ミールクによって)、バニリン(1874年にフェルディナンド・ティーマンとヴィルヘルム・ハールマンがコニフェリンから、同じくヴィルヘルム・ハーマンとカール・ライマー、そしてジョルジュ・ド・レールが1876年アセチレンオイゲノールから合成した)、人工ムスク(1888年アルベルト・バウアーによって)、そしてバイオレットのような香りのするイオノン(1893年フェルディナンド・ティーマンとポール・クリューガー、そしてジョルジュ・ド・レールによって)。これらの分子が合成されるにいたった経緯は多岐にわたる。匂い物質合成の成功は異なる時代、異なる国のさまざまな研究者たちによる多様かつ膨大な研究のたまものであると言えようが、しかし有機化学がさまざまな分野に応用される過程で期せずして偶然発見にいたることもあった。例えばロンドン王立化学大学助手だったウィリアム・パーキンは、医薬用にキニーネを合成しようとして染料のモーベインを発見したことで知られている。さらに1868年、パーキンはまさに今日彼自身の名を冠した反応によってクマリンの合成に成功した。彼が主に取り組んでいた問題は基礎研究に属するものであったようだが、ある種の偶然が彼を、その後の応用につながるような発見へと導いたとも言えるだろう。キャリアのなかで最終的に専門を変えることになった化学者たちもいた。なかでも有名なのは元は染料の研究で知られていたジョルジュ・ド・レールであろう。1860年代にシャルル・ジラールとの共同でローザニリン・ブルーを、ついでローザニリン・バイオレットを発見、他にも6種ほどの染料を合成し、まもなくこれらの特許を得たリヨンの製造業者ルナール・フレール・エ・フラン(その後ラ・フクシン社を創業)がそれによって大きな利潤を得た。1876年、ド・レールはバニリンの製造に特化した工場をグルネルに設立し、かくして彼は人工香料という新たな道へと身を投じる覚悟を決めたのだった。そのことからもジョルジュ・ド・レールはドイツ人研究者のフェルディナンド・ティーマンおよびヴィルヘルム・ハーマンと並びその分野におけるパイオニアのひとりとして位置づけられ、同年フランスにおけるアセチルオイゲノールを使ったバニリン製造の特許を申請してからは、自らの有する数々の特許をフランスのために役立てた。そしてフェルディナンド・ティーマンとの長年にわたる体系的研究を続けた末に、ついに1893年アイリスの根に関する研究成果を発表する。まさにその成果によってイロンと、さらにはバイオレットの香りの再生産を可能にした初の人工香料として知られるイオノンがもたらされることになったのだ。
民主化への端緒
これらの人工原料は製造コストの削減に寄与し、その結果、香水製品の価格を下げることを可能にした。ムスクがその最たる例であろう。麝香鹿の性腺から分泌されるこの天然の原材料の相場は供給量や時期によって多少の上下こそあるものの、いずれにせよ非常に高額であった。まだバウアーによる最初の合成がなされる前の業界誌『ラ・パフュムリー』には、キロあたり1,400から1,600フランと記されている。実に金の半値に相当する額である。別のさまざまな物質で割ってブレンドする偽造行為が横行するなど供給の面でも問題があった。そのような状況のなか、1888年にアルベルト・バウアーは人工ムスクの合成によって新たな可能性を切り開いたのだった。この原材料は始めこそ(10分の1に希釈され)キロあたり2,000フランで販売されたものの、特許が切れるとその価格は100フランにまで下落した。よく知られた他の合成物質も同様の経緯をたどり、ヘリオトロピンは1879年にはキロあたり3,790フランだったものが1899年には37.5フランと推移し、クマリンは1877年2,550フランから1900年55フランに、そしてバニリンは1876年8,750フランから1900年には100フランにまでその値が下がった。さらにこれらの原料自体が強力に香るものだったため少量しか使用することができなかったという事実をつけ加えれば、これらがいかに香水の民主化への最初の道を開いたかが容易に理解できるというものだろう。このようにして十九世紀のおける人工香料の合成はこの業界に驚異的な飛躍をもたらした。特筆すべきは新たな消費者層を開拓したことだ。調香師セプティマス・ピースは1903年に次のように記している。「化学製品の恩恵を受け香水業者も石けん業者もごく安価な商品を作ることができるようになったことで、新たな顧客層がすぐさま彼らの製品に飛びついた。[...] 低価格で購入できるようになったため、今ではごく質素で慎ましい職人でさえ香りつきの石けんを使っている。オーデコロン、アロマビネガー、オードトワレ、ハンカチ用エキスの使用もだいぶ一般的なものとなった。こうした商品の生産量が増加したことは人工成分の採用によるところが大きかった。人工成分は控えめな価格で、香水業者に大きな力を与えてくれた」。とはいえこうした経済的側面にばかり目を向けていては、これらの新素材が嗅覚にもたらした多大なる貢献と新たに開かれた創造的可能性を見えにくくしてしまうだろう。自らも化学者であるとともに、ルール社およびベルトラン・フィス・エ・ジュスティン・デュポン社を経営するジュスティン・デュポンもそれを認めている。自然界の植物や動物から得られる天然の原材料は依然としてあらゆる調合の基礎をなしていたわけだが、可能な組み合わせの数は限られていた。「そのため化学の発見がちょうどいいタイミングで助けにやって来ることがなければ、香水業者たちは新しものを作り出すことが不可能な状態に陥り、早々行き詰まっていたことでしょう」、そうデュポンは結論する。1921年にシャネル「No.5」を作ったエルネスト・ボーにとって、合成由来の香料はまったく新しい香りの可能性をもたらすものであったたとともに、香水そのものをモダンな時代へと導くものであった。「1898年、調香師の技術は主として限られた数の素材を準備し混合することにあった。[...] バニリン、ヘリオトロピン、クマリン、バウアー・ムスクが工業的に作られるようになるまでは......。それまではどのようなフォーミュラもごくシンプルなものだった。今日の調香師たちにとっては素朴で物足りないものとして映るかもしれない」。
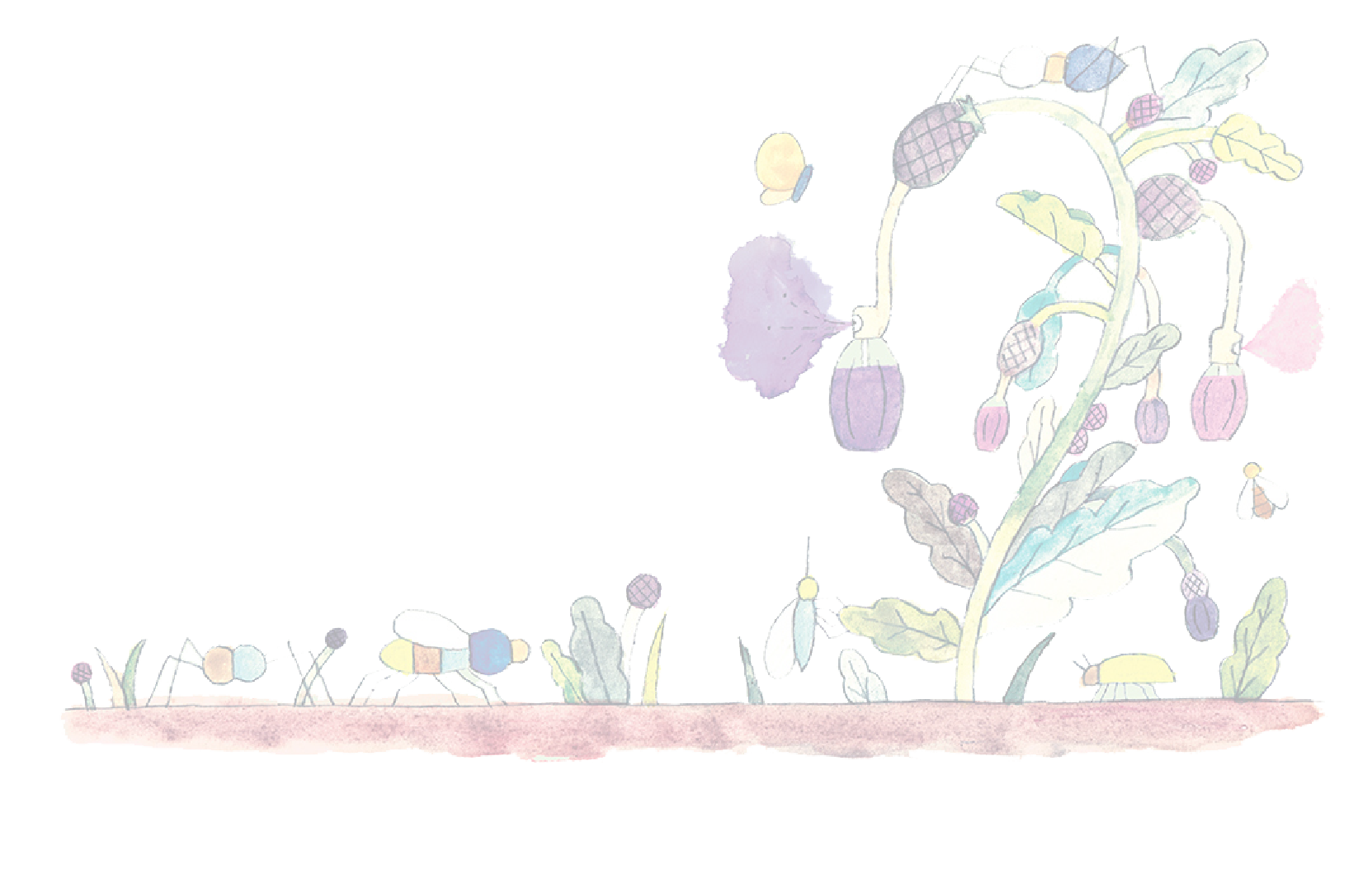
天然製品が取引きされるのを合成香料が邪魔だてしているのではないか? そう非難されると香水業者たちは、両者を組み合わせること
が重要なのだということを思い出させようとした。
思わぬ落とし穴、予期せぬ偏見
ところが人工香料にはその初期から早くも否定的な偏見がつきまとうことになった。最もよくあったのは、これらの物質が危険なものだと判断されたことである。こうした考えの一部はニトロベンゼンに起こった不幸な前例に端を発していた。最初に合成された匂い分子のひとつであったニトロベンゼンは苦いアーモンドのような匂いから石けんの製造に利用されていた。1851年の万国博覧会にもそのサンプルが多く展示されたほどであったが、しかしこのニトロベンゼンに毒性があることが1865年、調香師セプティマス・ピースによって指摘されたのだった。そこで明かされた事実が、人工香料に対しもとからつきまとっていた否定的なイメージ、すなわち化学というもの全般に対し抱かれる非合理的な恐怖にさらに拍車をかけることになってしまったのだった。「そうだ、これは犯罪に加担する妖精なのだ![...] この魔女の手によって信じられぬほどの財産が魔法のごとく築きあげられるわけだが......その影では最悪の厄災が生じているのだ」、1909年出版『香りの植物』と題された書物の序文にピースはそう記している。このような公衆衛生をめぐる論点に加え、これらは本当に良い香りなのだろうか? という疑惑も生じた。そうした不信はおそらく、いくつかの人工香料がその初期においては質が低かったということに起因する。特に果物のエッセンスに関しては。アロマそのものとしても香料としても使用されたそれらのエッセンスは、洋梨、林檎、パイナップル、マルメロ、苺といった果実を模すために合成された「エーテル」であった。それらの香りとしての質が議論の的となったわけだ。ここでもセプティマス・ピースが証言する。「化学分析によりいくつかの天然香料のなかにエーテル化合物が発見され、合成によってそれらを再生産できるようになってからというもの、産業的な成果はすぐに現れた。数々の不快な要素を組み合わせることによって、少なくとも不快ではない匂いを持ったエーテル化合物を工業的に製造することが可能になったのだ。それらはそのアロマによっていくつかの果実や花の香りに似せられた」。合成原料の特許が切れ公共のものとなるとともに価格の下落が起こる。その結果より広い消費者層向けの商品が作られるようになると、今度は富裕層の消費者たちがこれらの商品が低品質なものなのではないかと批判し始めたのであった。科学評論家ジュリアン・テュルガンによれば、この点については「たった一滴で、[...] 何リットルもの香水に香りを与えることができる」ムスクに最も非難が集中したという。一方でまた別の予期せぬ要因が合成製品の上に重くのしかかってきた。これらの新製品が「ドイツの粗悪品」であるとして、外国嫌悪と結びつけられてしまったのである。こうした考えは当然、匂い分子の合成においてドイツのなした成果が重きを占めていたことに由来していた。さら
には1870年の紛争、ついで第一次大戦と、物質的にも人的にもフランスの化学が大きく損害を被らされたいう文脈も加わり、こうした評判はなおさら払拭しがたいものとなったのであった。香水業者たちは消費者たちに対し別の論点をアピールすることでこうしたトラップから逃れようとした。天然製品が取引きされるのを合成香料が邪魔だてしているのではないか、そう非難されると香水業者たちは、両者を組み合わせることが重要なのだということを思い出させようとした。またこのような合成原料こそが香水製品を広く普及させる民主化に寄与したことを強調しつつ、市場が拡大することで天然製品の需要も高まるだろうと主張した。そして品質そのもの以外にも、合成香料は天然原料の消費をうながすような、そのような流行を生み出す可能性をも秘めていると指摘した。事実、1910年代以降ジャスミンの花から抽出される成分の需要が増加したことをジュスティン・デュポンは報告している。これは市場全体の成長をはるかに上回る増加であった。デュポンはその需要増加の原因が、同時期に流行したスズランとリラの香水にあると見ていた。それらが天然原料であるジャスミンの香りにヒドロキシシトロネラールを組み合わせて作られるものだからである。「化学者たちの発見によって、グラースで培われてきた花の文化に変化がもたらされたのです」、そうデュポンは述べる。最後は、美に関する論点だ。すなわち人工成分は、天然原料といっしょに使われたときのみその香りを十全に発揮できるのである。そしてそれらをいかにして巧みに組み合わせることができるかが香水業者および調香師たちの腕の見せどころなのである。
ムース・ド・サックス、リラVII、メリロティス
芸術家としての調香師のイメージが登場し始めたことは、合成成分による革命がもたらした主要な帰結のひとつであった。合成成分は強い特徴を持ち、その力を制御するのが難しいため、調合には高度な専門性が求められたからだ。それらの使用を容易にする目的から、原料のサプライヤーたちは製造した合成分子に対し、その特徴を引き立てつつ調合を容易にする化合物を組みこみ、それを「ベース」としてカタログに加え始めた。例えばド・レール社によるベース、アンブル83はバニリンを引き立たせていた。キャロンの「ニュイ・ド・ノエル」やモリナールの「ハバニタ」の香りを特徴づけているムース・ド・サックスは、イソブチルキノリン引き立たせるベースであった。1895年設立のジボダンはフィルミニッヒ社とともにジュネーブ地域における合成分子製造を主導してきたパイオニアであるが、そのジボダンのマリウス・ルブールは1905年よりベースを調合し始め、ジャサント・エクストレ(1906年)、そしてゲランの「ミツコ」(1919年発売)やランバンの「アルページュ」(1927年発売)にも使用されたリラVII(1911年~1912年)、ミュゲ16やメリロティス(ともに1916年)といったベースを開発した。これらは香水の主成分となるほどのもので、例えばサリチル酸塩、クマリン、オイゲノールを中心に構成されたメリロティスは、ジャン・パトゥより1929年にリリースされたアンリ・アルメラス作「モマン・シュプレーム」の実に3分の1を占めていた。新しい分子の価値を引き立たせるためのベースがこれらの企業によって開発されるなかで、調合の技術もまた発達した。そしてそれは彼らの強みのひとつとなった。彼らはただ原料を製造するだけに飽き足らずじょじょにその活動を広げ、ついには香水作りにまでその幅を広げるようになったのだ。そして今日の香水業界の大枠を支えることになる、調合会社というモデルを確立したのである(エレオノール・ド・ボヌヴァルによる記事を参照のこと)。新たな消費者層へと市場が解放され、創造的革命とともに芸術家としての調香師のイメージが立ち現れ、そして調合会社というモデルの誕生が準備された。これらは生産の機械化が進む状況下で、合成香料の発見が香水業界の基礎を作り、近代化へと導いたなかで起こったことである。
第一次大戦後になるとクリエイターとしてのオーラに包まれたデザイナーたちが大挙として市場に参入し始め、かくして現在の香水業界は誕生へといたったのである。