体臭というものが話題に挙げられるとき、まず思いつくのは汗であろう。この汗という分泌物は主として水と塩分、ナトリウムやカリウムといったミネラルで構成されているわけだが、実は基本的には無臭なのである。エクリン汗腺から分泌される汗は気温の上昇や運動によって高くなりすぎた体温を調整するためのもので、汗に含まれる酸性が細菌の繁殖を抑制し、それによって悪臭が発生するのを防ぐ。汗が悪臭を放つときがあるとすれば、主たる要因として考えられるのはその汗がアポクリン汗腺から分泌されているからなのだ。アポクリン汗腺から分泌される汗は粘性が強く、白く濁ったアルカリ性で、脂肪分が高い。先ほどの汗とは異なり、こちらには皮膚中の細菌が繁殖する格好の条件が整っている。しかしこの汗が分泌されるのはストレスを感じたときなど、特定の条件下に限られる。
体臭がするということは不衛生のしるしであると見なされがちだが、匂いこそが体の情報を伝達する確かな手段のひとつなのである。また、体臭はさざまなタイプの社会的情報も発信している。例えば人は年老いていくにつれ化学的組成が変化し、あらゆる文化で認知されている高齢者特有の匂いを生じさせる。日本語にはこの匂いを指す固有の語まで存在していて、これを「カレイシュー」という。「他の動物と同じように、人間もまた体臭の出すさまざまなサインを読み取ることができます。それらのサインによって、その匂いを発する者の生物学的年齢を識別し、病気の人を避け、適切なパートナーを選別し、自分の両親かそうでないかを区別することができるのです」、そう説明するのはフィラデルフィアのモネル化学感覚研究センターで研究活動に従事する、神経科学者のヨハン・ルンドストロームだ。
人体は「揮発性有機化合物(COV:ComposésOrganiquesVolatils)」という名で知られる、気化性のある無数の分子を生成している。そしてその多くは匂いを持つものである。これらは汗、呼吸、皮膚、尿、便、さらには膣分泌液からも放出される。「人体からは何百ものCOVが発散されているわけですが、それらはその個体の代謝の状態がどのようなものなのかを反映しています。つまり感染症や代謝疾患にかかっていると体臭が変化することが多い」、東京大学応用生命化学専攻教授、東原和成はそう解説する。事実臨床においても、特定の病状がこれらの揮発成分の匂いを変え得ることが認められ、したがって各病状に固有の匂いがひとつのバイオマーカー、生物学的指標として活用できるのではないかと注目されている。
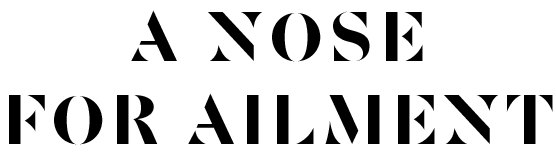
By Eléonore de Bonneval and Hirac Gurden

体臭が明かす秘密:病気を嗅ぎ分ける最新医学
エレオノール・ド・ボヌヴァル、イラック・グールデン
吐息、排泄物、汗、あるいはその他の分泌物。私たちの体から発せられる匂いは情報の宝庫である。その匂いによって、体の代謝や健康がどのような状態にあるかを知ることができるのである。そしてそのことは研究を進めるための重要な手がかりとなる。
悪い空気
古くは中世から、吐き気を催させるような匂いがあるところには必ず病的な何かがあると考えられてきた。当時は瘴気(ミアズマ)こそが病の原因であるとされた理論があったように、コレラやペスト、さらにマラリアなどといった疫病は「悪い空気」、すなわち汚染され毒に感染した大気によって広がるものだと信じられていた。十四世紀における「くちばしドクター」という呼び名は、診療にあたる医師たちがペストから身を守るために鳥の頭の形をした奇妙なマスクをかぶったことに由来する。そのマスクのなかにドライフラワーやハーブやスパイスを入れ、主要な感染源とされていたその悪臭から自らを遠ざけようとしたのだった。しかしそのような考えかたが誤ったものであると理解されるには、微生物が発見される十九世紀を待たなければならなかった。
より信用に足るアプローチを提示したのは十七世紀のイギリス人医師、トーマス・ウィリスであった。ウィリスは患者の尿を味見し、診断を下したのだった。つまりこのときから尿検査は単に目で見て検査されるものであることをやめ、複数の感覚に従って行われるべきものとなったのである。患者の尿に甘い味がするとき、そして糖代謝に問題があるときに生成されるケトン体に特有の、リンゴのような匂いがするとき、それはその患者が糖尿病であると診断するための有効な判断材料となった。
多くの病気にはそれぞれに特有の変わった匂いがある。なぜそのような匂いが生まれるのかというと、まず考えられるのは、体内で代謝不全が起こっているからだ。例えばトリメチルアミン尿症(英語圏では「フィッシュ・オーダー・シンドローム」という呼称で知られている)は体内でのアミノ酸の代謝異常から引き起こされるものであるが、その主な特徴は患者の体から魚のような匂いがすることである。また肝不全の患者からは腐った卵のような匂いがする。通常は肝細胞によって代謝される硫黄化合物が代謝されず、呼吸器内に残存してしまうためである。 とはいえ病いに関係するすべての匂いが不快なものとは限らない。ロイシノーシス(「メープルシロップ尿症」とも呼ばれる)は分岐鎖アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の代謝不全を病因として起こるものであるが、患者の尿、汗、耳垢からは甘くキャラメルのような匂いが確認される。2011年に発表した研究のなかで、そうした特徴的な匂いを持った病気のリストを提示してみせた東原和成教授もこれを認めている。またそのなかで教授は、コレラ患者の便からはジメチルジスルフィドとテルピネオールの影響を受けて甘ったるい匂いがすることも指摘している。
他の哺乳類と同様に、人間もまた嗅覚の働きによって見知らぬ人のなかから病気の人を見分け、接触を避けることができる。
がん細胞、その早期発見のためには
他の哺乳類と同様に、人間もまた特定の匂いをかぎ分けることによって見知らぬ人々のなかから病気の人を見分け、彼らとの接触を避けることで偶発的に感染してしまう可能性を排除しようとすることが、ストックホルム・カロリンスカ研究所のマッツ・J・オルセン博士らのチームによって明らかにされた。したがってこうした匂いは、病気の早期発見を目指すにあたってはかなり有効な手がかりと言えるだろう。モネル研究センター所属、有機化学を専門とするジョージ・プレッティ博士もこの点についてははっきりと同意している。「まさに鉱脈と言ってよいでしょう。がんを始め、遺伝性疾患、ウィルスや細菌による感染症などさまざまな病気に関連するCOVからは、実に豊富な情報を引き出すことができます」。
またモネル研究センターは他の研究機関との共同研究によって、人体の皮膚細胞から発される匂いがメラノーマ(悪性黒色腫)を検知するための指標として役立てられることを明らかにした。なおこのメラノーマ自体、固有の匂いを特徴として持つ疾患であることが以前から知られている。そしてがんの場合、この特有の匂いとは、がん細胞それ自体から発される匂い、すなわち健康な人体には検知されない(膀胱がん患者や前立腺がん患者から検出されるホルムアルデヒドなどの)揮発性代謝物の匂いと、さらにはそのがん細胞に抵抗して戦う免疫系を始めとした健康な細胞によって生成される匂い分子の、このふたつの要素が混ざり合った匂いということになる。 メラノーマとは、メラノサイト、すなわち皮膚の色素を生成する細胞組織に影響を与える腫瘍である。皮膚がんによる死亡原因の実に75%をこのメラノーマが占め、これを早期発見できるかが患者の生存率に直接関わってくる。これまで採用されてきたメソッドは皮膚を視覚的に検査し分析するものだったため、その方法が有効性であるかどうかはただひとえに、患者自身の自覚症状にもとづく自己診断と臨床医たちの能力にかかっていた。そこへ研究者たちが、メラノーマ細胞がそのサインとして特有の匂いを発生させることを突き止めるとともに、ナノテクノロジーを搭載したセンサーを用いることによってそのメラノーマ細胞と健康な細胞とをじゅうぶんな信頼性をもって区別できるということを示してみせたのだった。
機器を小型化し持ち運び可能にする製造技術と相まって、今日における電子技術の刷新は非侵襲、すなわち外科的措置をともなわない迅速な診断を行うための検出器を作ることを可能にした。イスラエル工科大学、通称テクニオン(「中東のMIT」とも呼び習わされる研究機関である)のホッサム・ハイク教授が2006年より開発を進めている「ナノーズ(Na-Nose)」はまさにそのような機器で、教授はこの「ナノ人工鼻」の運用により患者の呼気を分析し、卵巣がん、結核、肺高血圧症、さらにはパーキンソン病やアツルハイマー病など、最低23種の病気を早期に発見することを目指す。この方法が奏功すれば、病気が目に見える形で発症する15年前に発見することできるだろうと見積もられている。
人工の鼻「ナノーズ」開発の目的とは、卵巣がんや結核を含む23の病理の早期発見である。
牧羊犬か、マンモグラフィーか
他にも、動物の持つ嗅覚の鋭さに着目した、より費用のかからない方法も研究されている。例えば、犬には人間の約60倍にあたる3億個もの嗅覚受容体が備わっている。そのため訓練された犬ならば、さまざまな病気を高精度かつ非侵襲的に、しかも再現性高く検知できるのである。1989年から犬は世界中の研究施設に導入されている。英国・アマシャム病院のキャロライン・ウィリス医師率いる研究チームが明らかにしたところによると、前立腺がんに特有の臭気、例えばアルカンなどの飽和炭化水素を検知するにあたって、犬の嗅覚は確かな有効性を示したということである。この研究の最中、ある一匹の犬が患者のひとりから前立腺がんの匂いがする旨をしきりに訴えた。検査の結果その患者から前立腺がんに関わるいかなる兆候も確認されなかったが、しかしさらに詳しく検査をしてみると、その患者から腎臓がんが発見されたのだった。 2017年、看護師で科学の博士号を持つイザベル・フロマンタン主導のもと、キュリー研究所は乳がん早期発見プログラム「Kドッグ(Kdog)」を始動した。このプロジェクトは訓練を受けた2匹のマリノア犬が、女性が一晩胸に当てていたタオルの匂いから感染細胞を探り当てるというもので、初期の結果が良好だったゆえ、この方法がマンモグラフィーに代わる主要な検知手段として運用できるのではないかと期待する声が高まっている。
そして東アフリカのNGO、アポポが運用するのはサバンナハムスターである(別称ガンビアクマネズミ)。訓練を受けたネズミたちは痰のなかから結核の匂いを探り当てる。ネズミたちが反応を示したサンプルは補足試験に回され、その結果から病気の有無が判断される。同NGOによれば、この方法が導入された診療所では検知された件数が平均で42%増加したという。 むろんこれらのプログラムが即座に特効薬となるわけではない。研究はなお続けられているが、さまざまな困難もついて回っている。当然だが、すべての病院に犬を配置することは現実的ではないし、犬たちに特別な訓練とトレーナーが必要であることを考えればなおさらである。しかしこのような匂いの医学の研究は、今も世界中の研究者によって熱心に取り組まれ続けている。
「嗅覚が異常をきたすとき」
他の感覚能力と同様に、嗅覚もまた年齢とともに衰えるものであることは知られている。しかし加齢だけが嗅覚に変調を生じさせているわけではなく、さまざまなタイプの病理が原因となっていることもあるのである。「カコスミア(悪臭症)」はある種の悪臭を感じることを指すが、客観的なものと主観的なものがある。「患者は自分が良い匂いをしていないと感じるものです」と、パリ・ラリボワジエール病院耳鼻咽喉科のコリーヌ・エロワ医師は語る。
このように言われるとき、可能性があるのは消化器系の問題や感染性の歯の病巣が症例となるケースだろう。この場合、客観的カコスミアと言う。一方で主観的カコスミアの場合、患者が感じている悪臭は、他の人にはそうと認識されていない。そのようになった場合は「憂慮すべきでしょう。一般的には心理的トラブルに陥っている際見られる兆候です」とエロワ医師は語る。「パロスミア(嗅覚錯誤)」とは匂いの感じかたが変わることである。この症状を患っている者は鼻先に出された物の匂いを感じることができず、そのため自分が嗅覚を完全に失った(つまり「アスノミア」に陥った)、と考えるということがよくある。しかし実際には、これは嗅覚の喪失ではなく混乱なのである。 嗅神経細胞は生涯を通じて再生され続ける。嗅神経細胞は匂いを検知し、その匂いに対応するメッセージを脳内に位置する嗅球へ向けて伝達する。再生された各神経細胞がこの目的のために嗅球のなかの正確な位置に向けて繊維を送り出す。嗅球には特定の分子の認識に特化した異なるそれぞれのゾーンがあるため、送り出すメッセージに応じてその位置も異なるのだ。これらの繊維でできたケーブル上を電気信号化されたメッセージが走り、このメッセージの通行によって、鼻によって検知された分子Aと、嗅球によって受容された分子Aとの認識上の一致が可能となるのである。しかしここで大きな役割を担う神経細胞が損傷を受けた場合、その再生に際して問題が生じることがある。つまり新しく作られた神経ケーブルが嗅球内における別の匂い(分子Bとしよう)に特化したゾーンに到達してしまうと、鼻によって検知された匂い(分子A)と嗅球内で認識された匂い(分子B)とのあいだに一致が起こらなくなり、その結果誤った嗅覚的イメージが作り出されてしまうのである。
「神経変性疾患(アルツハイマー、パーキンソン病など)」もまた嗅覚の変調をともなう場合がある。ペンシルバニア大学嗅覚味覚研究センター所長、リチャード・ドッツィ教授らのチームが1980年代末に明らかにしたところによると、アルツハイマー病患者に対し匂いの感知能力と識別能力の低下が見られた。こうした「ハイポスミア(嗅覚減退)」はパーキンソン病に特有の症状でもある。実際、嗅覚に関わる症状は多くの神経変性疾患に見られるが、しかしコリーヌ・エロワ医師によれば、「患者の嗅覚を測定することはあまり努めて行われておりません」ということだ。確かに測定を実行するのはそう簡単なことではない。脳の中心的機能はゆっくりと変わっていくものなので、そのため患者が自らの症状を正確に説明することも困難なものとなるためだ。例えば「ステーキを食べていてその味が以前と同じではないと感じたとしたら、それは神経変性疾患のせいかもしれませんが、しかし本当のところはただそのステーキの味の質が自分が昔食べていたものより劣っているというだけの話だった、という可能性も同じくらいあるのです」。しかし今や研究の進歩とともに耳鼻咽喉科と神経科は部門の垣根を超えてより頻繁に共同するようになり、その結果今日では、問題となっているのが匂いの検出(したがって鼻の機能の問題)なのか、それとも匂いの認識と識別(すなわち脳の活動の問題)なのかを明確に判断することが可能となった。「精神疾患」においても匂いの認識への影響が見られることがある。統合失調症患者の嗅覚システムが萎縮していることが確認され、これが匂いを感じ取る能力の低下と相関関係があると見られている。またうつ病患者にも嗅覚能力の退行が見られる。反対に嗅覚障害にかかった患者にはうつ病の諸症状が見られ、その重篤度は嗅覚喪失の度合いに相関するという。
この嗅覚の喪失という現象をひとつの生物学的指標として適用するとき、より広範囲にわたることが予測可能となると解釈することは依然として困難であるように思える。現在の耳鼻咽喉科の施設には患者の嗅覚を測定するための適切なツールに乏しく、また嗅覚の変質を追うために必要となる臨床的知識も決してじゅうぶんとは言えない。くわえて試験に再現性を求めることは困難で、嗅覚の強度と感度の閾値を求める測定も複雑ときている。しかしそれでもなお、病いを予防的に検知するためのツールとしてこの嗅覚測定を行うことは、多くの病気に対する有効な研究手段としての可能性を秘めていると考えられている。







