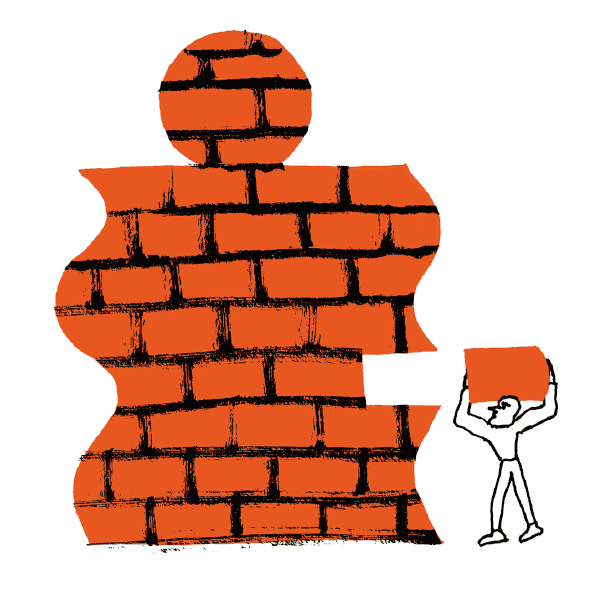『芸術の言語、象徴理論へのアプローチ』(1990年刊)は1968年にアメリカで出版された著書のフランス語版であるが、そのなかでアメリカの哲学者ネルソン・グッドマンは芸術を、固有の機能を備えたひとつの記号として論じている。グッドマンは唯一無二の作品を創造する「オートグラフィック・アート」(絵画、彫刻)と、複数の作品を創作するのに適する一方で特殊な記述法がその発生を条件づけている「アログラフィック・アート」(音楽、劇作品)とを区別する。グッドマンは次のように説明する。「絵画と音楽のちがいで注目すべきなのは、作曲家は楽譜を書いた時点でその仕事を終えるということだ。たとえその演奏が彼の仕事における最終的な成果となるとしても。一方、画家は最後まで絵を完成させなければならない。両者において何度習作や手直しが試みられたかはさして問題ではなく、この場合、絵画は段階ひとつの芸術であり、音楽は段階ふたつの芸術であるということだ」。音楽の曲と同様、香水もまた唯一無二の創作物とは言えず、また再生産不可能なものでもない。いやむしろ再生産されることを運命づけられている。それゆえ香水は段階ふたつのアログラフィック・アート、という規則に従うことになる。
フォーミュラの芸術
「アログラフィック « allographique »」という語はギリシャ語由来である。接頭辞 « allo »(「他の」の意である« allos »から)と動詞 « graphein »(「書く」の意)の語幹から構成された語。したがって絵画や彫刻などと関連し、芸術家が例外なく直接手を下し、たったひとつのサンプルだけを提出する「オートグラフィック」とは対立する意味である。アログラフィック・アートにおいては作品の実現は書かれたドキュメントを媒介にして起こる。ドキュメントそれ自体は作品ではなく、作品のアイデンティティはその記述を厳密に複製するということを条件に保証されるのである。
グッドマンによれば、記述されたものから派生したサンプルは正確なサンプルとして認知されることになる。音楽においては、その記述されたものは楽譜にあたる。舞台においては脚本。建築においては図面。そして香水においては、「フォーミュラ(成分表示、処方)」がそれにあたるというわけだ。もちろんそうだ。香水はフォーミュラから生まれる。すなわち調香師の意志(精神的企図)とその具現化のあいだを取り持つドキュメント。フォーミュラは薬剤師と調香師の関係が近いということにも注意を向けさせる。まさに香水の構成要素を網羅したリストである。楽譜と同じくひとつの指示書であるが、それそのものには実行方法に関する指示は記されていない。フォーミュラには構成物質の名前しか言及されておらず、せいぜいのところその物質が自然由来の場合はその形質(アブソリュートであるかエキスであるか)、原産(例えばベチバーであればハイチ産であるかジャワ産であるか)、配合比率といったものが付随するくらいだ。
元来、香りのレシピには必要な材料にくわえて、配合前の準備、どのように作るかといったことまで示されていた。その一例となるのが、17世紀の有名なパリの調香師シモン・バルブの残したレシピであるが、その詳細は同業者向けに書かれた概論書『王室の調香師』(1699年刊)のなかに記されている。「沸騰する」「浸漬する」といった指示がそこには数多く見出される。また調香師自身による蒸留を行うための指示も与えられている。例えば、「オー・ド・ジェロフル」(現代フランス語で「ジロフル」、クローブの意味)、別名「オー・ドゥイエ」(カーネーション水)の指示は次の通りだ:「クローブ4オンスを乳鉢で砕き、4パイントの温水に3~4時間、蒸留器の冷却器で浸漬させる。次に炉に置き、冷却器に新鮮な水を供給する。そこから出てくる水は、クローブよりもカーネーションに似た甘い香りがする。これがカーネーション水の作り方だ。カーネーション自体は良質な香料を生み出せないために、これはその代替香料となる。」。
香水専門のフランスの歴史家ウジェニー・ブリオによれば、、「19世紀末、調香師がアルコール混合物に直接混ぜる原料を入手できるようになった時、レシピは公式になった」。そのため、材料が使用可能な状態で来るので、植物から油を抽出する方法を調香師に伝える必要がなくなったのだ。
アイデンティティと記述
レシピの正確さが空白を埋め、公式化されればされるほど、実行段階における解釈の余地は少なくなる。したがってそこに記述されていることが香りのアイデンティティを全面的に決定づけることになる。つまり理論上は、原料を何かに置き換えたり(それが毒物であったり環境的制約上やむをえない場合)、鼻で香りをコピーするなどしてフォーミュラから逸脱してしまった場合、まったく別の対象物が作り出されるということになるだろう。ここでまず引き合いに出される議論は、テセウスの船のパラドクスであろう。すなわち少しずつすべての部品を交換した船は大まかな形は維持されていてもなお同じ船のままであると言えるのか、ということだ。ここでグッドマン主義の純粋主義者は、表記の厳密な実行ではなく、全体として捉えられた形式に焦点を当てるゲシュタルト理論家と対立する。これは20世紀最高の調香師とも呼ばれるかのエドモン・ルドニツカが1974年にオディル・モレノとルネ・ブルドンと共著した『L’Intimité du parfum(香水の親密さ)』において擁護した考えかたでもある。「フォーミュラを漏らすわけにはいかない。だがそもそもフォーミュラが簡潔な言葉で明記されていたところでそれがご婦人がたにとって何の役にたつというのだろう?仮に私が香りの構成要素をすべて開示したとしても、その形については何ひとつ描写したことにはならないだろう。これこれのソナタがドレミファソラシで構成されていると述べることがそのソナタを描写することにはならないように。 [...] 重要なのはこうした構成要素のすべてがどう配列されているかなのだ」。制作上の規則(フォーミュラに対しいかに正確であるか)ではなく、作品を需要するうえでの認知的感情的メカニズムを含む、最終的な結果のほうにこそ特権を与える、そんな受容の美学に向けて舵を切ることとしよう。この考えかたの特徴は、感知される形には変わることのないひとつの本質があると認めている点にある。たとえテンポが変えられ音程がはずされていたとしても、電話を保留されたときに聞かされるあの『四季』を誰もが認識できるように。
秘密の体制
ひとつの香水を再現するにはふたつの選択肢がある。ひとつはフォーミュラから再生産すること(これにより正確な香りの入手が可能となる)。ふたつ目は、つまりフォーミュラがない場合だが、嗅ぎ取れたものから再生産することである(したがってここでは推測で再現することになる)。香りを保護するという観点から見た場合、この第二の選択肢をはばむことは難しいため、香水業界はコピーを容易にしないことを優先し、フォーミュラを秘密にする体制を選択することになる。
香水は長い間、同じ植物学的起源を持つため薬剤師の薬と関連付けられていた。しかし十九世紀初頭にその区分が明確になった。フランスの人類学者で香水史の専門家アニック・ル・ゲレールは2005年の著書『香水:起源から現代まで』で、「1810年8月18日、帝国の布告により調香と薬学の分離が正式化された」と述べている。消費者を詐欺師たちから守るためにナポレオンは薬剤師に処方を公開するよう命じたが、調香師にその義務はなかった。以来、フォーミュラが秘匿された香水はその治癒力を大っぴらに宣伝することはできなくなった(それを飲むようすすめることも)。そのように香水が治療として使われた時代から、装飾品としての化粧品の時代へと移っていく。フォーミュラの所有権は依然として調香師が独占していたが、今日においては産業規模がより巨大になったためこのモデルは変化することになった。ブランドが自社で引き抜いた調香師を抱える稀なケースをのぞき(特にシャネル、カルティエ、エルメスがその例だ)、ブランドは香料メーカー(ジボダン、IFF、フェルメニッヒなど)に雇用された社内調香師たちに依頼し香りを制作するのが常である。フォーミュラがこれらのブランドに渡ることは決してない。フォーミュラは香料メーカーの手に残ったまま、香料メーカーが各ブランドに対し香りの濃縮液を売る。そしてブランドがその濃縮液をアルコールで希釈しボトルに詰めるのだ。在庫が尽きるとブランドは香料メーカーに、必要量の濃縮液を再度注文する。調香師が会社を辞め他社に移ったとしても、濃縮液の生産を続けるのは元の会社のほうだ。したがってある意味では調香師は自身のフォーミュラの権利を雇用された会社に譲渡していると言える。しかしながら1980年代に入るとガスクロマトグラフィー技術により分析機器が改良されたことにともない、さらには熟練の調香師たちの後押しも手伝って、香りの組成を事後的に解明することが容易となり、したがって模倣も容易となった。この場合、香りというものが著作権で保護されていない以上、ここで検討されるのは商法(ビジネスで遵守すべき法律)ということになる。

模造品問題
香水業界には、実にバリエーション豊かな模造品が存在している。市場では、消費者はそれが模造品であることを承知のうえでパッケージングされていない商品を買っているケースもあれば、さらにはまったくちがう名前、ちがうブランド名で流通している極めて巧妙な模造品もある。それらに関しては著作権が問題とならないため不正競争、くわえてブランドタダ乗りの原理に基づき商法が吟味される。管轄となるのは商事裁判所だ。
有名なのはティエリー・ミュグレ対モリナール事件であろう。パリ商事裁判所は「エンジェル」の独自性を認めるとともに、モリナール社が「ニルマラ」(1955年に作られたが事後的に改良された)の販売を通して行なったのが確立されたブランドへの寄生と不正競争にあたるという判決をくだした。当時、このふたつの香りが合致しているかを判断するために選ばれた1000人の女性消費者の過半数が、このふたつの調合物の細部のちがいを判別することができなかった。オランダの心理学者で嗅覚研究の専門家エゴン・ピーター・ケスターが2002年のエッセイ「嗅覚に固有の特徴」で指摘しているように、嗅覚というものは複数の匂いが同じかどうか判断するよりもそれらの違いを識別するほうが容易なはずなので、このふたつの香りの差異が見出せないということは弁護側にとっては不利に働いた。偽造というものは一般的にその差異ではなく類似性に応じて評価されるものである。この事例においては両者の相違は感知されなかったため嗅覚上は両者が同質であると言え、したがって「ニルマラ」は「エンジェル」の複製品であると言える。判決内容を受け、モリナールはフォーミュラの変更を余儀なくされた。とはいえこの種の裁判はまだ非常に稀であり、裁判まで発展しないケースも多い。
同じ名前、異なる香り
フランスの日刊紙『ル・モンド』の2011年の記事(「ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー社は香りの製造を再度わがものとする」2011年5月27日号)においてジャーナリストのニコール・ヴュルセは、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー社が社内調香師を迎え入れたことにともなう調香の改良に乗じて、いくつかの主要な香水のフォーミュラの権利を元の権利者である香料メーカーが主張できないようにしてしまったことを早くも指摘していた。消費者を困惑させないよう香水の一般的な形態は保存されていたが、もはや元のフォーミュラに正確には適合していなかった。その証拠に、いくつかの捕えられた分子組成のなかにはそれを作った香料メーカーが独占的に使用するために確保していたはずの化合物が見られなかった。その化合物の存在によってこそ香料メーカーは正当な権利者として振る舞うことができるのだが。
しかしながら上記のケースにおいては法的手続きは取られなかった。商業において巨人への攻撃は自分の足もとを銃で撃つことに等しいからだ。長きにわたりフレグランス業界は法の正義よりも商業的利益を重視する「紳士協定」の原則に基づいてきたわけで、公けにするよりも妥協が好ましかった。
その結果、同じ名前を冠しているが組成の異なる香りが流通するといった事態が生じることとなった。香りというものが単なる匂いの物質ではないということがこれで証明されたことになるだろう。香りにはボトルもあるし、パッケージングもある。そして何よりも名前だ。その名前の永続性こそが作品としてのアイデンティティを保証し、その香りが受け入れられる状況を有利なものにする。その香りの固有性を決定するのは最終的には各素材の持つ(匂いとしての、記号としての、視覚効果としての)異質性であるということだ。