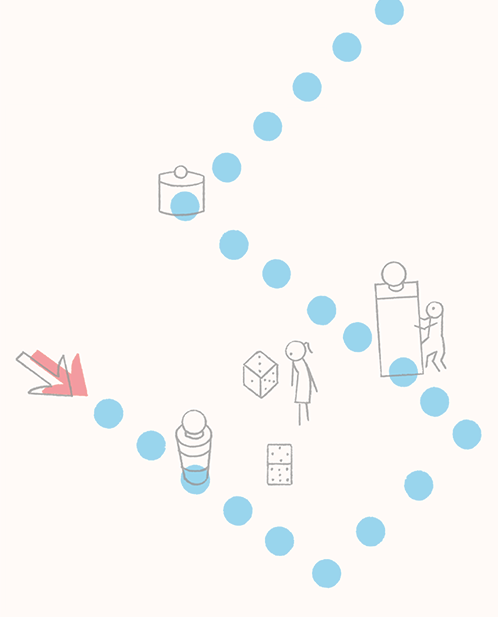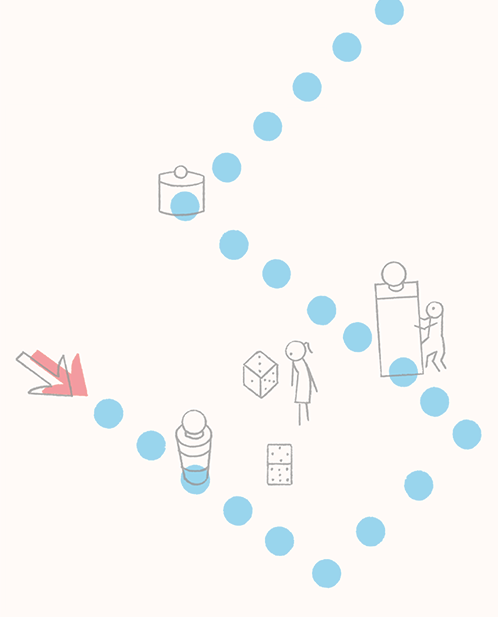ボードゲーム「世界一周レース」のなかでプレイヤーたちは五大陸すべてに旗を立てるべく奮闘するが、香水ブランド各社もまた世界で市場を獲得するために多くの課題を克服しなければならない。実際、国内市場だけでやっていくほうがもはや困難なのではないか。しかし輸出するとなればまたそれはそれで多くの障害がともなう。それぞれの国や地域で購買や流通に関わる特性が大きく異なるためだ。例えばドバイでは実店舗での購入が中心となるが、一方アメリカではネット通販が主となり、これについてはカリフォルニアでメゾン・デュケーヌ流通会社を設立したフランソワ・デュケーヌが「合衆国ではオンラインショッピングが目覚ましい成長をとげ、そのブームはまさに津波のように押し寄せたのでした」と例えたほどだ。またイタリアにはニッチブランドを扱う独立系の香水ショップが130近く存在するのに対し、フランスではわずか2、30ほどにとどまるといったそのようなちがいもある。そして中国に関してであるが、市場調査会社ユーロモニターの予測によれば、今後20年以内に世界最大の香水市場になるであろうと見こまれている。たとえ世界のグローバル化が進んでいるとはいえ、このように香水産業においては流通構造や消費者の嗜好によって、その実態は地域ごとに大きな偏差が見られるということが分かるだろう。
かつてフランソワ・デュケーヌはアメリカでランバンの経営に携わり、ついでプーチ・グループに買収される前のラルチザン・パフュームの経営にも参画した。現在は、オルファティヴ・ステュディオ、バオバブ・コレクション、クリス・コリンズ、アエデス・デ・ヴェヌスタス、といった複数のニッチブランドのアメリカでの流通を担っている。デュケーヌはeコマースの登場がゲームチェンジャーとなったことを強調しながら次のように述べる。「あるニッチブランドを取り扱うべきか思案するとき、例えばニーマン・マーカスのような高級百貨店はまずそのブランドがインスタグラムでどれだけのフォロワーがいるかを確認します。ブランドはソーシャルネットワーク上にコミュニティを持ち、eコマースサイトを持ち、さらにはサンプル提供も行い、そうして消費者たちと直接つながる手段を持っている必要があるわけです。その基準が満たされているのが確認されると、次は各地でトランクショー(展示販売会、受注会)を開催することが求められます。ブランドは各大都市に出向いていき、販売店でのプロモーション活動に追われるのです」。このモデルが音楽業界のそれとよく似ていることにデュケーヌは注意をうながす。アーティストはまずユーチューブで注目を集め、大手レコード会社の興味を引く。まさしくこうした流れから独立系ブランドのル・ラボは、設立された2006年から8年後にエステー・ローダー・グループに買収されたのであった。
アメリカ市場には独立系の香水ショップが少なく主流となっているのは百貨店であるため、規模の小さいブランドは独自の戦略を打ち立て創意工夫をこらす必要が出てくる。「流通業者はブランドから商品を仕入れる際に最終販売価格の5分の1を基準に買い入れます。しかしニッチブランドの生産コストは平均して一般ブランドの2倍におよぶため、この少ない利益幅がなおのこと重くのしかかってくるのです」とフランソワ・デュケーヌは指摘する。「彼らが取るべきモデルは、インターネット上のコミュニティを盛り上げ集客を図りつつ、店頭で実際に商品を体験してもらうこと、このふたつをうまく組み合わせることなのではないでしょうか。つまり彼らが資金をつぎこむべきはわれわれ流通に対してではなく、むしろ物流に対してなのです」。これはつまり、卸し業者に中間マージンを支払うよりも自社のウェブサイトを通じて商品を直接顧客に届けるシステムに投資するほうが理にかなっているのではないかということだ。
中東ではeコマースはあまり利用されず、ショッピングモールが主要な購買先となる。
各地域における特色と流通上の課題
ところでこれはあまり知られていないことだが、アメリカに次ぐ第2位の香水市場は(末尾に挙げたグラフにも示したように)意外にもブラジルなのである。統計データ会社のスタティスタ研究所の調査によれば、量だけで言えばアメリカをもしのぎ世界1位となる。これはブラジル人の習慣によるところが大きく、彼らは日に何度もシャワーを浴び、浴びた後は冷たい水で時間をかけて体をこする。北半球と同じく甘い香りも人気だ。現地にはボチカリオ・グループ、ヒノデ・グループ、そしてナチュラといった企業が君臨する。特にナチュラの力は大きく、エイボン、イソップ、ザ・ボディショップを傘下におさめ、訪問販売部門でトップを走るとともに、化粧品業界世界4位のシェアを誇るグループ会社である。「国際ブランド大手が束になってかかったとしても、ブラジル市場におけるシェアはわずか10%にすらおよびません」と、同国にパラレラ香水学校を創設したアレッサンドラ・トゥッチは証言する。「税金および登録手続き上の理由からブラジルの市場に参入するのはそう簡単なことではありません。そんななか例えばジョー・マローン(エステー・ローダー傘下)のようなブランドはよく健闘していて、旅行中にふらりと訪れ商品を手に取る買い物客たちをうまく取りこみ、緩やかですが着実な成長を見せています」。この南米の大国を攻略することは決して不可能ではないのであろうが、そのためにはゆっくりと時間をかけることをいとわない忍耐強さと、信頼できる現地パートナーが必須となるであろう。
ここで大西洋を渡り、ニッチフレグランスの聖地、イタリアに目を向けてみるとしよう。ロベルト・ドラゴはランカスターの香水部門を率いた後、妻のダニエラとともに(フラゴナール、ピエール・ギョーム・パリ、サンク・モンドといった)香水と化粧品を専門に取り扱う流通会社、カオンを設立した。なお彼は自身のブランド、ラボラトリオ・オルファティーボも持っているため、このふたつの業種に特有の課題や問題点はどちらもよく熟知しているのだ。「イタリアでは独立系香水ショップどうしが強固なネットワークを築いています。それがフランスとは異なる点でしょう。衣料品店など他の業種を含めれば約300の店舗がそのネットワークに参加しています。商業的利潤を追求するという本来の目的のかたわらに、香水の芸術性を追求する余地が、ここイタリアには残されているということです」。
ニッチフレグランスの見本市としてはミラノのエクセンスやフィレンツェのフラグランツェなどがあるが、そうした場はクリエイターたちにとって流通業者たちと出会うまたとない機会となる一方で、ときに失望や幻滅をともなうこともある。「最近の起業する若者たちは、商売をするには何ごとも手数料がつきものだということがまるで分かっちゃいないのです。倉庫から物を持ち出すには配送料を支払わなければならないのは当然のことです。5万ユーロでブランドを立ち上げるだけ立ち上げておいて、商品を再リリースしようとするころにはもうすでに予算を使い果たしてしまっている、なんてこともしょっちゅうです」とロベルト・ドラゴは語る。「ブランドの運営責任者が予算を決定する際にはまず『エクスワーク価格(工場渡し価格)』というものを理解しておく必要があります。つまり売り手であるサプライヤーが買い手であるブランドに製品を引き渡す時点での価格のことで、言い換えれば、そこから商品が流通経路に乗った後の諸々のマージンを含まない価格ということですね。この流通マージンは流通業者の得る利益のことで、しかしそこには輸送費、広報宣伝費、販売手数料、さらにシェンゲン協定圏外に輸出する際の別途税金、などといった原資も含まれるため、商品の流通を円滑に進めるためにはこの流通マージンを考慮することも非常に重要なものとなってくるのです」と、そう強調するのは自身もパリでコントワール・シュド・パシフィックというブランドを運営するヴァレリー・ピアネリだ。「そうしたすべての費用を計算したうえで最終販売価格を決定するわけですが、となるとニッチブランドでは200ユーロに達することもざらです。この価格は平均的な消費者にとってはほぼ高級品の域でしょう」。
ヴァレリー・ピアネリは1974年に設立された別のブランドを引き継いだ際、すでに確立された流通ネットワークの恩恵を存分に受けることができ、そこで国ごとの格差を実感したという。「イタリアはニッチブランドにとっては素晴らしい市場です。一方フランスでは市場が大手チェーンに集中し、その大手チェーンすらも競合他社との差別化をせまれているくらい競争が激しいため、ニッチブランドにとってはなおのこと困難な状況となっています。なので私たちのブランドはビューティ・サクセスに独占的に展開することで独自の住み分けを図るとともに、広い販売網を確保しているのです。ドイツ市場は中規模といったところでしょうか。化粧品チェーンのダグラスが支配的で、各百貨店にはニッチフレグランスのコーナーが設けられています。アメリカではユーロパフュームスというしっかりとした代理店が流通を担っており、安心と信頼を保証してくれます」。
ハロッズ、ハーヴェイ・ニコルズ、リバティ、セルフリッジズといった有名百貨店を擁するイギリスも、やはり香水の世界地図を描くうえでは重要な拠点となってくる。またヨーロッパにはバルト三国におけるクレーム・ドラ・クレームのように型にはまらない独特な小売業者も多く存在し、大陸でのニッチフレグランスの拡大に貢献している。
さらに東へ、中東へと視点を移してみよう。そこでは香水はまさに生活必需品である。「友人たちに配るからと一度に10本香水を買っていく買い物客も珍しくはありません。ドバイの食卓ではフランス人が飲みながらワインについて語るときのような、そんな気軽さで香水について議論が交わされます」、そう語るのはフィルメニッヒ・アラブ首長国連邦支社の調香師、ハミッド・メラティ=カシャーニだ。一方、「これは中東全域の習慣として言えることですが、人々が香りをつける際には体にはボディローション、お香を衣服に染みこませる『バフール』、そして首や手首にはオイルを塗るといったように、複数の香りが同時につけられるのが常です。さらには肌につける香水に関しても、いくつかの種類がレイヤリング(重ねづけ)されるのです」と、そう教えてくれたのはドバイに拠点を置くブランド、パルファン・ド・マルリーでグローバルブランドマネージャーを務めるコリーヌ・モンサラーだ。「女性用、男性用といった区別はありません。弊社から出ている『ダリナ』というフローラルな香りは男性からも好評です」。このブランドの由来はルイ15世の庭園から来ており、ヴェルサイユ宮殿からほど近いこの庭園に、ブランド名ともなっている「マルリーの馬」の彫像が作られたことで知られている。香水にはそれぞれ馬の名前がつけられているということもあり、競馬が好きなエミラティ(中東諸国におけるアラブ系の自国民)たちにもこの「パルファン・ド・マルリー」はたいそうお気に召している。同地域ではeコマースはあまり利用されず、ショッピングモールが主要な購買先となっている。伝統的な商業地区であるスークには(ディスカウント品や偽造品が横行する)ほぼ黒に近いグレーマーケットがひしめき合っているが、裕福な家庭は百貨店やニッチブランド専門店に足を運び、平均して年間で355ドル(355ユーロ)を香水に費やす。フィルメニッヒの調査によればこの数字はアメリカの85ドル、ヨーロッパの78ドルを大きく上回る。
「トラベル・リテイル、香水市場の新たなる可能性」
ロレアル・グループが「第6の大陸」と呼んでいるものがある。「トラベル・リテイル」、すなわち空港や免税店、あるいは航空機内やクルーズ船上といった場所で旅行客を対象とした小売販売経路のことである。それ自体がひとつの大きな市場であるとともに、近年の航空旅客数の増加によって大幅な拡大が見こまれている。ジェネレーション・リサーチ社によると、香水と美容製品を対象としたトラベル・リテイル市場は2018年だけで実に315億ドル(275億ユーロ)を計上し、しかもこの数字は前年比23.5%増だった。
エディション・ド・パルファン・フレデリック・マル(エステー・ローダー傘下)、ペンハリガン(プーチ・グループ)、ディプティック(マンザニータ・キャピタル傘下)などを始め、大手グループ企業に買収されたニッチブランドのいくつかが、この新たなる香水市場に参入し始めている。趣味や仕事で旅行をするミレニアル世代をターゲットに利益を上げることを目論む投資家たちにとって、この分野への進出はまさしく理にかなうものだった。「ですが、そんな風にどこででも手に入れられるのなら、それはもはやニッチフレグランスとは呼べないのではないでしょうか?あくまで私見ですが、インターネットもまたニッチ精神とは相容れないものだと思っています」とロベルト・ドラゴは疑義を呈する。ドラゴは流通会社カオン、そして自身のブランド、ラボラトリオ・オルファティーボの創業者である。
だがいずれにせよ、多くの独立系ブランドにとってはその市場に入りこむ余地はない。「空港のショッピングセンター運営者に支払うマージンが他よりかなり高いからです」とフランソワ・デュケーヌが補足する。デュケーヌは自身の会社、メゾン・デュケーヌにてアメリカにおけるニッチフレグランスの流通を担う。「毎年カンヌで開催されているサロン・タックスフリーは『トラベル・リテール』のための展示会とされていますが、アフリカやアジアといった、物流がまだ整っていない地域への流通サービスを模索する場としても重要なイベントです。香水市場はいまだ並行輸入など非公式な流通網によって成り立っているようなものですから」。むろん、それらは公式の統計上には現れてこないわけだが。
たった2分で12,000本の売り上げ
香水業界における新たなる革命の主導者として中国の名前が浮上している。「この市場を無視することのできるブランドはひとつとしてないでしょう」とマーケティング・コンサルタントのダオ・グエンは述べる。彼女が設立したコンサルティング会社、エッセンツィアはパリと上海に拠点を持つ。「これまで中国は香水市場と呼ぶにはほど遠い国でしたが、今や目を見張るスピードで変わりつつあります。香水をつけるという行為はかつてはスキンケアやメイクに付随する『ついで』や『おまけ』程度にしか考えられておりませんでしたが、今では自身のアイデンティティを示すものとして不可欠なものとなっています」。続けてダオ・グエンは、中国大陸には3億8,500万人ものミレニアル世代(18歳から35歳)がいることに注意をうながす。アメリカの5倍にあたるこの数字は、この層がこれからも伸び続けるであろう強力な購買力を秘めていることを示している。
流通経路に関しては実店舗と同じくeコマースも強い影響力を持つ。その筆頭はアリババだ。「決して避けては通れない、誰もが認める存在です」と、そうダオ・グエンもうなずく。「消費者たちは実際その商品がどんな香りがするかなどお構いなしにオンラインで購入します。モデル・女優のキム・カーダシアンの新作香水は中国の祝日である独身の日に(毎年その日にはネット上で大規模なセールが行われる)たった2分間で何と12,000本も買われました」。ユーロモニターによれば、中国は2040年までに世界のニッチフレグランス市場の半分を占める見こみである。そしてそのころまでには中国市場そのものが世界最大規模となっていることだろう。こうした予測の根拠としては、新規出店が加速度的に増加していること、若年層が消費へと参入しつつあること、香水の香りそれ自体ではなくブランドを重視して購入する傾向があること、などといった要因が挙げられる。「私どもも中国へは年に2、3店舗は新規出店しています」と、そう証言するのはクリストフ・セルヴァゼルだ。妻のシルヴィ・ガンテとともにアトリエ・コロンを創業した(なお2016年にロレアルの傘下に入っている)。「すでに中国が当ブランドの最大の市場となっております。中国の消費者たちはフランス製を好み、天然成分を好みます。またフランス的な革製トラベルケースやコフレといったものにも目がなく、そうした傾向がギフト用の購買を大いに促進しているのです。5人の子どもを持つ私ども夫婦の個人的なエピソードも気に入ってもらえているようです」。
中国で販売するためには現地の規制に従うということを念頭に置かなければならない。なかでもよく知られ頻繁に議論の対象となっているのは、やはり動物を使っての試験が義務づけられているということだろう。この政策は西洋で「クルエルティ・フリー(残虐行為根絶)」を掲げる人々から猛烈な批判を呼んでいるわけだが、ここでは「クロスボーダー」で、つまり文字通り中国国外から販売することで、この規制の網の目をかいくぐることができる。例えばコスメブランドのフェンティ・ビューティはアリババ・グループのプラットフォーム、天猫(Tmall)に出店しているが、香港経由で販売することでこの問題を回避している。また別のブランドがそうしているように、国外へ出国する中国人旅行客にターゲットを切り換えるという方法もある。「健康スキャンダルが多く発生した過去を持つ中国国内では、動物実験はさほど議論の対象とはなっておりません」とダオ・グエンは解説する。「ペットの飼育が増えてきておりますので、今後変わる可能性はあるかもしれません。ですがペット文化と動物実験の是非が同じ価値観に基づくものではないということもまた確かなことです」。
同じではない、ということは味覚や嗜好に関しても言えることだ。中国の消費者たちは彼ら独自の基準に基づき成長してきた。「甘い」という概念が想起させる味覚的感覚もフランスとは異なるし、バニラも中国の食文化にとってはまったくなじみがない。しかしだからと言ってそうした地域的な嗜好を考慮して「フレッシュな」香水を売りこもうとするのはいささか短絡的だ。
「中国には14億人もいるのです」とダオ・グエンは強調する。「彼らがフレッシュな香りを好むというのは実際よく言われていることですが、それでも現実の全体像を反映しているわけではありません。『ブラック・オピウム』をつけている若い女性たちだって多くいるわけなのですから」。一方で、旅をするミレニアル世代が香水市場に対しどんなことを期待しているのか、ということに関しては万国共通だ。すなわち、店頭でのさまざまな体験、パーソナライゼーション、そしてブランドの由来をめぐる秘話。香水産業においてはいまだマーケティングや大手グループによる利益追求が大きな影響をおよぼしているわけだが、ここに挙げた中国の事例は、こうした大きな力ですらすべてを画一化することはできないということを明確に示しているように思われる。
どの国や地域であろうと、旅をする「ミレニアル世代」は皆同じことを期待している。すなわち店頭でのさまざま体験、パーソナライゼーションなど……。
「世界の香水市場、どこが一番売れているのか?」2018年における香水市場の総額は数十億ドルにおよぶ。下記はその内訳である(出典:ユーロモニター・インターナショナル)。
アメリカ:8.39億ドル
ブラジル:6.88億ドル
フランス:2.60億ドル
イギリス:2.52億ドル
その他の地域:50.96億ドル