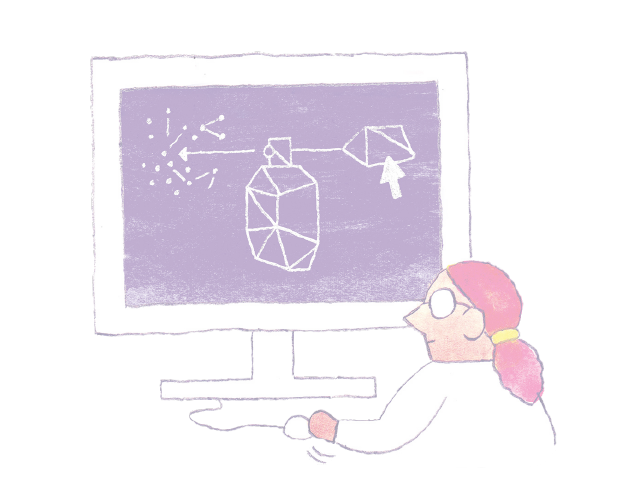2017年秋、ドイツBASF社が管理するルートヴィヒスハーフェン所在の工場で反応炉が火災を起こした。この火災はシトラールの流通に壊滅的な影響をおよぼした。このシトラールという物質は柑橘系の匂いを持ち、大量消費向けの香水にも高級な香水にも広く使用されていた。またこの業界で用いられる他の多くの分子を合成するための起点となる成分でもあった。高度に集約化された産業においては、主要サプライヤーの工場が停止してしまえばその産業に従事するすべての構成員が影響を被ることになる。最初に影響を受けたのは香料メーカーであった。香料メーカーは異なる分野のさまざまなブランドに向けて香水や香料を調合する。つまり下請けとして、特定の要求に応じて新しいフレグランスや洗剤、シャワージェルといった製品を作るのである。また香料メーカーは原材料のサプライヤーでもある。そして企業の収益の大部分が、香水を調合するために使用されるそれらの分子の売上げからなっていた。
BASF工場で起こった事故を受け、香料メーカー各社は業務を続けるための解決策を模索することに奔走することとなった。しかしどの企業もこの問題について公けにコメントすることを避け、この件について消費者に対しどのような情報が伝えられたかも明らかにしなかった。ある企業の情報筋が匿名を条件に述べたところによると、いくつかの商品の再調整を同社の顧客とともに行う必要があったという。「再調整が行われる場合はもちろん法令に則ったうえで、すなわちHSE(hygiène「衛生」、sécurité「安全」、environnement「環境」)の規則を遵守したうえで行われます。香りとしての性能に影響はなく、香水としても安全です」。他の企業も、このような状況こそ他の自社製品をアピールする好機ととらえるべきだとコメントするにとどまった。これらの企業は売上げをのばすためのイノベーションに企業の命運を賭けていた。平均して収益の10%を研究開発(リサーチ&デベロップメント)費として再投資し、新たな分子を創出することをその目標に掲げる。そうすることによって「香りに関わるあらゆる分野においてバランスの取れたレパートリーを有することができ、その結果調香師たちは香水を作るにあたってあらゆる成分とノートを自由に使うことができるのです」と、フィルメニッヒ社副社長兼合成責任者のジル・オッドンは補足する。
そのプロセスには膨大なコストがかかり、ひとつの分子を開発するのに実に約200万ドルもの研究開発費があてられる。そのため各社は注力すべき方向性を慎重に見定める必要があるわけだが、いったいどのような基準がそこでは考慮されるのであろうか。その香りに想定されるヘドニック変数(個人や集団の幸福や満足度にどのような要因がいかに影響を与えるかを分析するために用いられる変数)はもちろんのこと、分子を生産する際にかかるコスト、ターゲットとなる市場での競争力や、特許を取得できるかどうか、あるいは環境への影響、生産ラインへの導入から市場への投入にいたるまで、さまざまな基準が検討される。これら柱となる要素がひとつでも欠ければ、その研究が完遂されることはないというわけだ。
発明し直されるスズラン・ノート
研究開発活動の目的のひとつは、刻々と変化する規制に対応すること、そして可能であればその規制がどう変化するかを予測し先取りすることである。香水に使用される原料の安全性を確保する役割を担う国際香料協会(インターナショナル・フレグランス・アソシエーション)がいくつかの分子の廃止を定期的に勧告しているからである(ジュリエット・ファリウによる記事を参照のこと)。そうした措置が通告された場合、施行されるまでには平均して5年の猶予が与えられるが、この5年という年月はそっくりそのまま、廃止される分子の代わりとなる成分の開発期間にあてられる。
例えば香料メーカーは現在各社とも、スズラン・ノートの研究開発に注力しているようである。このノートはこれまで主としてリリアールとリラールから得られていたが、これらの合成分子は香水製造に広く使われる一方で、接触アレルギーを引き起こす可能性のある物質としても知られている。これらの分子の流通する規模から見ても、満足のいく代替案を最初に提示することのできた企業にはかなりの経済的利益が見こまれるだろう。満足のいく、というのはヘドニック変数は言うまでもなく、価格、性能(すなわち香りの強さ)といった基準、実行可能な製造プロセスであるかどうか、といったことを含めた条件を満たしたものであるということだ。 香料メーカーが新たな香りを生み出そうとしているとき、それはときとして、すでに機能している歯車を再びわざわざ発明し直すようなものではないかと、そんな風に映るかもしれない。だが事実、まさにそうすることによってラインナップは補完されているのである。「自社の有するレパートリーを評価し見積もることを通してこそ、われわれはそこにどのような好機が眠っているのかを策定することができるのです」、そうコメントするのはIFF(インターナショナル・フレイバー・アンド・フレグランス)副社長、香料研究開発責任者も務めるジョン・チェルカウスカスだ。「われわれは北米に向けて非常に豊かで多くの製品を提供してきましたが、アジア市場の需要を満たすためにはまだまだ分子が不足しています」。どのような場合にも、調香師と研究者はトレンドを見極めるべく協力しながら仕事をする。
なぜなら調香師こそが香料メーカーにとって最初の顧客であると言えるからだ。「何か革新的なものを作り出すことが彼らにもインスピレーションを与え、それを好機に彼らは新たなるアイデアの探求へと乗り出すことができるのです」と、ジボダンの香料開発部門主任化学者のフィリップ・クラフト博士は述べる。博士は自分がトレンドの仕掛け人であると思われることを好んでいる。博士によれば、たとえ技術の発展によって「いくつかの分子が安価になり、その結果自分たちがそれまでとはちがったさまざまな方法でそれらを使えるようになったとしても、それでも真のインスピレーションとは分子のモデリング、さらには化学者=調香師としての創造性によってもたらされるべきなのです」という。すなわち換言すればそれは、他の関係者を刺激する可能性を秘めた新しい香りを設計できる化学者の能力によって、ということになるだろうか。 フランソワ=ラファエル・バレストラはフィルメニッヒ社で機能性香料の開発を担当する化学者であるが、合成による、さらに言えば生体合成による新たな成分を開発する主任調香師でもある。毎年、彼は研究部門で開発される約2,000もの分子を審査したうえ、それらをふるいにかける。彼が評価をくだした後、そこから200が生き残る。多くの調香師たちが世界中にちらばるさまざまな制作部門で働き、審査を担当する。審査の対象は無加工の原料そのままのときもあれば、調香中のもの、あるいはもうすでに香水の形になっていることもある。ときには「遊ぶような」感じでそれらの成分を色々試してみるよううながされることもある。そして最終的にはたった4種か5種類の分子だけが香りのパレット(各自が制作のために自由に利用できる天然または合成原料のセット)のなかに加えられる。そうするころにはだいたい6年が経過している。フランソワ=ラファエル・バレストラは出張で海外の制作部門に行く機会を活用し、市場の動向を把握する。「そしてニーズを特定し、それに対応した詳細な開発計画を研究部門に伝達します」。 こうしたプロセスは他社においても似たようなもので、ただ審査する分子が年間500であるか3,000であるかといった数のちがいでしかない。開発サイクルは平均して5年におよぶという。
「藁山のなかから針を見つけ出すようなものではないか」というのがチーム内で繰り返されるおなじみの表現となる。
まず乗り越えねばならない試練は、開発するうえで義務づけられたいくつもの検査である。例えば、生み出された物質が生物に対しどの程度有害であるかを調べたり(毒性一般)、それらの物質が自然環境のなかでいかに分解され無害な物質に変じるか(生分解性)、あるいはその安定性といったものや、皮膚に接触することでアレルギーを引き起こす可能性があるか(皮膚感作性)など、実施すべき試験がこのように数多く存在する。しかも国によって法令が異なるのだ。「基準が各国で異なるため、色々な場所で何度も試験を行わなければなりません。例えば中国ではそのいくつかに関して、中国国内で実施されたものしか認証されません」、そう証言するのはシムライズ社で研究開発責任者を務めるエミリー・シンガーだ。ひとたび成分が開発された後も、それが登録されるまで平均して3年もの月日を要する。そしてその費用は20万から25万ユーロにものぼるという。
こうした手続きと並行して、分子そのものの開発作業も開始される。所用期間については、そこで採用される合成プロセスの複雑さや目標とする売り値によっても変わってくる。そしてその売り値についてだが、「キロあたり100ドルのこともあれば、10ドルのときもあります。それにしても[製造]工程を5、6段階も要する分子をたった10ドルで売るために作ることは、しかも環境に配慮した化学(グリーンケミストリー)、あるいは持続可能な発展、といったわれわれの掲げるポリシーを遵守したうえでそれらを作ることは、本当に骨の折れる挑戦です。博士号所持者やその道の専門家たちにいたるまで、われわれの持ち得るすべてのノウハウを動員しなければなりません」、そうジル・オッドンは語る。
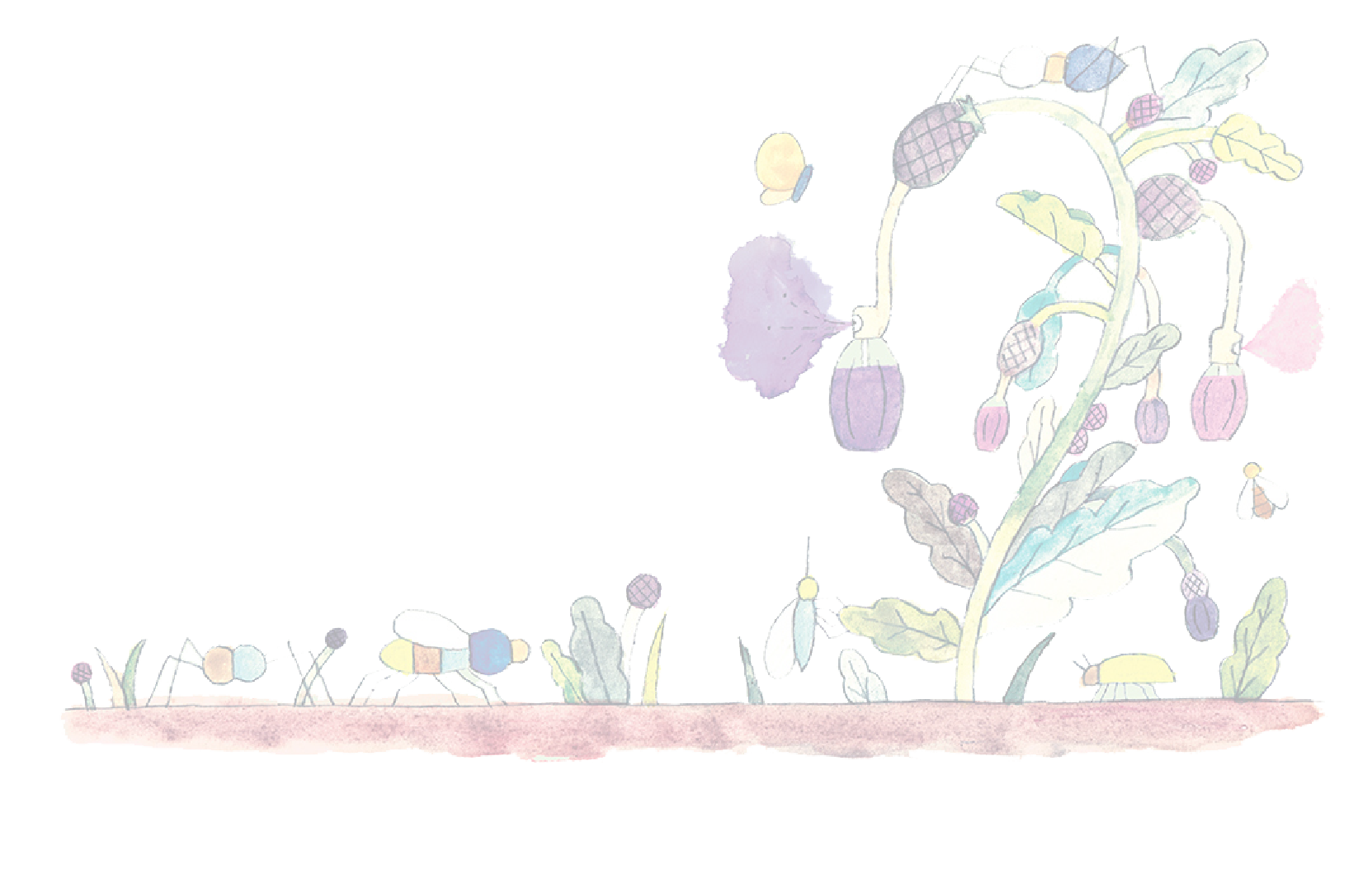
クロマトグラフィーによって特定されないため、いわゆる「キャプティブ分子」は配合のなかに使われてもコピーされる心配がない。
キャプティブ分子とは何か
生産物の特許を取得することは研究を継続するうえでの必須条件となる。特許を申請することで当該分子が保護され、その分子を作り出した者が20年間独占的にそれを使用することができるからだ。しかもその分子がまったく未知のものであった場合、その分子の製造方法や香水への応用といったものまでもが特許化される。そして他分野において既知であったとしても、香水への応用には特許が適用されるといったケースもある。
したがって香料メーカー各社は特許を取得した成分の使用を自社の調香師だけに許可するという判断が可能になる。調香師たちが独自の原料を用いて仕事ができるということはすなわち、競合他社との差別化につながるわけだ。このような分子を「キャプティブ分子」と呼ぶ。「独占分子」という呼称もある通り、配合への独占的使用が法的に保護されており、クロマトグラフィーで特定できないため他社からコピーされる心配もない。このような分子を各社がいくつ所持しているかは不明であるが、シムライズ社だけでも15から20種類のキャプティブ分子を有しているとのことである。
この独占による制限期間がどのくらいであるかは、各社の取る商業的戦略によるとしか言いようがない。そしてそうした戦略も、例えば競合他社がその分子に強い関心を示している場合、かつ大量生産が保証され、それによって投資回収が容易にできそうな場合などには変動する可能性も高くなってくるわけだが、そうでない限りは慎重さを期すことが求められる。特に生産面においては。「同社のキャプティブ分子は自社工場のみが占有的に製造しています」、そうエミリー・シンガーは強調する。
しかしいくら香水産業において当たり前のものとなった秘密主義と言えど、他の分子が外注されることを完全に防げるわけではない。他の部門と同じように、生産能力が低下したときや社内では習熟されていない技術に頼る必要があった場合、あるいは地理的な条件面からその必要にせまられたときには、分子は外注されやすくなる。「例えばインドにある自社工場では製造工程の大部分を完了させることができますが、不要な中間輸送を省くため、われわれは現地のパートナーとも協力しています」と、ジル・オッドンは明かす。生産ラインに対しては資本が集中的に注がれている。市場はグローバル化の一途をたどり、製品処理プロセスもますます複雑になっているからだ。匂い分子は石油原料由来の成分を起点に合成される。持続可能な開発を実現するための責任を促進することを目的に1990年代始めごろ導入されたグリーンケミストリーの12原則は、香料メーカー各社全般にわたって遵守されている。これについて規制業務担当のマリー・ドランジェは、「製造プロセスが分子の構造に対し変化を加えることは何もありません。変えられるものがあるとすれば、それは環境に対する影響でしょう」とコメントする。今日の業界内では、より毒性の低い試薬を用いること、溶剤とエネルギーの使用量削減に努めること、廃棄物を最小限にとどめること、などといったことが標語となっているわけだが、こうしたアクションが環境問題に貢献する意義やコミュニケーション面での利点とはまた別に、経済的な恩恵さえ期待できるということに香料メーカー各社は早くも気づき始めている。