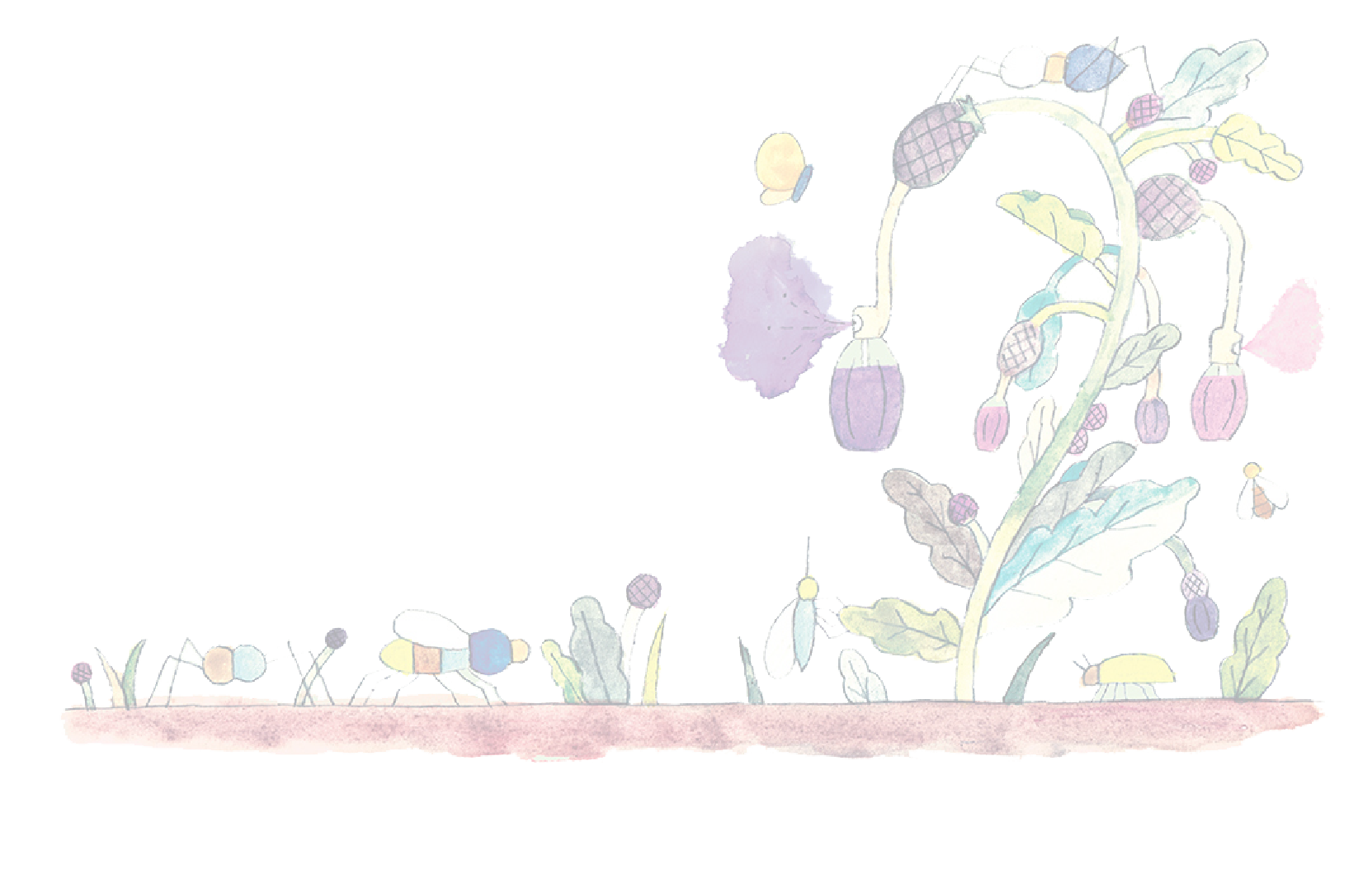「そのとき私は次のごとき直観を得た。すなわち言葉を持たないとき、人は迷う。そうだ、本当に迷い子のように迷ってしまうのだ! いらだちを覚えて、テーブルの上に香水を置き、ただムイエット(試験紙)を通過させるにまかせながら、私は何も言わなかった。そんなことがあった。皆は互いに顔を見合わせながら、いったい何が起こったのかとささやき合った。そして何を言うべきかが分からなくなった彼らは、原料について語り始めたのだ」。セルジュ・ルタンスはそうと知っていてわざとこんな風にヴィトゲンシュタインめいた言いかたをしたのであろうか。語り得ぬものについては人は沈黙せねばならない、という有名な言葉を1921年に残したオーストリアの哲学者であるが、そのヴィトゲンシュタインもきっと、広報担当者という役職があるなどとは思いもよらなかったであろう。香水というこの形のない商品をプレゼンテーションする場において、沈黙はさすがに論外であろうが、一方で、今日の業界のイメージを支配する「物質主義」の隆盛に首をかしげたくなるのもうなずける。まさに自然とは真逆の方向へ行くことによって香水の近代化は成ったはずだからだ。モダニズム美学の頂点に立つシャネル「No.5」は、一点もののオブジェのようでいて、各原料の上に目立つごつごつとした荒削りな部分を研磨してならし、なめらかにしているようなところがある。そのような「一着のドレスのように人工的な、言ってしまえば作り物のような」面については、そうガブリエル・シャネル自身もすすんで強調している通りである。その点についてはフランス的贅沢を体現するもうひとつの至宝、高級料理(オート・キュイジーヌ)と比較できるかもしれない。「皿の上の料理を、純粋なるひとつの抽象的記号に変化させること。自然的産物をわがものとして支配するひとつの試みとして表現すること。工場やアトリエで作られるものに可能な限り近づけ似せること。それこそが同じである、ということに取り憑かれたブルジョワ的想像力にくみするための大原則なのである。食材にソースを塗ること、つやをつけること、コーティングを施すこと、といった作業は工業製品に対して言う『仕上げ』に対応するものである」と、ニコラ・ブーリオーは『料理の書、その技法と工程』(パリ美術出版局、2013年刊)において記している。原料の上に形を与え表現する近代の香水も、そしてこのようなブルジョア的料理も、西洋思想における基本原則を例証していると言えるのではないか。その原則とはすなわち、自然に対する文化の優位である。
化学という禁忌
ベル・エポック(十九世紀末から第一次大戦ごろまで)から始まり「栄光の三十年間」(1945年から75年まで)へといたる香水の黄金時代は、上記のごとくただ原料の物質性のみを前面に押し出すことに対し拒否が突きつけられた時代であったわけだが、くわえて、調香師と化学というふたつの圧力によって板ばさみにあっていた時代でもあった。そのどちらもが生産の現実に深く関わってくるぶんこれは二重に厄介であった。「ゲランでもシャネルでも、手段はたくさんあったはずだが、そのすべてが自然、もしくは自然的な性質を有するものの上にその基礎を置いていた。確かに自然原料があり、皆がそれについて話していた。一方で合成について口にすることはタブーだった」、調香師モーリス・ルーセル(現在シムライズ付)はそう回想する。1973年には化学者としてシャネルの開発に参加していた。ピエール・ブールドンやアルベルト・モリヤスらといった豪華なメンバーとともにに、共著『香りをめぐる諸問題』(コープマン出版、1988年刊)を上梓。このなかで複数の執筆者たちがこのタブーについて皮肉をこめて書いている。「バニラは人に夢を見させるが、バニリンは[...]その夢を悪夢に変えてしまう。毒草のことや地震のことなどとうに忘れて、人々は自然を単に『良きもの』だと考え、『本当の』香りを実現するのに役立つただひとつの匂いの供給源だと思いこんでいる」。またもや逆説的なのは、香水が誘惑のためのツールとして売り出されているということだ。というのも誘惑とはある意味欺瞞によって人をだますことであり、ここでは商品をめぐっての欺瞞が起こる。すなわちそれが人工的なものであるという。「その後、ここ20年ほどのあいだに調香師たちが表舞台に立ち始めた」とモーリス・ルーセルは見ている。「彼らは自分たちの調香について自ら語り始め、香水が決して天然成分だけからできているわけではないということを伝えようとした。それによって彼らは香水の持つ美的価値を説明しようとしたのである」。
原料優位への回帰
こうして「沈黙の掟(オメルタ)」が破られ始めたのと時を同じくして、具体的自然原料をまったく新しい形で表現するニッチフレグランスのブランド各社が頭角を現し始めた。ニッチフレグランスは、香水の黄金時代に立ち帰ろうというノスタルジックな思想にその根を持っていた。中世のポマンダー(オレンジのまわりにクロブを敷き詰めたイギリスの魔除け)を連想させるスパイシーな香りが特徴であるディプティックの「ロー」(1968年発売)を皮切りに、レミニセンスからは「アンブル」「ムスク」「パチュリ」の三部作(1970年発売)、調香師ユーリ・グツァッツ創設によるル・ジャルダン・ホトルヴェからは単一の花の香りを表現したソリフロールが(1975年)、そしてジャン=フランソワ・ラポルト率いるラルチザン・パフューム(ラルチザン「職人」という語が含まれるそのブランド名は産業革命以前の時代を想起させる)もまたソリフロール創作した(1976年発売)。こうした花や植物の香りを主役とした作品が次々と登場するなかで、ニッチフレグランスというムーブメントはこの時代における自然を重んじる感覚を見事に体現していたと言ってよいだろう。そして同じ時代に同じような感覚を体現していたのが、あの革命的な「ヌーヴェル・キュイジーヌ」だった。「ヌーヴェル・キュイジーヌ」では原料そのものが持つ品質と価値が最もクローズアップされる。「原料そのものを提示するかのような具象的な料理」、そうベルナール・ロワゾーシェフは表現している。同じようにセルジュ・ルタンスは、冒頭にも見られたようなマーケティングの現場で繰り広げられる「混沌とした、しかし空虚で無駄な議論」への反発として、単一の植物の香りに焦点を当てた「ソリノート」の創作を試みた。このように原料の具象性への回帰を志向することこそがこれら例外的香水において最も共通した特徴であると言えようが、とはいえそれは単に自然とつながりたいという願望だけを意味しているわけではない。あらかじめ想定されたイメージを提供するファッションブランドとは対照的に、ニッチフレグランスはそのイメージを通して(しかもそれを言葉で表現しなければならない)主眼たる香りを根づかせなければならない。すなわちかぐわしい植物の香りを。なお、一般の人々にとって良い香りとは自然の香りであると刷りこまれているため、表現しようとするもの(アコード、ベース、ノート)から実際の成分への落としこみは、そこまで難易度は高くはならない。