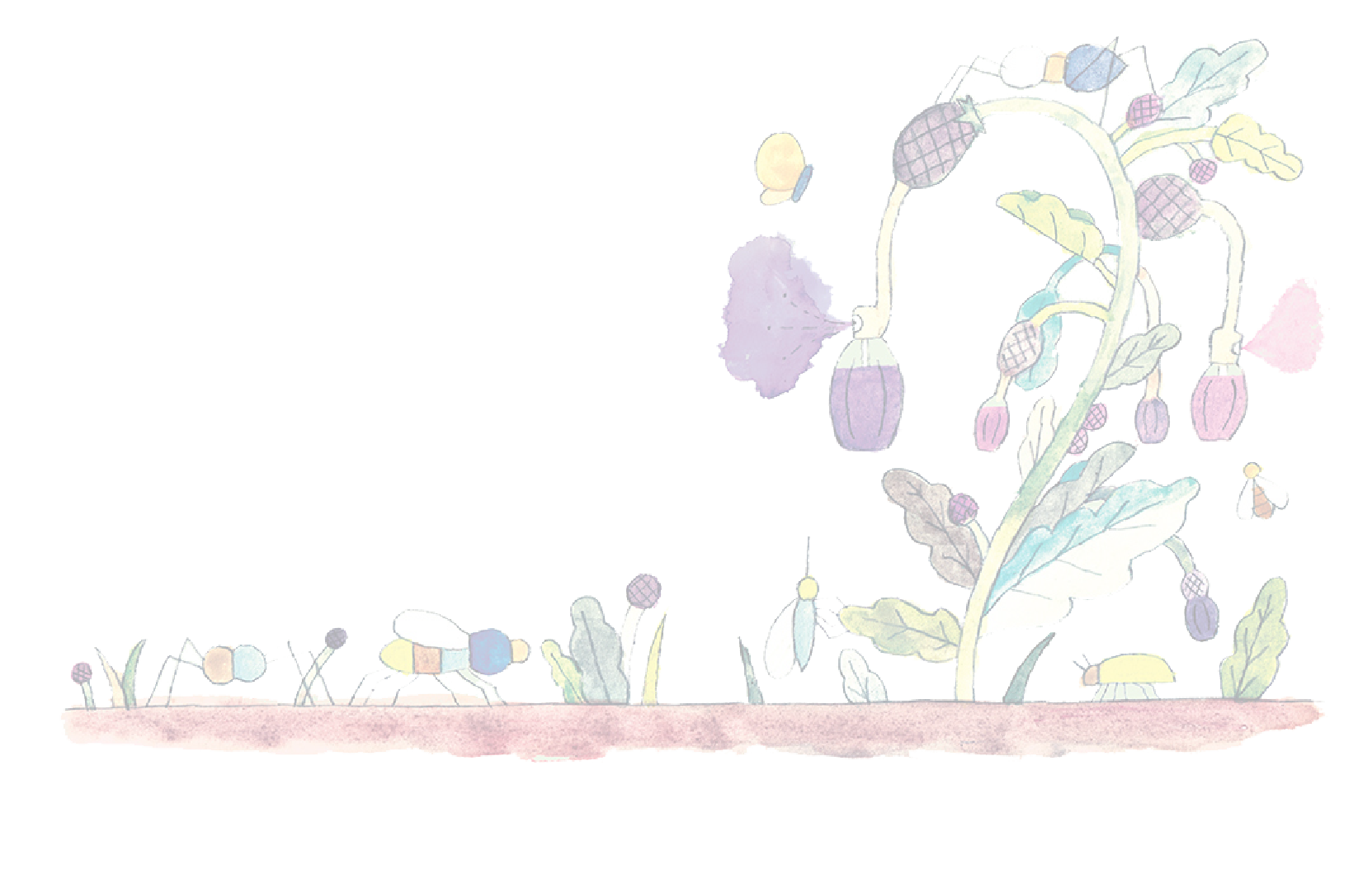「リスクゼロ」を目指すことは、香水を始めとした化粧品業界全体に課せられた使命である。化粧品の作用があくまで皮膚の上にのみ及ぶものである限り、特段命に関わるものでないように思われる。そのため化粧品はその利用者に利益だけをもたらすのであろうとそう見なされてきたわけだが、しかし今日において消費者たちは業界大手に不審のまなざしを向け、より健康的でより自然な選択肢のほうへ注目し始める人々が増加している。コスメビオ協会のアンケートによれば、オーガニックないし自然化粧品の消費者の3分の2が初回の購入に際し、環境意識や健康上の問題、あるいはその健康に対し化粧品が与える影響への懸念といったものが決め手となったと答えている。そして調査対象となった41%がこの種の製品を使用し安心感を得ていると回答しているという。オーガニック香水やエッセンシャルオイルの需要が高まるなかで、2017年にはこれらの売上げが約20%増加した。一方で、化粧品業界はここ15年のあいだ、使用された合成分子がらみで何件かのスキャンダルに起こしている。その背景には人間の手によって作られた素材と、自然界に始めから存在していたものとの対立関係に起因するある種の恐怖心が透けて見える気がする。とはいえ自然であることが無害であることを即座に保証するものではないということもまた、ずっと前から知られていることであるはずだ。1937年には早くも、鎮痛作用の薬効がある植物、ウィンターグリーンの精油による中毒事故が6件報告されている。すべて成人で、うち3名が死亡。その3名はそれぞれ15ml、30ml、80mlの精油を経口摂取していた。そして当時24歳だったアメリカ人女性エミ
リー・スミスは2017年11月、ディフューザーから噴霧された精油の原液を誤って浴び、顔に深刻な火傷を負った。つまりこれらの事案から言えることは、こと健康衛生面に限っては(つまり環境に対する配慮などは除いてということだが)天然であるか合成であるかという対立関係は、科学的視点から見てもほとんど意味をなしていないということなのだ。「合成分子の利点は、対象となる成分の構造を(すなわちその分子を構成する原子の空間配置を)正確に把握できることです。それによってアレルギー反応を起こすリスク(感作性ポテンシャル)を明らかにすることができます。一方で天然抽出物はこれよりはるかに複雑です。300以上もの分子を含むとも言われ、そのなかには未知のものさえあるのです」、化粧品産業における規制管理業務を担当するマリー・ドランジェはそのように語る。香水に対する消費者たちの懸念は2000年ごろからじょじょに高まり始め、やがて食品産業に対するそれと同じような動きをたどっていくことになった。「自分が肌に何を塗って、何を環境のなかに排出しているのかが心配になってきたのです」、マリー・ドランジェはそう言葉を継ぐ。
毒性リスクについて
どのような香水も分子から構成されている。それが天然由来であれ合成プロセスを経たものであれ、あるいは自然界に存在するものであれ人間によって開発されたものであれ、みな例外なく。そして生体にとって異物である物質には例外なく毒物としてのリスクがある。その毒性の影響は治療可能な場合もあれば不可能な場合もあり、ときには死を引き起こすこともある。香水の一部成分はアレルゲンであり、その他の成分には発がん性(Carcinogenicity)、遺伝物質に変異を引き起こす因子(Mutagenicity「変異原性」)、生殖毒性(Reproductive toxicity)に分類されるものがあり(これら3つの頭文字を取りCMRと総称される)、そしてなかには内分泌かく乱を起こす可能性を持った因子もある。接触アレルギーで相談に訪れる8%から15%が香水に対しアレルギー反応を起こす兆候を見せたと見積もられているが、実際のところ正確な有病率はいまだ明らかにされていない。現在欧州規制のリストに記載されている26のアレルゲンのほとんどが自然抽出物に含まれる分子であるということも注目に値するだろう。マンダリンオレンジの精油の主成分であるリモネンもこのリストのなかに入っている。CMR分子はすでにそのほとんどが禁止されているものの、無害な濃度に希釈することで許容されているものもある。ローズオキシドがその例だ。バラの抽出物のなかにもともと存在している分子だが、その含有量は危険をともなう割合ではない。つまりこうした物質やアレルギー問題に関しては、「量が毒を作る」というパラケルススの格言が示している通りなのである。有名なのは青酸カリなどの原料となるシアン化物であるが、これが完全に天然のものであった場合、例えば体重60kgの人にとって0.48gからが致死量となる。したがって、それ以上だと悪影響が引き起こされるという閾値を明確にすることが争点となってくるわけだ。その閾値に加え、個人間の感覚の差異や一日のなかで偶発的に摂取してしまう(曝露)量の最大値を考慮した安全マージンを設定することで、認可レベルの上限を導き出すことができるのだ。バラに含まれるもうひとつの分子、メチルオイゲノールは製品カテゴリーによって0.0002%から0.01%とその含有量にはばらつきがある。内分泌かく乱物質は天然素材だけではなく合成素材にも同様に含まれ得るが、その危険性が認知され始めたのは比較的最近のことである。欧州当局がこれらの物質をめぐる定義を採択したのもようやく2017年12月になってからのことだった。決して軽視されているわけではないものの、化粧品におけるこれらの物質のリスクはいまだ正確に見積もられていないというのが現状だ。というのもこの内分泌かく乱物質に限っては、毒物学における基本的アプローチ方法である「用量と効果」の関係則が通用しない場合があるからである。ごく少量偶発的に摂取しただけでも、多量に摂取するより深刻な結果をもたらす可能性もある。クラランス・グループ研究開発部門元責任者のリオネル・ド・ベネッティによれば、「現行する科学的知識に基づいて申し上げるとすれば、認可されているすべての物質は通常の用法用量で使用されている限り、あらゆるリスクを免れていると言えます」とのことである。とはいえ消費者にとってはこうしたどこか要領を得ない、歯切れの悪さも懸念材料となっているのだろう。
欧州規制リストに記載されている26のアレルゲンのほとんどが、例えばリモネンのように、天然素材からの抽出物に含まれる分子なのである。
フタル酸と合成ムスク
こうした疑惑は消費者団体やNGOが公表した報告書によっても高まることとなった。なかでも有名なのはグリーンピースが2005年に発表した調査書「香水におけるスキャンダル」であろう。この調査ではさまざまな香水のなかに含まれるフタル酸エステルや合成ムスクの含有量が測定された。さらなる懸念を呼んだのは、事実としてこれらの化合物が血液や母乳から検出されているということだ。しかしある液体内にある物質が存在するからと言って、その物質に毒性があるということを即座に示すわけでもない。したがってフタル酸類などある分子群をひとくくりにして非難するのは誇張的だと言わざるを得ない。例えば一部原料の溶媒として使用され、アルコールの変性剤としても使用される(コラム
「香水瓶のなかには何が入っているのか」を参照のこと)フタル酸ジエチル(DEP: Diethylphthalate)がグリーンピースによる調査内で槍玉にあげられた。しかし繰り返し安全性評価が行われた末、いかなる危険性も見出すことができなかったと消費者安全科学委員会(SCCS:Scientific Committee on Consumer Safety)が明らかにした。この委員会は科学的問題について欧州委員会に勧告する専門機関である。一方で、フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP: Diethylhexyl phthalete)は確かに内分泌かく乱物質であると特定され、化粧品への使用が禁止された。次にガラキソリドに関してだが、この分子は衛生製品や香水にも頻用される人工ムスクの一種であり、同じくグリーンピースによる調査対象となっていた。先の消費者安全科学委員会を含む、欧州連合に属する複数の科学機関により2002年、2003年、2007年と検査が実施され、その結果、人体や環境に対し目立ったリスクは
見出されないと結論された。そしてこの結論は2014年、合衆国の環境保護庁によっても確認されたのだった。ところが一転して欧州化学機関(ECHA: European Chemicals Agency)により水生生物に対し大変な毒性があると判定されると、その結果、機能性香料(洗剤や柔軟剤など)にガラキソリドを多用していた調合会社大手各社は以降代替品を使用するようになったのであった。高級フレグランスには依然としてこのガラキソリドが使われ続けているものの、その使用量は微々たるもので、環境への排出に関してもその影響は無視してさしつかえないものである。
透明性の要求
香水業界の関係者たちは香水作りにおける多くの利点から合成を擁護する努力を惜しまないが、しかしながら化学という分野が一般においてはごく狭い層にしか理解されておらず、そのため今のところは不安感を与える側面だけが強調されてしまっているというのが現状であろう。「なので自然製品に関してはわれわれも透明性を求める声に対応することができますが、残念ながら現時点では、合成物は不透明なままなのです」と、自然化粧品を専門とする独立コンサルタント、ミュリエル・フォルマール=カーンは解説する。多くの人々にとっては「シャマエメルム・ノビーレ」という言葉を読むときのほうが(ローマカモミールの学名、ラテン語名だ)、「1-メチル-4-プロップ-1-エン-2-イル-シクロヘキセン」(柑橘系植物に含まれるリモネンの化学名)と記載されているのを目にするよりも安心できることだろう。一方で、現代の社会の方向性を決めるにあたり強い影響力を有しているミレニアル世代は、今や透明性は企業と顧客との信頼関係を築くにあたり非常に重要なものとなっているととらえている。プロクター・アンド・ギャンブルは化粧
品に含まれる香料成分の詳細を、その成分が0.01%を超える場合に公開する体制を2019年までに整えると発表した。しかしこのような取り組みに続こうとする企業は今はまだ少ない。香水にはコピーから保護するための法的手段がほとんどなく、その数少ない手段である企業秘密の理念と正面から衝突してしまうからだ。
さらに多くの業界関係者たちがそろって、化粧品および香水業界はコミュニケーションの面で問題があると指摘している。「誰もが発言を恐れており、反応までの時間が非常に遅いのです。発表が行われるころにはもうすでに、何か悪いことが起こっているということがしょっちゅうです」とリオネル・ド・ベネッティが状況を要約する。フタル酸類のケースがそのいい例だろう。問題を引き起こす可能性のあったフタル酸系分子のうち、その多くは香水ではなくプラスチックの製造に使われていた。にもかかわらずこの点について一般の人々に届くような発表は何ひとつ行われず、結果としてこの主題をめぐって世間に流布している誤解を払拭することができなかったのであった。香水業界特有のこのような内気な性格は、関係者たちの意欲や真剣さに対して向けられる疑惑を知らず知らずのうちに助長してしまっているのではないか。このような現状はこの業界に対し正当な評価を与えるものではあるまい。何せ香水業界は40年もの長きにわたり製造方法と自己管理方法を絶えず革新し続けてきたのだから。しかしながら、これは驚くべきことであるが、1970年代ごろまで化粧品の製造および使用に関して規制と呼べるような規制はほとんど存在しなかった。「当時は誰もが何を作ってもよく、どんな製品を使おうが自由でした。ですがもちろん、それは普通のことではありません」、そうリオネル・ド・ベネッティは留意する。当時は化粧品が皮膚というバリアを透過するものだとは考えられていなかったのである。フランスでは1972年、赤ちゃん用ベビーパウダー「タルク・モランジュ」に起因するスキャンダラスな衛生事故が発生し、当該製品に含まれるヘキサクロロフェン(殺菌剤)による事故汚染で36名の赤ちゃんが死亡したことを受け、ようやく当局が動き出したのだった。