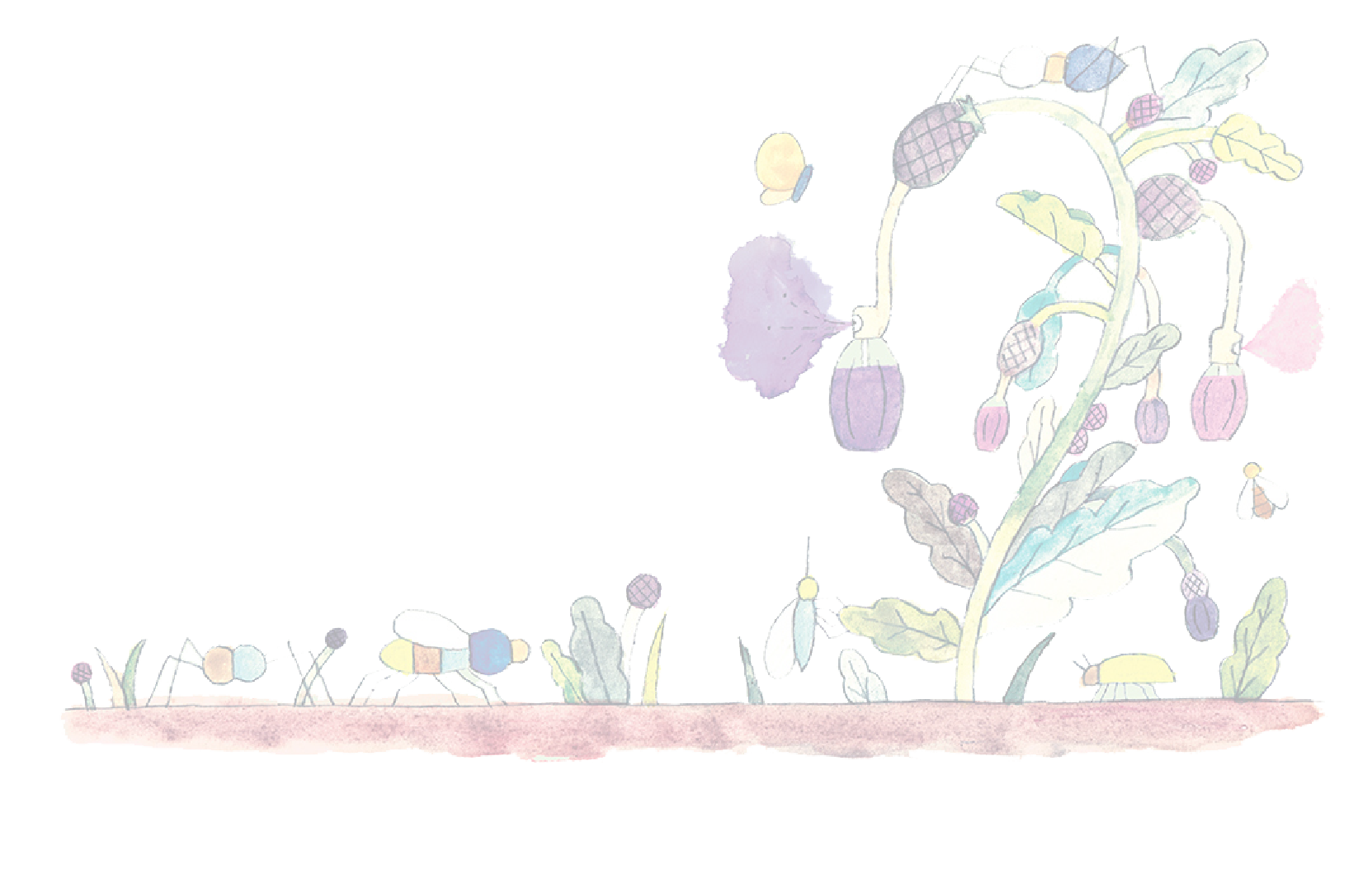食品産業の工業化が進むにしたがいその当然の帰結として、何か口に入るものがあるところにはどこへでもアロマ(香料、香り成分)がつき従うようになった。フランス消費者法典および欧州規則が定める定義によればアロマとは、「そのままの状態で消費されることを目的とせず、食品に対し香り、さらに/または味をつけ加えることによりその食品に変化を与えるためのもの」を指す。つまり食材の持つ味や香りを整え修正を施す加工材料であるわけだ。整えるばかりではなく、ときに増幅させ、ときに引き立たせ、強調する。では食材の性質を変えてしまうようなことも、すなわち自然な状態から逸脱させてしまうようなこともあるのだろうか? これについてはアロマの付加されていないヨーグルトを指して「ナチュール(自然)」と呼ぶことが暗に示しているように思える。アロマが付加されるやいなや食材は自然なもの、生のままのものではなくなり、人工の領分に移行してしまうかのようだ。とはいえ自然な風味を再現するためにデザインされている以上、人工的なものそれ自体は味において目立たないことが多い。したがって良いアロマとは、使われていること自体が忘れ去られているアロマであるということだ。控えめであるか否かにかかわらず、アロマはどこにでも使われている。「国内で生産されるイチゴの総量をもってしても、すべてのイチゴヨーグルトに香りづけするにはまだ足りません」、ジボダンのシニア・アロマティシャン、アルノー・ブスケはそう語る。イチゴヨーグルトに含まれるほんの数切れの果実片ではイチゴ味と分かるような風味を伝えることはできず、したがって消費者の期待を満たすためにはアロマの添加がまさに必要不可欠なものとなる。調香師という職業が皆ある程度の抽象化を許容できる素質を持っているのは、まさにこのような現実よりも本物らしい精巧な非現実を作りあげること(ハイパーリアリズム)こそがアロマティシャンの本懐だからなのだと、そうアルノー・ブスケは強調する。口に入った瞬間の感覚は、ラベルに記載されている約束と一致していなければならない。イチゴヨーグルトはアロマが使用される食品のなかでも最も多く消費されているものの一例であるが、どうだろう、ちゃんとイチゴの味がするではないか。事情を知らなければ、たががイチゴヨーグルトに複雑な解釈もスタイリングも装飾も何もないように見えるわけだが、実はこのような背景があったのである。そのイチゴヨーグルトも国によって味が異なる。消費者の寄せる期待やフルーツに対する味覚的イメージによって適用されるアロマの構成も変化するからだ。文化や食育のちがいから、例えばスペインでは「さっぱりとしていてフレッシュな」、フランスでは「さっぱりとしたなかにもフルーティーさのある」味となり、さらにドイツでは「ジャムのような」、イギリスでは「キャンディみたいな」味が好まれる傾向にあると、IFF(インターナショナル・フレイバー・アンド・フレグランス)シニア・アロマティシャンのジャン=フィリップ・フルニオールは語る。一方ロシアではより「フローラルな」イチゴ、すなわち「木イチゴ」の味が好まれるという。これらイチゴ味と同様のことがバニラについても言える。ただしこの場合目立った例外はフランスのみで、というのも他の国ではただ単にバニリンのもたらす風味で満足されるのに対し、フランスではそれに加え「キャラメル、フローラル、スパイシー、リキュール」といったニュアンスが求められるのだと、そうアルノー・ブスケは補足する。マダガスカルはバニラの実の主要生産国であるとともにかつてのフランスの植民地でもあった。そのため古くから天然のバニラに親しんできたフランス人の本物志向は強いというわけだ。アロマの調合作業はこうした文化的背景の織りこまれた消費者たちの期待と現実的な製品の着地点とをすり合わせて行われるものである。そのアロマの持つ特性を強調するためには、天然の抽出物に他の天然または合成の成分を加える必要がある。ここで重要となってくるのが、アロマティシャンとしての高い専門性だ。その専門性をもって彼らは風味の傾向に修正を加え、任意の味覚的特徴を増強してみせる。だがこれは本当に深く微細な知識を要することで、それがなければ食品の発する匂い分子を再現することはできないだろう。
アロマの起源
現代のアロマが誕生したのは1970年代から80年代に発達した化学成分の分析技術、特にガスクロマトグラフィー技術によるところが大きい。溶液中に存在するひとつひとつの分子を識別し、食品における匂い成分とアロマの構成をほぼ完全に特定することのできる技術である。付随して、「ヘッドスペース分析」と呼ばれる技術も登場した。こちらは空気中の揮発性成分をとらえて保存する技術である。この揮発性成分をクロマトグラフィーで分析することにより、記録された匂いを正確に再現することができるというわけだ。
通常、木に実をつける果実の匂いは収穫時における酵素作用によって変質が生じるわけだが、このセンサーを備えたガラス球の登場以降、収穫前の匂いを把握することが可能になった。具体的には熟した果汁たっぷりの桃の匂いを「撮影」し、この匂いをアロマの中心要素として再生産することができるようになったのだ。したがって先ほどのイチゴヨーグルトの例とは異なり、このヨーグルトには見た目用の果肉のかけらに加えて、まだ木についている段階の果実の香りを忠実に再現したアロマが付加されることになる。
自然であることとは何か 錯覚から再現へ
それで消費者たちが満足するかはどうかは定かではない。私たちは市場に流通している商品に慣れ親しむあまりそれが自然だとすっかり信じこんでしまっているが、必ずしもその商品が自然抽出物由来だとは限らない。アロマティシャンは合成成分を用いた果実の香りの再現にすぐれて熟練している。アロマの「自然らしさ」とは何より人工的なものであり、精緻な調合作業によってもたらされるものなのである。そしてそれにはふたつの要因が深く関わっている。ひとつは、天然抽出物による再現性が低いということ。これには天然原料が脆弱で、抽出方法によってはその原料が損なわれてしまうことが関係している。そしてもうひとつは、これら天然原料の収率の低さである。「必ずしも『沈黙の果実』というわけではありませんが(香水の世界では匂いを抽出できない花を『沈黙の花』と呼ぶ)、高価ゆえコストがかかります」とアルノー・ブスケ。「ですがそうした事情も、2000年代からじょじょに変わってきました」。消費者たちから寄せられる自然らしさへの要求と欧州における厳しい規制に対応するために抽出方法が改良され、天然成分の性能が向上したのである。ゆえに今日では自然であると「見せかける」のではなく「実際にそうである」こと、それを強調しあらゆる場所に明記することが求められている。ブラインドテストでは必ずしも天然抽出物が高い評価を受けるわけではないものの、「自然」と明記されたサンプルには一貫して好意的に受け止められ評価されていることが、心理学者レイチェル・S・ハーズの研究によって明らかにされている(「嗅覚への言語コンテクストの作用」『一般心理学ジャーナル』2003年号)。この業界には魔法の言葉めいたものはほとんどないが、「自然」だけは数少ない例外のひとつである。