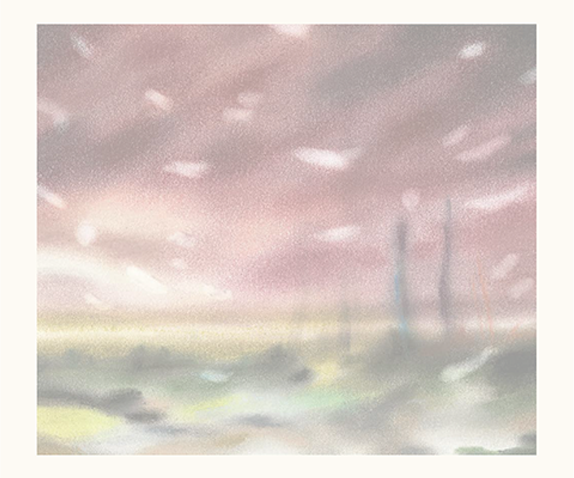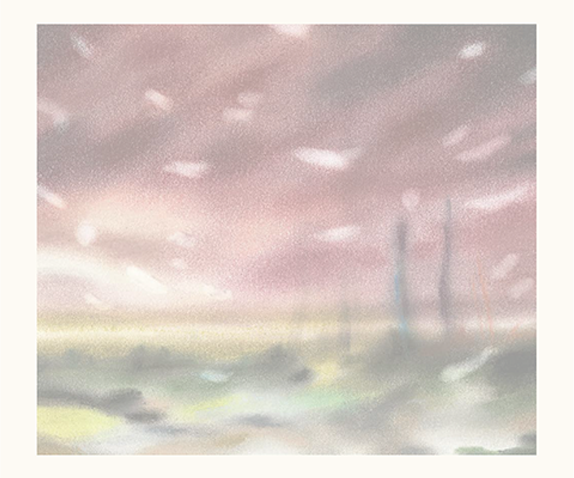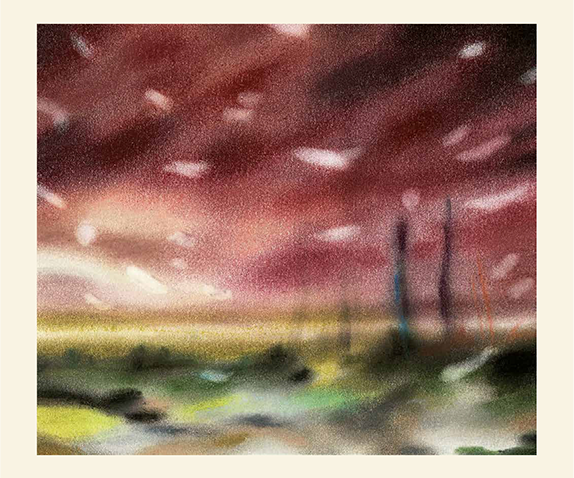ホモ・サピエンスにとって嗅覚とは、種の保存のためには欠かすことのできない鍵となる機能のひとつであった。暗闇や木立の影に隠れている捕食者の存在を知らせることで危機を回避させ、食物のありかを示しその場所へ導くことで旧石器時代における狩猟採集民族の食生活を守ってきた。そのような重要な役割を嗅覚が担う一方で、戦争の起源は人々が定住化へと移行し守るべき土地や所有物への執着が生まれ始めた8000年から10000年前にさかのぼると言われている。これまでは他の生物が発する臭気からその動物を攻撃すべきか逃げるべきかの判断をする必要に迫られていた状況は、そっくりそのまま他の人間が発する匂いから友好的か敵対的かを判断する必要性へと移行した。
したがってこの戦争という現象に関わる匂いのなかで、最も多く氾濫しなおかつ謎めいているのは敵の匂いであると言えよう。どのような紛争においても、人々はその敵対勢力が持っているであろう嗅覚的特徴に想像と幻想を膨らませるものである。十九世紀末から二十世紀初頭におけるフランス人にとってはドイツ人たちの匂いがそれにあたり、かなり激しく、暴力的過ぎると言わざるを得ない言説が飛び交っていた。代表的なのは『ドイツ人種における耐えがたき臭汗症』(1915年出版)の著者として知られるドクトル・ベリヨンで、同医師はドイツ人たちが不快な匂いをまき散らしていると糾弾し、その原因がフランス人と比べ4分の1以上は高いと見られる彼らの「尿毒係数」にあるとした。「現代ドイツ人の主な生体的特徴は、腎機能を酷使しすぎたせいで尿酸成分の排泄をじゅうぶんに行うことができず、その不足を足の裏で補っているという点である。この見解を端的に言い直すとすれば、彼らは足から排尿している、ということに他ならない」。ベリヨン医師はあくまでも医学的な文体で自説を詳述しており、これはアニク・ルゲレー『匂いの魔力』(オディール・ジャコブ出版、2002年刊)にも引用されている。 上記のように敵と悪臭は不可分のものであるとそう人は信じこんでしまうらしいが、まさにこの匂いを検知することによって敵方の位置を特定する軍事装置が開発されたという例もあるようだ。ベトナム戦争における匂いの問題について論じた研究(『危機の匂い ベトナム戦争の記憶を探る』)のなかで、『Nez』シリーズ執筆陣のひとりであるエレオノール・ド・ボヌヴァルは1965年よりアメリカがジェネラル・エレクトリック社に依頼し開発に着手した装置を紹介している。そしてその装置は、北ベトナム軍兵士やベトコンの体から出る汗や排尿、あるいは彼らが調理用に起こしたたき火の匂いなどを探知することを目的としたものだった。当然と言えば当然かもしれないが、「ピープル・スニファーズ(人間探知機)」なるその装置を運用するにあたっての最大の困難は、敵よりも装置の使用者ばかりを検知してしまうことであった。またそのような作戦とは裏腹に、逆に装置を使うアメリカ兵たちのほうがその体から漂う独特なチーズっぽい匂いによって所在が筒抜けになり、敵方に狙い撃ちされてしまうという窮地に陥ったということも同著者は報告している。この匂いはバターを始めとした乳製品を多く取るその食生活に起因するものとされており、アジアの人々にとっては西洋人に特有の匂いとして言及されることも多い。
このベトナム戦争に限らず、日常生活と同じ頻度の入浴が困難な状況とあっては、味方兵の匂いもまた耐えがたいものとして感じられるだろうということは想像するにかたくない。アンリ・バルビュス『砲火』(1916年出版)のなかで、その匂いはまさにひとりの歩兵を眠りから引き剥がすほどのものとして描かれている。「こんちくしょう! やつらの足が俺の顔のすぐ近くにあるもんだから、すっかり目が覚めちまったよ。それぐらい気分の悪くなる匂いだよ」。特に新兵にとっては、こうした経験によって見させられる景色はまさに恐怖の対象でしかないだろう。別の登場人物は、仲間たちが夜納屋で休むため靴を脱ぐ様子をぼんやりと目にしている。次の瞬間起こるであろう窒息の予感に恐れをなした彼がそこでとっさに取った行動とは、オーデコロンをしみこませたハンカチを自らの鼻先に押し当てることであった。そしてその香りに包まれながら、彼は嗅覚的な恩寵を見出すのであった。ミカエル・ランドルト、フランク・レジャン著『東部戦線異状あり 第一次大戦期におけるアルザス・ロレーヌ地方の考古学』(ストラスブール美術館出版局、2013年刊)のなかでも取り上げられているように、実際かつての前線で発見される遺物のなかにはオーデコロンの瓶が見つかることも多いという。
したがってこうした戦時下という状況においては、入浴や床屋での散髪、そして至高の贅沢品である香水といったものは、戦争という極限状態からの一時的な逃走線としての役割を果たしていた。まさにそうしたものの恩恵にあずかるときのみ、兵士たちは束の間、かつての平和だった市民生活へと帰り、幸福をかみしめることができるのだ。モーリス・ジュヌヴォワ『14年の人々』からも引いてみよう。以下は作家自身の1915年2月の経験をもとに書かれている。「そして私は今、ヴェルダンにいる。温かな風呂のなかに深くこの身を沈め、足の指を開いている。[...]彼もマゼル通りの床屋に行くようだ。髪も切る、ひげも剃る、洗髪もする、そして仕上げはマッサージだ。フジェール・ロワイヤルをたっぷりつけて、頭皮をマッサージしてもらうのだ!」。
獲物にして捕食者
血とは何よりも生命を司る液体である。実際に体外に流れ出たときにしかかぐことができないという意味において、血の匂いとは何か普通ではないもの、戦争や死といったものを不可避的に連想させる特異なものであると言えようが、しかし同時にごく幼い子どもですらそれがどんな匂いかを知っている、そんな普遍的なものでもある。誰かを傷つけ血を流させること。それは視覚的にも嗅覚的にも最も言い逃れできない方法で、「汝殺すなかれ」という、人間にとっての最大の禁忌を侵犯することを意味する。それは死に最も接近することであり、死に触れること、逃げ去る命をその鉄のような匂いのなかに感じることである。そして同時に命を奪う側もまた生きているのだということ、何よりも両者の立場は逆転し得るのだということを否応なしに意識させる。オリヴィエ・R・P・ダヴィッドによる血の匂いの分析は『Nez#2』で読むことができる。どこかで血が流されるとき、血液中に含まれるエポキシデセナールという分子が捕食動物の食欲をそそる。逆に餌食となる動物たちにとってはその分子の匂いは危機がすぐそこまで迫っていることを知らせる信号となり、その危機をやり過ごすために動物たちにその場に倒れ死んだふりをするよう促すのである。狩る側にも狩られる側にも回る可能性のある人間にとってはこの匂いは本能的に耐えがたいものであり、その匂いを認めるやいなや、即座にその場から立ち去り逃亡するよう生存本能によって命じられる。「その洞窟が血の匂いに満ちているのを認め、私は慌ててそこから飛び出した」と、アルフレッド・ド・ヴィニー『軍隊の服従と偉大』(1835年)の主人公ルノーもそう語っている。ナポレオン軍の大尉であるルノーはその後銃剣を手に200人の兵を率い、ロシア軍に占拠されたランス近郊の農場を奪還した。
一方テクノロジーが進化した現代の戦争においては、この血という、有機物が生きた後その場で死んだことを示す痕跡は、戦闘員から意図して覆い隠される傾向にあるようだ。ヘリコプターに機銃掃射された戦闘員の死は、もはや肉眼ではなくサーマルカメラ越しに「飛び散る無数の熱反応の点々が映るというひとつのイメージとして」確認されるにすぎない。そう『戦火の下』(タランディエ出版、2014年刊)に記したのは元フランス軍士官の歴史家、ミシェル・ゴヤだ。またゲリラ作戦では爆発物を遠隔で作動させることも多いため、やはり直接血が流れる現場に遭遇することは少なくなった。そのような意味では血の匂いというのは、もはや敵からではなく自身あるいは味方から漂ってくることのほうが多いのかもしれない。
白兵戦の衰退から化学兵器の登場まで
戦争の匂いの歴史とは、使用される兵器の歴史と言い換えてもさしつかえないはずだ。ミシェル・ゴヤによれば二十世紀以降の戦争では白兵戦による死傷者の数は全体の1%にも満たない。それでは剣やナイフによって流される血の匂いはいったい何に取って代わられたのだろうか。火器と火薬の匂いである。アンリ・バルビュスはやはり『砲火』において、第一次世界大戦下の戦場を飛び交う砲弾を「凶暴な猛獣のようだ」と表現したうえで次のように記している。「その猛獣は硫黄の匂いに包まれていた。それは黒色火薬の匂いであった。他にも焼け焦げた布の匂いや燃える土の匂いをまき散らしながら、それは野原全体をたちまちのうちに覆い尽くした」。そしてクロード・シモンが1940年6月の敗走について詳述した『フランドルへの道』(1960年)においては、その兵器の匂いについて「あの思わず吐き気を催させるむせ返るような硫黄と焼けた油の匂い。火にかけられたまま忘れられ放置されたフライパンのようにパチパチと音をたてながら煙をあげる、黒いオイルまみれになった砲身から漂う、脂身の焦げたような悪臭、そこへ石膏と埃も入り混じったようなひどい匂い」と、そう語り手に描写させている。
戦車の匂いに関してはフランス最初期の戦車兵のひとりであったシャルル=モーリス・シュニュによる描写が自身の著書『戦争捕虜のトトシュ』(1919年)のなかに見られる(なお同じ箇所をミシェル・ゴヤも前掲書に引用している)。「戦車は激しい砲撃を行ったせいで煙にまみれ、煤だらけになっていた。[...]充満したガソリンと埃の匂いは鼻を突き刺すかのようで、そのきつさときたらそのまま喉が詰まり窒息してしまうのではないかと思わせるほどだった……」。ここではガスの充満についての言及が認められるが、それによりさらに恐ろしい結果が引き起こされる場合もある。1918年6月に初出撃をかざったフランス軍ルノー・FT17戦車が、出撃した121両中、実に35両がその充満したガスに引火し、爆発炎上してしまったのである。これについてはミシェル・ゴヤが次のように補足している。「たとえ機体の爆発までは免れていたとしても、きっと次に搭乗する戦闘員は金属製の機体にしみついた、前任者の残した焼けこげた匂いを否応なく吸いこむはめになっただろう」。
また、第一次大戦はこれまで存在しなかったまったく新しい兵器が登場し始めた戦争でもあった。最初の化学兵器として知られる塩素ガスは、窒息、吐き気、体調不良を引き起こし、漂白剤のような匂いを持つ緑がかった雲の出現によってその使用が確認された。その塩素ガスの初の大規模実戦投入は1915年4月22日、イーペルにほど近い地域でドイツ軍によって実行され、わずか45分のあいだに死者5,000人と15,000人の中毒者を出したということが陸軍博物館によって報告されている。ガスマスクの着用によって有毒物質が体内に侵入するのをおおむね防ぐことはできたようだが、それでもその脅威は桁外れのものだった。新たなガス兵器が現れたのはわずか2年後の1917年のことだった。使用者はまたもドイツ軍で、そのガスはわずかにマスタードに似た匂いを持っていた。ここでもやはりイーペルの地が舞台として選ばれ、「イペリット」と名づけられたその兵器名はまさにこの地名にちなんでいる。高い残留性および浸透性ゆえ消散しにくく、衣服に染みこみやすい、水で洗い流しにくい、ガスを吸いこんだ肺だけではなく触れた皮膚にも深刻な火傷を与える、などといった特徴が見られた。
この兵器の持つ真に破壊的な効果とは上記のような直接的被害でも深刻な後遺症でもなく、それは人々の内に抑えきれない恐怖や不安を植えつけることだったとは言えないだろうか。「すっかり怖気づいたブフィウはすみっこで縮こまっていた。決してガスマスクを手放そうとせず、風に乗ってわれわれのもとまで運ばれてくる火薬の匂いひとつにさえ恐れをなしているようだった。もう1時間ほど前から彼は『リンゴの匂いがする……マスタードの匂いがする……ニンニクの匂いがする……』などと口ごもりながら、そのたびにおびえた様子でフードをかぶり直すのだった」とそう語ったのは『木の十字架』(1919年)のロラン・ドルジュレスだった。そして1925年、ジュネーヴ議定書によりこの種の兵器の使用は禁止されるにいたったのであった。
熟練兵は感覚に耳をすませる
第一次大戦を戦った兵士たちに求められていたのは、自身の感覚を研ぎすますことであった。特に自らの嗅覚を信じること。鼻先に届く匂いから読み取れるサインを的確に理解し、爆撃の危機が迫っていることや、爆弾までの距離、弾薬の種類などを知ること。そして何よりも匂いというものがそのような情報に満ちた有益な指標であると心得ること。そのことはたとえ時代や状況はちがえど、はるか昔の旧石器時代の人類にとっても言えることだった。兵士たちにとってこのように音や匂いを読み解くすべを学ぶことは、敵地での過酷な環境に適応することや自身の生存率を上げることに直結した。第一次大戦におけるフランス軍の死傷者の約半数が、まさにその始めの1年間によるものであったということにミシェル・ゴヤは注意をうながしている。だがその1年を無事生き抜き、そこから1918年まで戦い抜いた兵士であれば、自身の感覚に耳をすませることにかけてはもはや熟練の域に達していると言えた。「そして今、彼らは膨大な経験に裏づけられた鋭敏な本能を身につけていた。彼らはまさに、戦場のスペシャリストであった」と、そのように述懐するのは自身も第一次大戦に従軍していた作家・ジャーナリストのヴェルナー・ボイメルブルクだ。引用はその著書『ひとりのドイツ人が語る第一次大戦』からで(やはりミシェル・ゴヤの本のなかにもその引用がある)、彼は次のように続けている。「まるで彼らは戦場に関するすべてを知っているかのようであった。その耳はあらゆる音を本能的に聞き分け、そしてその鼻は、塩素、ガス、火薬、死体の匂いを検知するばかりか、それらを区別する微妙なニュアンスの差さえも完璧に把握しているのであった」。
それぞれの戦場で異なるのは装備や地形といった物質的要素ばかりではなく、その場を漂う匂いにもそれぞれ独自の特徴が現れてくる。特筆すべきなのは1954年の、ディエンビエンフーの戦いにおけるそれであろう。第一次インドシナ戦争最大の激戦と呼ばれたこの戦いは、予想よりも早々に激化してしまったため負傷兵を戦場から脱出させることができないという普通では考えられない状況に見舞われたのだった。フランス軍史上類を見ない事態であり、第一次世界大戦時において最も過酷だった戦闘でさえこうした惨事に陥ることは考えられなかったという。結果として、戦場には耐えがたいほどの腐臭が漂い始め、それがそっくりそのままディエンビエンフーの異様さを証明する形となった。「ディエンビエンフーは想像していたよりもずっと恐しいものであった。想像していたよりもずっと悲惨であった。巨大で、地味で、栄光に満ち、何よりも汚れていて、ひどく臭かった。想像していたより、ずっと」と、そう述懐するのはピエール・シェンデルフェールだ(ロラン・ロス監督の1986年の映画『焼かれた眼』より)。後に映画監督となるシェンデルフェールは当時は軍付きの映像カメラマンとして従軍していたところ、ベトミン軍に捕えられ捕虜となったのであった。また(ロジェ・ブルージュ著『ディエンビエンフーの人々』に登場する)戦闘中負傷したルイテール中尉も次のように証言している。「傷口が化膿し、自分の体が悪臭を放っているのを感じていた。おまけに赤痢のおかげで下痢続きで、何も飲むことができないというありさまだ。[...]ブリエの体にはギプスのあいだからウジがわいてきていた。傷、下痢、死体というこれら恐るべき三種の悪臭に加え、われわれは戦友の体にわいたそのウジを払ってやらねばならなかった。[...]そこへさらに雨が降り始めると塹壕はほとんど泥沼のような様相を呈し、これ以上不潔な状態になることなんてなるはずあるまいと信じきっていたところに、こうしてさらなる醜悪な環境が現出したのであった。[...]目の前にある死体がひどく臭ってしかたがなかった」。
これらの匂いが耐えがたいものと感じられるのは、それらが死の進行とともに確認される匂いだからであろう。カダベリン、プトレシン、インドール、フェノール、そしてスカトール……。死体の腐乱臭の正体と言われる分子である。存在し得る危機のなかで最も究極的なものと言える死、その結果生じることになる腐敗の匂いは時代や地域を問わぬ普遍的な拒絶反応を引き起こす。
1863年7月初旬、後に南北戦争を決したと激戦と語られることになるゲティスバーグの戦いが始まってから3日目、戦場にはくまなく硝煙と火薬の匂いが立ちこめていたという。「あたりの空気は煙と硫黄の蒸気で重くなり、部隊のほぼ全兵士を窒息させんばかりであった。そんな風に苦しんでいるそばからなおも砲撃が続き、状況はますます悪化した」。そのような証言が戦いから25年後に氏名不詳のニュージャージー州の住人によって語られたという。そしてその後その言葉は歴史家のマーク・M・スミスによって『戦いの匂い、包囲の味 南北戦争の感覚史』(2014年)のなかに記録されたのであった。しかしさらなる惨状が待っていたのはその戦闘が終了してからであった。その火薬の残り香にくわえ、7月という夏の暑さのなか、戦死した兵士の亡骸や動物の死骸、そして動けなくなった22,000人もの負傷者たちから生じる腐敗臭があたりに立ちこめたのである。この強烈な悪臭は当時の人々の証言によると、10月になり寒くなり始めるまで消えることなく残り続けたという。だがこの死体という匂い自体、どうやら状況によってちがう匂いかたをするものらしい。エーリヒ・マリア・レマルクによる小説『愛する時と死する時』(1954年)のなかにそうとうかがわせる記述を見ることができる。小説の冒頭は第二次大戦下のロシア戦線を舞台に展開するのだが、それは次のように始まっている。「ロシアで感じられる死の匂いはアフリカのそれとはちがっていた。アフリカでは[...]砂と太陽と風とが死体を乾燥させ、さっぱりとした清潔な状態に保っていた。だがここロシアではちがう。ロシアの死はねばっこく脂ぎっていて、吐き気を催させた」。
アンリ・バルビュスは戦場を飛び交う砲弾を「猛獣」に例えた。その猛獣は「硫黄の匂いを身にまとい、焼けこげた布と燃える大地の匂いを発散させていた」
匂いはいたるところに、あらゆる形で
戦争の匂いにはさまざまなものがあり、ただ血という例外をのぞけばその匂いも条件や状況によってさまざまに変化する、ということを見てきたわけだが、本来戦争とは結びつけられることのない日常生活の匂いが戦争の匂いへと変ずる場合もある。当然のことながら、戦闘の舞台となる場所には戦争という文脈からは切り離されたその土地本来の匂いがあるものである。それは平凡でありふれた匂いであるはずだが、しかし前線で戦う兵士たちにとってはその匂いは戦争の匂いと混同され、戦争の匂いの一部をなすものとして知覚されてしまうのである。1970年代始めのベトナム戦争を戦った兵士たちにとっては、炭の匂いがそれにあたった。炭火で作った料理を売る屋台が路上に広がるベトナムでは常にその匂いがともにあった。そして2009年にチャドへ派兵されたA中尉にとっては、それは炭化水素の匂いであった。発電機から出る、いわゆる排気ガスの匂いである。都市部でも村落でもどこへ行っても空気中にこの匂いが感じられたという。匂いはこのように場所や土地に由来する一方で、2020年マリへ派遣された中尉A・Mが語った雨天後の過熱によって蒸したテントの窒息せんばかりのカビ臭さや、無香料の洗剤を使って洗濯するため「無臭」とも言えない一種独特な香りをまとうことになる洗濯物の匂いなど、そのように軍の備品や慣習に由来する匂いもあるのである。そのため兵士たちからしてみれば一見戦闘に関係なさそうな匂いでも、彼らのなかでその匂いが暴力的場面と結びつけられそのふたつが脳のなかでセットとして記憶されてしまうと、後になってその匂いをかいだときPTSDを発症してしまう恐れがある。1970年代後半のクメール・ルージュによる大虐殺を生きのびたカンボジア人たちの多くにとっては、タバコの匂いがそうしたトラウマのトリガーとなる役割を大いに果たしたことだろう。実際、クメール・ルージュにはタバコを吸うものが多くいた。彼らがタバコを吸うのはその煙が虫除けになったからでもあったし、質の良いタバコを入手できるすべを知っていたからでもあった。
なので実際に粛清の脅威にさらされた人々からすればタバコではなくちょっとした普通の煙を前にしただけで非道な残虐行為の記憶がよみがえってきてしまうかもしれないし、自動車などから出る排気ガスの匂いをかいだだけで硫黄臭い匂いをともなう爆撃の記憶がフラッシュバックしてしまうことだってあるかもしれない……と、そのようなことをデヴォン・E・ヒントン、ヴース・ピッチ、ダラ・チーン、マーク・H・ポラックらは論文「クメール難民におけるパニック発作の嗅覚的トリガー」、(ジム・ドロブニク編『ザ・スメル・カルチャー・リーダーズ』2006年刊所収)において指摘したのであった。しかしこれらはごく日常的でありふれたものであるだけに、これらを完全に避けて生きていくのはどう考えても非現実的だ。
テロリズムは古典的な戦争の定義には合致しないが、匂いの特徴としてはおおいに重なるところがある。
新たなる暴力のかたち
ここ20年ほどのあいだに戦争のありかたにも変化が起こりつつある。電子兵器の進化によって一部戦闘の無人化が実現するとともに、それゆえどこか無味乾燥とした、空虚なものとなったのである。装甲車やヘリコプターに搭乗する兵士たちは自陣を発ち、彼らを待ち受ける危機とそれに対応する戦争の匂いに身をさらされることとなる。作戦中ひとりの兵士が嗅覚によって感じた恐怖を同僚の別の兵士がやはり嗅覚によって感じ取り、そのようにして恐怖がじょじょに伝染していくということもあったのかもしれない。まさに太古の昔、まったく同じようにして仲間どうしで感覚と感情が共有されたように。だがこれからの戦争においては、パイロットはヘリではなくドローンを操縦する。実際の戦場からは何千キロと離れた場所にいるパイロットは、ではそこでどんな匂いをかぐと言うのだろうか。イランやアフガニスタンの基地に設置されているドローンの操縦ブースにも、きっとその場所に固有の匂いがあるのだろう。しかしそのブースに詰め、ひとりドローンを操縦するパイロットたちはひょっとしたら、もはや自分が何と戦っているのか分からなくなってしまうことだってあるのではないか。彼らがその戦争を「自分自身との戦争」と錯覚してしまうことだってあるのではないか。そしてそんな彼らがそのような仮想的戦場でかいでいる固有の匂いとは、ブースのなかで敵機を撃墜すべく引き金を引くときに感じる、恐怖とはまた異なる類の奇妙なストレスに反応している自身の体臭なのではないか。そしてその体臭と混じり合う、ブース内の電子機器を構成している錫やプラスチックといった各種部品の匂いなのではないか。そしてこのとき戦争の匂いは、自分自身の匂いと渾然一体のものとなっているのである。
この現代化された戦争のもうひとつの特徴は、暴力の分散化である。つまりこれまで局所的なものだった戦争状態が、その力を分割・細分化させながらじょじょにその範囲を広げ、かつ多方向に散りばめられていく。そしてその力は国境を越えるばかりでなくあろうことか市民社会の内部にまで浸透していくのであった。テロリズムは古典的な戦争の定義とは確かに一致こそせぬものの、その嗅覚的特徴にはおおいに重なる部分がある。2015年11月13日の、あの恐るべきパリ同時多発テロが今も記憶に新しいように、カフェのテラスで、そして劇場で、出し抜けかつ理不尽な形でそれは起こる。ある女性は次のように語っている。彼女はバタクラン劇場で繰り広げられる一方的な虐殺のただなかにいた。「火薬の匂いがつんと鼻のなかに入ってきた。そして次に、血の匂いが。そして次の瞬間には、絶叫する人々がいた。つぎつぎに死んでいく人々。泣き叫ぶ人々が」(ローラ・ナティエ、ドニ・ペシャンスキー、セシル・オシャール著『11月13日』より)。平和と戦争状態の境界が次第に曖昧になりつつあるこの世界において、火薬と血の匂いだけは今なお明白に恐怖の対象として君臨し続けているということが改めて確認される。
第二次世界大戦下においてはレジスタンス活動を行ったかどでブーヘンヴァルド強制収容所に幽閉され、後にインドシナ戦争とアルジェリア戦争に従軍したヘリー・ド・サン・マルクは回想録『燃え尽きた荒野』のなかで次のように記している。「戦争とは[...]汚物、血、涙、汗、尿といったものが寄せ集められて作られた、究極の恐怖のかたちである」と。多くの神話では、地獄は耐えがたい悪臭に満ちた世界であると語られている。古代人たちはそのような地獄のイメージを、ひょっとしたら戦争から着想したのではあるまいか。言い方を変えれば、戦争とはこの世における地獄のアナロジーに他ならないということだ。