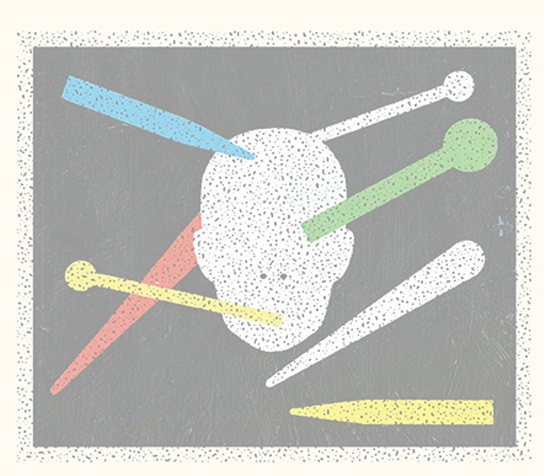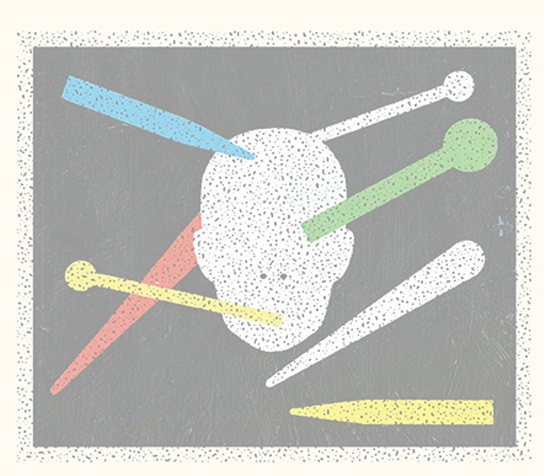そもそものところ、現代で言う「調香師」という職業はいったいどこからやって来たというのだろうか?その起源を問うことは、この「香りを作る者」という職能の正確な定義や、彼らに対し社会的に割り当てられた役割および存在意義を改めて検討し直すことにつながるであろう。むろん今日においての調香師の仕事とは香料を組み合わせ、ときに市場からの要請に応じながら、十全に思考され推敲された香水を完成させることを指すものとされるわけだが、その源流をたどっていけば、やがて古くは魔術師やシャーマンといった存在にまで行き着くと考えられている。
芳香物質の使用は早くも先史時代から確認されていた。とはいえその目的は精霊崇拝や狩猟に関するものであったとされ、このことからも当時の「調香師=香りを作り扱う者」の役割が、物質と非物質の境界に立つ存在として、目に見えるものと見えないもの、すなわち神と人間とのあいだを取り持ちつなぐ「対話者」にあったということがうかがえよう。
大きな転換をもたらしたのは香水の歴史のなかでも特に際立った2つの技術的革新だった。まずひとつめとしては、中世末期のヨーロッパで実現した蒸留技術の確立が挙げられるだろう。これによってアルコールを基材とした香水の製造が可能になり、天然原料の新たな処理法が生まれた。もうひとつは十九世紀における、香料を人工的に合成する合成香料の誕生だ。これによって調合技術に変化がもたらされたばかりでなく業界そのものが大きく再編された。こうした技術革新にとどまらず二十世紀には消費社会の到来により市場は急速に拡大し、それとともに従来は複数の異なる業務を兼任していた調香師の分業化が進み、最終的には、今日知られているように創造的役割だけが彼らに残されることになったのである。そしてそこへついに、人工知能が現れた。
聖なるものとしての香り
古代エジプトにおいて香りを調合していたのは宗教的儀式を行う司祭であった。香りは神殿内で作られ、神聖な秘儀において使用された。なかでもよく知られているのは「キフィ(kyphi)」であろう。「火のなかにくべて焚くための香料」を意味するこの香りには病いを癒す力もあるとされ、紀元前2000年代の医療行為の記された古いパピルスからはこのキフィが治療薬としても用いられていたことが確認されている。
したがってこうした香料を作る司祭=調香師たちの役割には、神々に祈りを届けその加護を受けることを保証する奇跡の物質を作るという、宗教的・魔術的側面があったと言えるだろう。またその魔法の香りが人々を病いから守るものでもあったという点においては、予防的・医療的側面も認められよう。なお香りの組成に関しては誰が作ってもそこまで大きな差異はなかったとされる。これには香りの配合に関してもそれを使って行われる儀式に関しても、正確かつ忠実な再現性が重視されていたということが関係している。
一方古代ギリシャ・ローマにおいては上記のごとき調香師の宗教的性格は薄れ、その存在ははるかに世俗的なものとなっていった。エジプトと同じくオリーブオイルやアーモンドオイルといった油脂が香料の基材として重要であったという点は変わらなかったものの、この時代において香料を作る設備としてなくてはならなかったものはオリーブオイルをしぼる圧搾機であった。古代史の研究者たちはこの発見から当時の調香師たちの作業場がその圧搾機とともにあったということを特定することができた。扇形に広げ鼻先を近づけるあの何本ものムエット、それが今日における調香師たちにとっての象徴的アイテムだとするならば、その時代の調香師たちのそれは圧搾機にくさびを打ちつける無骨なハンマーであった。当時の調香師たちは芸術家というよりははるかに職人的であった。彼らは香料の基材をもとに調合を行い、期待された香りを忠実に再現するよう求められた。ゆえにそこに個人の創造性が入りこむ余地はほとんどなかったのである。
職人、技術者としての調香師
調香師の役割に大きな変化が訪れたのは中世末期からそれに続くルネサンス期にかけてであった。十二世紀に始まる蒸留技術の進歩は先述した通りだが、以降盛んに蒸留されるようになったのは植物であった。特にバラ水は香水だけでなく化粧品や薬品にも使用された。そして十三世紀末に冷水によって常時冷却可能な蛇菅型の蒸留装置が発明されると、発酵飲料からエタノールを蒸留抽出できるようになったことによって、ここに現代へと通ずるアルコール基材香水への道が開かれることになる。とはいえルネサンス期から古典時代にかけての香水製造の指南書にはまだまだ化学的知識のなかに錬金術的なそれも多く混じっている、そんな時代であった。また当時は手袋職人が香水製造業者を兼ねていた時代でもあり、この職業はギルド制度によって厳格にシステム化されていた。正規の職人(マスター)としての地位を得るためには4人のマスターと監視人の立ち合いのもと、5つの香りつきの革手袋をそれぞれ異なる動物の皮で作り、傑作として評価を得る必要があった。
続くアンシャン・レジーム期にもこの手袋職人=香水師は、依然としてひとりの職人の地位にとどまっていた。ところが当時記録されていた配合記録をひもとくと、(例えば「ハンガリー王妃の水」や「アンジュの水」などといった)規定のレシピを遵守しあるべき香りの「型」を再現する以外にも、このころあたりからじょじょに、各職人ごとに異なる製造プロセスの工夫や革新への野心が際立つようになり、そのような独創的な創意工夫が試みられるようになっていったということが分かってくる。原材料の加工から商品の販売までを一手にこなしていた当時の香水業者にはどうしても「実務の人」という印象が否めなかったものの、このころからそうした「専門的知識を持った者」というイメージも生まれてくる。
芸術と科学の統合を果たした調香師という存在は、まさしく現代の錬金術師であった。
香料レパートリーの拡大
そのような専門的知識人としての調香師のイメージは十九世紀前半にはすでに確固としたものになりつつあった。女性誌やモード誌では調香師のことを語る際には決まって「化学者」という形容が用いられたし、『ルプチ・メサジェ・デモード』誌が調香師ルグランを「偉大な化学者」として賞賛すれば、『ル・ボンタン』誌は「まるで神がかりのようなゲランの科学」と褒めたたえた。事実、当時の調香師は化学者としての象徴であるラボや研究室を持つ存在であった。香料の選択と組み合わせを駆使し、数々の重要な発見や革新を実現した。また猛毒の白色顔料である鉛白や同じく毒性のある赤色顔料の朱砂による被害を経験していた十九世紀において、彼ら調香師たちは提示された製品の品質を保証する責任ある立場にあったとも言えた。その十九世紀の終わりには香水製造にとっての新たな転換点が訪れた。新たな天然原料の発見、溶媒抽出法、そして何よりも合成分子(クマリン、ヘリオトロピン、バニリン、合成ムスク、イオノンなど)の登場によって、香料パレットは史上類を見ないほどの飛躍的な拡大を見せたのであった。この合成香料は商業的、産業的に有利なばかりでなく、香水に新たな可能性をもたらす非常に大きな潜在的力を秘めていた。そのことはシャネル「No.5」(1921年)の生みの親であるエルネスト・ボーが「ある調香師の回想」(『香水産業』1946年刊、所収)のなかで雄弁に語っている。これまでにはなかったまったく新しい創造の可能性をもたらした合成香料によって香水業界に近代化の時代が到来したことを強調しつつ、ボーは次のように記している。「1898年、そのころの調香師の技術と言えば、ただただ限られた数の材料を使って作ったり混ぜ合わせたりすることばかりに終始していたように思う。[...]ところが1900年になると、われわれは香水が突如として凡庸さから脱するのを目にすることになった。それがサリチル酸アミルを使用した、ピヴェ『トレフル・アンカルナ』の登場であった」。その合成香料を世界に先駆け初めて使用した「フジェール・ロワイヤル」(1882年)の後に、ジャック・ゲランの「ジッキー」(1889年)がすぐさま続いた。この時点で香水はもはやひとつの芸術として見なされるようになっており、それにくわえてブランド各社が取り組むイメージ面へのアプローチによって、人々のなかに眠る香水への興味はよりいっそうかきたてられることになった。またウビガンにとってのポール・パルケやピヴェにとってのルイ・アルマンジャのように、香水の制作がブランドには所属しない外部の調香師に依頼される傾向が強まっていったのもこのころからだった。とはいえエルネスト・ボーとガブリエル・シャネルという対比からも明らかなように、香水を作った調香師自身の名はその起用を決定したデザイナーのカリスマ性の影に隠れがちであった。ジャンヌ・ランバンが起用したマダム・ゼッドとアンドレ・フレイエ、そしてジャン・パトゥが香水制作を依頼したアンリ・アルメラスとの関係にも同様のことが言えた。
調香師をひとりの芸術家として描くというイメージ戦略を取ることで、ブランドの持つ市場価値を飛躍的に高めることができると、そうマーケティングは判断した。大衆化が進む香水市場においてあえて「芸術作品」のような高級品を売り出すという差別化を図ることで、その商品を他には存在しない、つまり他とは比較できないものとして昇華させることが可能になったのであった。
いっぽうで、このようなロジックはひとつの否定し得ない現実を浮き彫りにすることになった。創造の可能性が広がったことによって取れる選択肢や組み合わせも加速度的に増加したことで、調香師たちはこれまでとは異なる新たな才能を磨く必要にせまられることになったのである。合成香料を扱い制御するには特別な知識と経験を要し、長い時間をかけてその特性を理解し、さまざまな可能性を探ったうえで最適な形で調香に取り入れる必要があった。つまりそれ以降、調香師たちは名ばかりではなく本当に芸術家にならなければならなくなったのだ。
二十世紀始めごろまでは化学者としてのイメージが強かった調香師だが、やがて人々の集合的イメージのなかでその姿は、芸術と科学とを統合し合成する「現代の錬金術師」へと変わっていく。そしてわれらが錬金術師は鉛から黄金ではなく、エレガントな香りを錬成するのであった。
近年特に盛んになっている持続可能な開発というスローガンの後押しによって、調香師に対しても環境への負荷を最小限に抑えた製品を作るよう求められるといった傾向が強まりつつある。
役割の分散化
同じく二十世紀始めごろ、合成による新たな香料の生産が活発化するいっぽうで、浮上してくる問題もあった。こうした合成分子には単独では扱いづらいものが多く、またそれを扱い制御する側のノウハウにもまだまだ手探りで荒削りな部分があったがゆえ、使用難度が高かったのだ。この問題を解決するべく尽力し、相性の良い合成分子や天然香料を複数種ブレンドし調香に取り入れやすくした調合香料「ベース」の開発にごく初期から取り組んだのが、ド・レール製造所のマリー=テレーズ・ド・レールやジボダンのマリウス・ラブールらといった先駆者的調香師たちであった。
また同じころ、ポール・ポワレに続きガブリエル・シャネル、さらにジャンヌ・ランバンやジャン・パトゥなど、被服だけには飽き足らず活動を多様化させるパリのファッションデザイナーたちがこぞって香水事業へも参画し始めるなかで、それまで調香師向けに香水用原料を卸していた供給会社のなかから、素材の調達だけではなく香水の調合までをワンパッケージで請け負う企業が現れ始めた。これこそが今日における調合会社の誕生に他ならないわけだが、この流れは上記のような各ファッションブランドから寄せられるニーズが次第に増加していったという当時の時代背景を反映するものでもあった。第二次大戦後になるとこの組織形態が広まり、調合会社に所属し勤務しながら開発に従事するというのが調香師にとっての一般的な活動モデルとなった。フィルメニッヒ、ジボダン、インターナショナル・フレイバーズ・アンド・フレグランシズ(IFF)、ルール=ベルトラン・フィス、ジュスタン・デュポンなどが主な調合会社として知られている。こうした企業勤めが主流となるなかで、エドモン・ルドニツカは1946年にド・レール製造所を辞し、妻のテレーズとともにアール・エ・パルファンという小さな会社を南仏カブリに立ち上げた。1949年のことだった。そして以降エドモン・ルドニツカは独立した調香師として独自の創作活動を展開し、その独創的な嗅覚美学を数々の著作を通して、明確に言語化したうえで提示した。この点においてはまさにルドニツカは極めて例外的な存在であったと言えた。大手調合会社が業界を牽引するこの構造は二十世紀全体を通してますます巨大化し、それとともに調香師たちが担っていた業務の細分化が起こった。細分化されたそれぞれの業務にはその業務だけを行う固有の職種が新たに設けられ、結果としてもといた調香師たちにはただ創造するというミッションだけが残されたのであった。もっとも規模の大きな企業ではこれに先駆け十九世紀の時点でもうすでに、事業が成長するにつれ販売や商業開発といった業務は独立した別の部門に明け渡される傾向にあった。これにくわえ配合の計量などといった作業は調香助手が受け持つこともあった。1950年代に入るとアメリカの調合会社ではマーケティングが独立した部門として機能するようになり、市場調査から顧客へのプレゼンテーションまで幅広く担当した。
1970年代初頭、ここで再び大きな転換点が訪れる。「エバリュエーター(評価者)」という新たな職種の登場である。調合会社大手のIFFで初めて誕生したこの職業は、その初期においては調香師の試作品を評価・管理することを主な業務としていたが、やがてクライアントであるブランドや消費者たちのニーズに応えられるよう調香師たちの創作の方向性を導く、ということにまで手を染めるようになる。IFFフランス支社にてこの職を最初期に担当していたエリザベート・マチュー=マドレーヌは、自分たちに唯一残された領分であるはずの創造まで他部門から指図され、当時から影の存在として職務に従事していた古参の調香師たちとしては決して快くは思ってはいなかっただろうと、そうペル・フムム財団企画のワークショップ「エリタージュ(s)」のなかで述懐している。むろん、この職種の名称や業務内容は各調合会社によって異なった。ジボダンのオリヴィエ・ファーブルについた肩書きの名は「クリエイティブ・フレグランス・ディレクター」であった。2018年までこれを務めたファーブルは、他社を含め、この職業がいかなる変遷をたどってきたのかをその目で見てきた。例えばIFFでは「オダー・エバリュエーション・ボード(OEB)」という評定会議が定期的に開かれ、そこにはエバリュエーターだけでなく技術者、販売担当、マネージャーといったさまざまな部門・役職の関係者たちが集まり、顧客に提案する香りの評価・選定を協議した。一方ジボダンには「フレグランス・リコメンデーション・センター」という部門が存在し、香料コレクション内にある各香りの評価、管理、分類を行うとともに、新たなノートが開発される際のマネージメントも行なった。またフィルメニッヒにおいてはエバリュエーターの仕事はマーケターのそれと重なる部分もあった。調香師の役割が細分化され専門分化していったのとは対照的に、このエバリュエーターの業務内容は複数の業務を包含しながら次第に複雑化していき、フィルメニッヒにおける「フレグランス・デベロップメント・マネージャー(FDM)」やジボダンの「クリエイティブ・フレグランス・マネージャー(CFM)」、あるいはIFFの「セント・デザイン・マネージャー(SDM)」といったように、調香師たちを率いる開発のプロジェクト・マネージャーやチームリーダーといった役割をも担うようになっていったのだった。
なおも進む分業化
二十世紀末はとにかくあらゆる種類の規制によって際立っていた、そんな時代であった。それらは種の保存、環境保護、あるいは消費者の安全を配慮して実施されたものであったが、そうして調香師たちの香料パレットに対し使用の中止を求める制限が相当数かけられたことによって、その調香師たちが担う香水の制作ばかりでなく、調合会社各社における創造・開発システムそのものに対しても甚大な影響がもたらされたのだった。
「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」すなわち「ワシントン条約」(CITES)が採択されたのは1973年のことだった。これによってムスクの供給源である麝香鹿が保護種に指定された。そして同年、国際香料協会(IFRA)が発足すると、消費者への安全に配慮した危険性のない香料の選定および使用法を香水業界全体に推奨・勧告するようになった。こうした規制機関や規制法の登場によって、調香師たちはそれまであって当然のものだと信じこんできた原料や成分を突如として使用できなくなってしまった。そのなかには香水の構成において重要で不可欠なものも多く含まれていたため、調香師たちはその大きすぎる欠落を補うためによりいっそう卓越した技量と知識を示さねばならなくなるという状況に見舞われたのであった。またすでに市場に出回っている香料に関しても規格に適合しているかを定期的にチェックする必要に迫られたため、その作業を専門に行うチームを組織しなければならなくなるという厄介さもあった。こうした実際課される規制や制限にくわえて、近年特に盛んに議論されている持続可能な開発や気候変動への対応といった研究トピックの後押しによって、調香師に対しても環境への負荷を最小限に抑えた製品を作るよう求められるといった傾向が強まりつつある。その依頼元であるブランド各社からのリクエストも年々要求度の高いものとなってきている。こんな風に着色してほしい、品質劣化しにくいものにしてほしい、アルコール以外の基材は使えないのか、などなど要求は多岐にわたるが、なかには、香りをカプセル化してほしい、などといった特殊なノウハウの導入を前提としなければならないものもある。こうなるともはや調香師ひとりの手には余る次元の話になってしまうので、そのようなとき調香師は会社内にある各専門チームからの支援を受けながら配合を構成することになる。そうして調香師が完成させた香りの成分や基材がちゃんと現行の規制に適合しているのか、などといった小難しい技術的問題の調整はそれを専門とする部門に委譲され一任されることが多く、特に大手調合会社ではその傾向が顕著である。
AIに魂の作品は作れるのか
「優れた調香師であれば、処方を書き記すべく紙を取ったその時点で、自分が作り出そうとしているその香りがどのようなものになるかがはっきりと理解できているはずである」。1946年にルール香水学校を設立した調香師ジャン・カールによる言である。ここでジャン・カールが的確に要約しているように、自らの創造的プロセスを知的に構築し、そして自らの抱く感情的な思いを香水という形式へと見事に昇華させることができる、まさにそのような能力を有していることこそが現代における調香師の定義と言えるのではないだろうか。しかしながら人工知能の登場によって、何かを創造するという営為それ自体が問い直されるとともに、そのような創造性が専門的知識を備えた卓越した人間の知性にではなく、あろうことか機械に委ねられる可能性が出てきたということもまた否定できない事実ではあるまいか。この人工知能の歴史は意外にも古く、1953年には早くも情報工学の祖アラン・チューリングと最初期のプログラマーであったクリストファー・ストレイチーによって、ラブレターを書くアルゴリズムなるものが作られている。そして自らを「マンチェスター大学のコンピューター(Manchester University Computer)」と自認するそのプログラムは、その頭文字「MUC」を自らの名前として手紙の末尾に署名するのであった。このようにAIに人間的感情を模倣させるという試みはSF的な夢として古くから行われていたことであったが、しかし2020年代に入るとその成果は開発する側である人間の期待と想定すら大きく裏切るほどのものとなり、私たちの予想をはるか上回るその進化は文章ばかりでなく造形芸術や音楽においても、もはやAIが作ったものと人間の手によるそれとではそう簡単に区別をつけられないというところまで来てしまったのであった。ただ香水だけが、この香水というジャンルだけが例外的にこの大きなうねりのなかから逃れ出ることができた……などと言えるはずはもちろんない。だがここで注意しておきたいのは、人間だけに許されていたはずの特権が長い時間をかけながら次第に機械によって奪われ剥奪されていった……たとえそれが装飾芸術を始めとした人間の誇るあらゆる芸術の歴史の内実であったとしても、果たしてピアノの自動演奏がプロのピアニストの演奏に勝っているなどと、そう本気で信じているものが私たちのなかにいるのだろうか?ということなのだ。同じように「ヘッドスペース分析システム」が調香師の仕事を完全に奪い去ったわけではない。少なくとも今現在は……という留保つきでしか語れない問題ではあるのは確かだが、創造する人間にとってAIはあくまでもその創造を手助けしてくれるひとつのツールにとどまるものでしかなく、それを使うか使わないかは人間の自由意志にゆだねられている。3Dプリンターの普及が進むこの現代にあっても、手作業による温かみは何ごとにも代えがたいと、
そう信じる消費者がまだまだ多くいるということもまた事実である。マルセル・デュシャンによる「レディメイド」の例がすでに証明していたように、人の手によって作られた、たとえそれ自体は何の変哲もない品物でも、それが人間の歴史や人の生活という厚みのある文脈のなかに位置づけられたとたんに突如として明白な意味を持ち、その物の持つ不完全さや不恰好に修理された跡、そしてそれが今ここに偶然存在しているという奇妙な生々しさとが相まって、その何てことはない代物が魂のこもった芸術作品の地位にまで押し上げられる、そのような奇跡のような魔法のような例を、私たちはもうさんざん目にしてきたはずではないか。