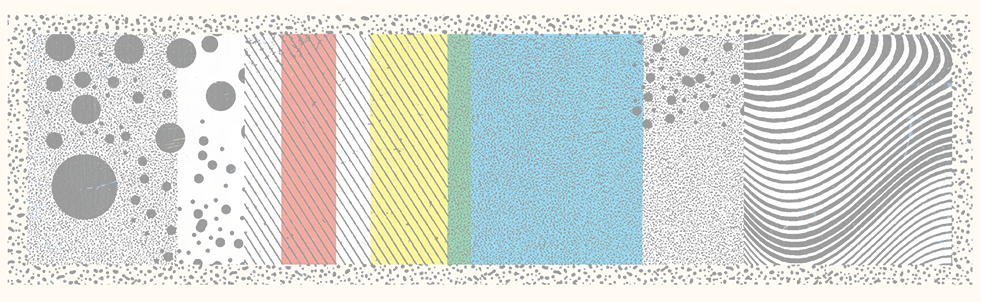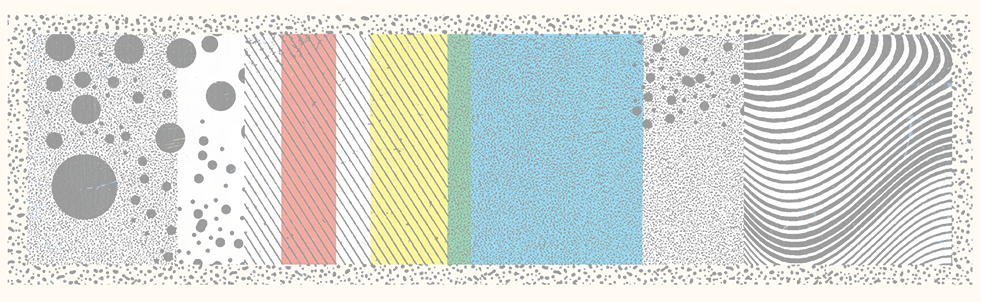香水の歴史をさかのぼってみると、香りにはさまざま形式や形状が存在していたことが分かってくる。液体なのか固体なのか、ポプラのように乾燥しているのか、それとも脂っぽくねっとりしているのか。そんな風に古来より香りの形質や質感は多岐にわたるものであったため、その香りを保管したり運んだりするための器具や道具にもまたさまざまなものが存在したのであった。そして本稿で取り上げることになる香りを拡散するための装置に関しても、それは同様であった。
それぞれの容器の形状は、なかに入っている香りの形質やその香りの使用用途によってデザインされたものである。そしてそのデザインされた形状こそが、それを使い扱う者の手の動きや仕草をデザインする。つまりある意味では香りは私たちの触覚や習慣といったものにも深く関わってくるものなのである。香りの拡散をともなう儀式やそこで使われる器具を知ることによって、それらがいかにして日常生活のなかに取り入れられてきたかを学ぶことができるだろう。そしてそれを知ることによって、嗅覚文化の歴史そのものに関する理解も深まるのではないか。
香りを拡散する技術が進歩するにつれ、当然のことながら香水業界は大きな利益を得ることとなった。特にディフューザーには歌手でもあったボリス・ヴィアンも目をつけており、技術革新が進む当時の時代背景を風刺的に歌いあげた「進歩の嘆きぶし」(1956年)のなかでは、昔ながらの愛や心情に取って代わることになったさまざまな現代的テクノロジーのひとつひとつを悲しげに列挙していきながら「嫌な匂いを丸ごと食ってくれる、あの大きなサーキュレーター……」と歌っている。かつてはゴム製のボールをプッシュしていたのが今ではディフューザーのボタンひとつ押せばよくなったり、かつては香炉の芯に火を灯していたのが今ではその仕草の対象はアロマキャンドルになったりと、そうした技術革新にともない香りの拡散方法や器具も変化してきたわけであるが、しかしそれらは決して単線的な進化をたどったわけではなく、その歴史をひもとけば各時代ごとに多くの枝分かれ的分岐を経験してきたことが立ちどころに分かってくる。香りを燃やす、希釈する、噴霧する、あるいは運ぶ、そうしたさまざまな目的のためにさまざまなアイテムが作られてきたわけであるが、こうした道具が発明された背景には実に多様な伝統から着想のヒントが得られたということがあったため、年代順に記述される単線的な歴史のなかに位置づけることは困難なのである。
香炉と燻香器
1850年の雑誌『ラ・モード』には次のような記述がある。「寝室で香を焚くことが流行っている。これはまるで、ルイ15世の時代に逆戻りしているかのようではないか」。ところが実際には、この習慣ははるか古代にまでさかのぼる。すなわち香りの起源、まだその使用用途が宗教的儀式にあり、天に立ち昇るかぐわしい煙が神々との交信を取りなすとされていた時代の話である。そしてこの習慣はその後もさまざまな時代を経るごとに幾度となく復活を果たしたのであった。例えば、ひとつかみの香を、まるで供物を捧げるときのようなうやうやしい手つきで燃え盛る炎のなかに投げ入れる古代人たちの姿は、新古典主義の絵画のなかに繰り返し登場するモチーフとして描かれたし、十八世紀の装飾芸術によって生み出されたさまざまなスタイルの香炉は富裕層の家具のなかには必ずと言っていいほど見出される品だった。なかでもアテネ風香炉にはギリシャ風の美しい装飾が施され、また三脚台の上に小さな壺上の香炉を備えたスタイルの三足香炉はとても大きく、丈の高さもテーブルに匹敵するほどだった。本物の金や銀で作られた燻香器はカトリックや正教会の祭礼に使われる欠かせない要素であり続けたわけだが、一方でこの香を焚く、という習慣が世俗的に浸透するようになったのは、その香ばかりでなく陶磁器や漆器といった工芸品の分野でも皇帝たちを魅了してやまなかった十七世紀中国の文化を始め、そのようにしてヨーロッパへと輸入されてきた他文化の影響が大きかった。
その中国においては、香を焚くという習慣とともに、繊細な技巧を要する美しい器具の製作もごく早い時期から発展したということも強調しておかねばなるまい。それらは仏教における儀式の中心となる香を捧げるために使われたり、または医術として、あるいは文人たちの社交の場に利用されたりなどやはりその用途はさまざまであったが、まさに驚嘆に値するそれら洗練された香炉の数々は、2018年にフレデリック・オブランジェによるキュレーションでセルヌーシー美術館にて開催された「中国の香り」展でも大々的に紹介された。実際、明王朝(1368-1644)から清王朝(1644-1911)の時代にかけては実に多くの香炉が作られていた。材質は砂岩、銅、陶磁器、青磁、玉器などと多岐にわたり、その形状や質感に関しても、すべすべとなめらかであったり、植物や動物の装飾的モチーフが施されたもの、巨大なものや逆に小さくて持ち運び可能なものまで、さまざまなものがあった。もくもくと焚かれる開放型の香炉が広い神殿内を薫香で満たすのに適していたのに対し、ふたつきのものはよりこじんまりとした室内を慎ましやかに香らせるのにぴったりだった。こうして宗教以外の領域でも香が一般的に用いられるようになるにつれ、香を焚くために必要となる道具一式が整えられていった。これに関しても実に種類豊富なさまざまなものが作られたが、一般的な類型としては、香をしまい保存しておくための箱とその香を焚く香炉、そして火の状態を調節するための(例えば香木を動かす箸や灰をすくうための匙などといった)器具の収められた壺、というこの3種の神器で構成されていた。なおこれに付随して、細々とした用具を置いておき準備しておくための板状のプレートが香炉の横にセットされる場合もある。さらに実はもうひとつあるのだが、これは上記のごとき美意識に基づく「型」というよりかは、より日常的で実用的な意図から来たものであった。すなわち香炉全体を覆うような形で檻上の骨組みを設置し、その枠組みの上に衣服を乗せることで、下から立ちのぼるかぐわしい香りを衣服に染みこませることができたのである。このような用具の存在からも、嗅覚の喜びを探求する人々の試みがいかに広く、かつ貪欲に行われていたかをうかがい知ることができるだろう。
散布器の登場は十二世紀にさかのぼる。さまざまな花の香りのついた水を散布するためのこの用具は現代でも使われているが、特に当時は大切な賓客をもてなすために重宝された。
ハイドロラットと香水の泉
中世イスラムを専門とする考古学者、ステレン・ルマゲールが自身のブログ「香と没薬」でも紹介している研究によれば、アラブ世界において早くから香が盛んに使用されて背景には、コーランのなかに香りに関する制約を定めた記述が存在しないことと、さらには他ならぬそのコーランが楽園はかぐわしい香りで満たされていなければならぬと定めていたこととが関係していた。こうして宗教的、世俗的の両面から使用されていた香は、特にこのアラブ世界においては客人に対し歓待の意を示すものであると同時に、社会的地位の高さを表す指標であるとされた。ここで注目すべきなのは香は煙としてだけではなく液体の形でも用いられたということだ。香りのついた水を使った沐浴である。身を清めることを目的としたこの習慣は確かに宗教的なものであったが、そこには衛生上の意図も含まれていた。有名なのは何と言っても、バラ水であろう。その蒸留方法はペルシャのアヴィケンナにより発見されたと伝えられている。ここで『千夜一夜物語』より、「荷かつぎ人足と乙女たちとの物語」の一節を引いてみよう。「彼女は蒸留所に立ち寄り、10種類の水を買い求めた。バラの水、オレンジの花の水、そのような香りのついた、さまざまな水を。[...]そして彼女は散布器も買った。それはほんのりとムスクの香るバラ水をまくために作られたものだった【編集者への連絡:本文中にはこの位置に同書仏訳者の名前が併記されていますが、ここではあまり意味をなさないため割愛しております】」。さてここで散布器という新たな道具が出てきたわけだが、一般的にはこの散布器は細長い首がひゅっと縦にのびた形状をしており、十二世紀にはガラス製のものがよく見られた。さまざまな花の香りのついた水を噴霧するためのこの道具ははるかインドにまで広がり、この現代においても重要な賓客を丁重にもてなす際に用いられているが、時代を経るにつれてじょじょに金属製のものが主流となっていった。 花から精油(エッセンシャルオイル)を抽出した後には、蒸留芳香水と呼ばれる副産物が残る。別名「ハイドロラット」とも呼ばれるこの花の香りのついた水は、洗面などの身繕い用として使われることが多かった。十九世紀のヨーロッパでは体を洗うのに水を使うことが一般化し始め、となるとそこへ香りをつけるという流れはもはや必然であった。そして体を衛生的に保つというその行為を行う場は、じょじょに浴室のなかへと移っていったのであった。こうした流れのなかで登場したのが香りつきの石鹸であったということを歴史家のウジェニー・ブリオは『香水の製造 あるいはラグジュアリー産業の誕生』(ヴァンデミエール社、2015年刊)のなかで明らかにしている。そしてその石鹸の製造によって、多くの実業家たちが財を成したということも。実際、当時の女性雑誌やマナーガイドによって実施されたアンケート調査を参照してみると、洗面用の水に香水をつけ加えるという習慣が広く実践されていたことが認められる。なおここで言う「香水」とは、1830年代以降確立された製造法によりアルコールで希釈されたものを指す、まさに現代で言うところの「香水」である。さらに十九世紀末になると、「さあ、あなたの家の浴槽にもリュバンの香水を注ぎましょう」と香水の美肌効果を謳う広告が繰り返し掲載されるなかで、出版社のグラッセの広告ポスターにも、洗面器に向けて香水瓶を傾けるという動作が描かれた。だがこのように香水を水で希釈しその香りを楽しむという行為を最も強力に象徴していたのは、何と言ってもウジェーヌ・リンメルの「香水の泉」であろう。どこかルイ15世の時代を彷彿とさせるこの「香水の泉」を、リンメルは1851年のロンドン万博に出品した。東洋趣味の、やや仰々しいスタイルのこの彫刻作品は、著名な調香師の作によるヴィネグルド・トワレが小さな水盤の上に流れ出る仕組みになっていた。このような仕かけを持った物が公共の場に存在するということが人々の内に大きな喜びと熱狂を呼び起こしたということは、エミール・ゾラの小説『ボヌール・デ・ダム百貨店』(1882年刊)のなかにも見て取ることができる。同作の中盤には次のような一節がある。「人々を何ともうっとりとした気分にさせていたのは、中央にある銀色の泉だった。花畑のなかに羊飼いの女性像が立っており、その女性像からはか細いスミレの水が絶え間なく流れ出ており、それが金属製の水盤に当たってまるで音楽のような美しい音色を奏でていた。周囲にはかぐわしい香りが広がり、そこを通るご婦人がたは皆自分のハンカチをその泉に浸していた」。
ベンチュリ効果
燃え盛る炎のなかに香を投げ入れること、あるいは、浴槽のなかにオーデコロンを注ぎ入れること。上記に見たこのふたつの行為はどちらも香りを発生させるためになされる動作であるという意味では共通しているが、しかしこれもすでに見てきたように、実際にはこのふたつはそれぞれまったく異なる伝統から生じたものであるし、その香りを発生させる目的自体も異なっていたわけだった。そして何よりも、前者は火を、そして後者は水を、というように、互いに相反する属性をその領分としていた。ところが十九世紀になると、ある発明品の登場によってこの火と水とが思わぬ形で融合を見ることになる。噴霧器の誕生である。このころ香水産業そのものが大きな成功を収めたことにより、その市場の拡大にうながされ、香水の香りを拡散させるための器具もそれ以降続々と発明されるようになっていった。フランス国家産業財産庁に今も保存されている数十件にもおよぶ特許が当時の発明競争の過熱ぶりを物語っていよう。さて、現代では「アトマイザー」と呼ばれることのほうが多いこの「噴霧器(vaporisateur)」であるが、この言葉が「蒸気(vapeur)」から派生した語であることからも分かるように、この初期の噴霧器は現在で言う小型のスプレー式アトマイザーではなく、蒸気式のものを含意していた。すなわち香料を加熱することによって気化・蒸発させ、その蒸気を制御しつつ四方へと香りを拡散する。つまりそれまで火で焚かれもくもくと立ちのぼっていた香の煙は、このより細やかな、蒸発するミストによって取って代わられたということになる。1861年に調香師のリンメルによって特許が取得されたリンメル噴霧器は、劇場の消臭に重宝されていたということである。当時発刊されていたファッション・音楽・演劇関係の新聞『コモエディア』紙がそれを報じている。またこのリンメル噴霧器と類似した機構を持つルグラン噴霧器を1867年にオリザ・ルグランが発売し、こちらもやはりアパルトマンや公共の場を香らせるのに好評を博したという。
こうした革新的なアイテムが世に出る一方で、注射器の例でよく知られている圧縮ポンプの原理を応用した発明品も数多く登場した。例えば1810年の国立産業奨励協会の報告書には、美食家として知られるブリア=サヴァランによって考案された、上記の加熱式とはまた異なるタイプの噴霧器が紹介されている。高潔な人物だが、ユーモラスな茶目っ気もあわせ持っていたブリア=サヴァランは、科学アカデミーで行ったその器具の実演を次のように回想している。「持参した機械のなかに、空気はしっかりと充填してあった。私は栓をひねる。すると、シューッという音とともにかぐわしい香りの蒸気が装置のなかから出て立ちのぼり、部屋の天井にまで届く。その蒸気はやがて水滴となってぽたぽたとしたたり、部屋にいた人々の頭を、そして書類を濡らす。パリで最も知性ある人々が私の作り出した霧の下でかしずいている光景を前にして、私はそのとき言い知れぬ喜びを感じる。それにくわえ、私にとって何とも愉快に思われたのは、そこで最も濡れている者が最も幸せそうに見えたということだ」(『味覚の生理学(美味礼讃)』1826年刊より)。ブリア=サヴァランによるこの拡散方式にはいくつかの後継機が続き、なかでもナタリー・ダニロフは1864年「液体香料をミスト状に放射する機械」という題目で特許を取得した。
また十九世紀末にはミュシャの商品ポスターによって人々の記憶に永久に残ることとなったロド香水噴射器の登場によって、より遠くにまで香りを放射することが可能になった。現在一般的に使われているガス圧縮式のエアゾールスプレーも、容器の外に内容物を、圧力を利用して粒子状に放出するというこの機構においては似通ったところがある。そして現代の私たちにとってなじみのあるアトマイザーの原型も、同じくそのころに開発されたのだった。これを使うにはボール状に膨らんだゴム製のポンプを押して容器のなかに空気を送りこんでやる必要がある。つまりは十八世紀に発見された物理法則、ベンチュリ効果を応用したものだった。1870年代に登場したこの器具は、より安価で効果も優れているとたちまちのうちに評判となった。そして何よりも、付属するゴムポンプを手で握って押すというこの新たなる象徴的動作をそのアイテムは生み出したと言えるだろう。調香師たちがそれぞれ思い思いの香水瓶を使うようになり始めたのもやはりそのころだった。歴史家ロジーヌ・ルルーは『調香師の歴史 フランス、1850年から1910年まで』(シャン・ヴァロン社、2016年刊)のなかで、1888年のバルセロナ万博ごろから調香師たちが自身の香水だけでなく外部に製造を委託した香水瓶や噴霧器といったアクセサリー類も出展する権利が認められるようになっていったことを記している。さらに従来では色とりどりのボトルに好きな香水を詰め替えて使うことができる化粧用セットが人気であったが、やがて二十世紀に入ると完全にこの文化が廃れ、人々は香水メーカーが販売する専用の香水瓶をそのまま使うようになる。
こうして一般家庭の化粧台の上にも噴霧器が普及するようになると技術的な改良はさらに加速し、特にゴムの劣化が早いという声が多くあがったため、ポンプの材質の見直しが進められた。またこれと同じくらい熱心に取り組まれた課題は、携帯性の向上であった。これによって密閉性の高いしっかりと閉まるキャップの開発や噴霧器そのものの小型化が吟味検討された。そして噴霧器メーカーのマルセル・フランクは全体が金属でできた、バッグにもすっぽりと収まる試作品を完成させ大きな成功を博した。「少なくつけても、しっかりと香る」という広告スローガンはまさにそのコンセプトを体現する言葉だったと言えた。同作はチャップリンへのオマージュとして「ル・キッド」(1923年発売)と名づけられ、そしてその後継が「ウィーク・エンド」として1950年代始めごろ発売された。
現代におけるアトマイザーの原型ともなったこの噴霧器は、十八世紀に発見された物理法則「ベンチュリ効果」を応用したものだった。
宝石、嗅ぎ塩、ヴィネグレット
噴霧器を持ち歩くことができる、それは人々が長いあいだ見続けていた夢であった。十八世紀のヨーロッパではすでに、手のひらのなかに収まるくらいの小型のアイテムが複数存在していた。またどのような環境下においても変わらぬ密閉性を保証する小瓶の特許が数多く出願されていたことも、香水を持ち運ぶことに対する人々の期待と願望が並々ならぬものであったことを示していよう。香水をつけてもその香りはすぐに立ち消えてしまうものであるがゆえ、人々はその香水を携行し、いつでもどこでもつけ直すことによってその嗅覚的喜びを何度でも、しかも持続的に味わいたいとそう願ったのである。そのように香水をさっと取り出して使えるということは、特に香水が治療薬として重用されていた時代にあっては理想的なことであった。気つけ薬としての嗅ぎ塩を迅速に失神した人の鼻先に持っていけるようになったことで、そのように気を失った人々はどれほど救われた思いをしたことだろう。そしてこのような気つけ薬は本物の宝石が散りばめられた美しい小瓶や、「ヴィネグレット」と呼ばれる気つけ薬入れとアクセサリーの両方を兼ねたジュエリーのなかに入れて持ち運ばれたのであった。このように香水を携帯して持ち運び、そしてその香りを身にまとうということは世界に広く浸透した習慣であると言えたが、その香りをいかにして香らせるかということに関しては、ふたつの方法があった。すなわち肌に直接接触させることと、他の何かに染みこませることである。具体的な例としては、まずは今も続く伝統として、「サシェ」と呼ばれる小さな香り入りの袋が挙げられるだろう。その香り袋のなかにはドライフラワーやハーブが入っており、これを肌着に忍ばせることによってかぐわしい香りをその身に移すことができた。南仏プロヴァンスではラベンダーが、北米ではスイートグラスが入れられることが多かったという。肌着の他にも、手袋に香水をしみこませるというのも好んで使われた方法だった。また香りつきのカードや扇子などは、香水業者や調香師たちが自身の香水を世間に認知させ宣伝するための広告手段として一役買った。人の肌に対し常に直接接触しているという点においては、ジュエリーを始めとした装飾品類に香りを仕こむというのが最も効果的な方法と言えるかもしれない。なかでもアンバーグリスのネックレスはその高貴な香りだけでなく病気への予防効果もあったとされ、早くも十二世紀ごろから人気を博していた様子がうかがえる。また「琥珀のリンゴ(pomme d'ambre)」に由来するとされる「ポマンダー(pomanders)」はその名の通りリンゴの形に似た球状の金銀細工で、球のなかにアンバーグリスやムスクが入れられベルトやガードルなどに吊り下げて携行された、非常に特徴的な嗅覚アクセサリーだった。そこから香水産業はさらなる発展をとげ、それとともにさまざまな技術革新がもたらされることになる。
1891年にはレンテリックが「アティーシュ」という名のペンダントタイプのディフューザーを発売し、従来のものより長く香りを持続させることができると評判になった。その後にもさまざまなアイテムが続々と登場することになるが、全体的な傾向としては「まるでジュエリーのような香水瓶」から「香水瓶の機能を持ったジュエリー」へとシフトしていったと言える。例えば1930年代に登場した「ル・イルレ」というブレスレットは、その表面に香水を数滴垂らすことで手首から香りを発散させることができた。こうした香水ジュエリーにおいては、アクセサリーにしみこませるなり滴らせるなりした香水がそのアクセサリーとともに人の肌に触れることにより、その温度によって温められ、より香りやすくなるというのがポイントだった。これまで見てきた香水用アイテムは、それを扱う動作も含めて、この現代においてもなお生き残り続けているものばかりである。仮にすでに消え去ってしまったものがあったとしても、少なくともそれらのリバイバルは市場において定期的に起こり続けている。このリバイバルの傾向は今紹介したような香水アクセサリーにおいて特に顕著であるように思われるが、しかしそのような終わりのない流行り廃りが永遠に繰り返されるなかで、香水業界は時代ごとに異なる新たな課題に適応する必要性に常にせまられ続けてきたわけだった。目下の課題は、やはり環境への配慮であろう。そうした環境意識の高まりによって、今日では香水瓶が、中身を補充することによって再利用可能なタイプのものへと切り替えられつつある。過去数十年のあいだ支配的だったキャップの開閉できない香水瓶の優位性が否定され、多くのブランドは空いた香水ボトルを再び香水で満たすことを呼びかけている。非常にシックなデザインの香水用サーバーも登場し始めている。こうして使い捨ての文化からの脱却が進めば、ひょっとしたら香水の泉にハンカチを浸すというあの古い習慣が復活する日だって、そう遠くはないかもしれない。
アンバーグリスのネックレスはその香りだけではなく病気への予防効果を持つものとしても重宝された。