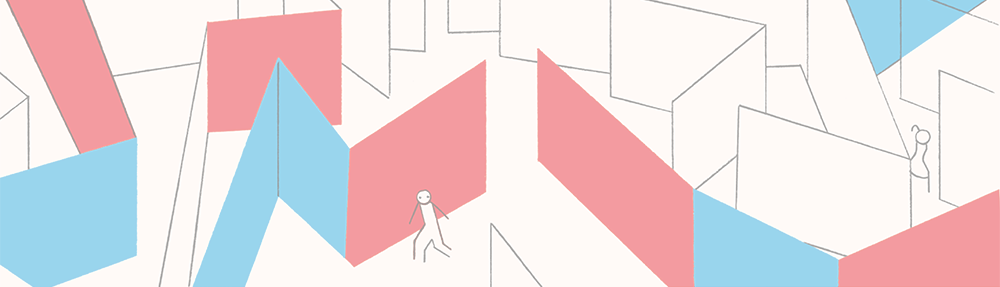2020年1月30日、フランス国民議会は「フランスの田舎を感覚遺産として保護すること」を目的とする法案を第一読会にて可決した。つまりこの法案が議会により最終的に承認されれば、匂いや音といったものまでもがその地域における文化のひとつとして認められることになるのである。しかしながらこの法案の適用を待つまでもなく、個々人の嗅覚や味覚による感覚が家族、地域、国民の歴史を通して連綿と受け継がれてきた遺産であるという考えかたは、すでに人々によって広く共有されているものと思われる。
食事を取るという行動、あるいは食習慣、そしてその食事と結びついた料理や食材の香り。これらが遺産として共同体内で継承されることにより重要な文化的指標が形成される。換言すればこのような継承こそがその共同体が社会化される条件であるとも言えよう。フランスの美食家、ジャン・アンテルム・ブリア=サヴァランは1825年に著した理論書『味覚の生理学、あるいは超越的美食をめぐる瞑想』(日本では『美味礼讃』のタイトルで知られる)において早くもその認識に達していた。ブリア=サヴァランは次のように記している。「君が普段何を食べているのか言ってみたまえ。君が何者か言い当ててみせよう」。故郷を離れ異国の地をさまよう者たちであればなおのこと、その言葉に異を唱える者はいないだろう。というのもそんな風にあるべき本来の食生活から切り離されてしまうことこそ、彼らを悩ます解決困難な問題のひとつに他ならないからだ。ドキュメンタリー映画「クッキング・ホーム」のなかで、監督のジョンモウ・スンはジョージ・ワシントン大学で学ぶためにワシントンDCに移住してきたふたりの中国人青年の姿を追っている。監督はノスタルジーにさいなまれているふたりにとって、故郷の味がいかに大切かを浮き彫りにしていく。そしてそのノスタルジーは旧正月の訪れとともに最高潮に達し、その伝統にならい故郷では家族が皆一堂に会していることを思うと、彼らはなおのこと孤独や疎外感にとらわれてしまうのであった。さらに悪いことにはソーシャルメディアによって皆の様子をほぼリアルタイムで知ることができてしまうため、そうしてふたりに対しさらなる追い打ちがかけられるのであった。彼らのひとり、ジャオ・シーハオはカメラの前で次のように打ち明ける。「中国の友人がポストしていた料理の写真を見て、ちょっぴり悲しい気持ちになってしまいました。写真に載っていたのは僕の好物ばかりで、ああ、全部食べたいなあと思いました。講義なんてサボって、飛行機に乗って中国に帰れたらなあと。そしてそのまま休暇に入ってしまえたらどんなにいいだろう、などと考えていました」。
ホームシックへの処方箋は料理をすることだ、というのはよく言われることである。実際このふたりもそれにならうことにした。監督はカメラを片手にその様子を観察する。そこでも彼らはソーシャルメディアを大いに活用している。ビデオチャットで両親たちと連絡を取る。ただ近況を伝え合うだけではなく、牛肉の煮こみやワンタンスープなどの直伝のレシピから、どうすれば自分たちが故郷で作ってもらっていた家庭料理を忠実に再現できるのかアドバイスを乞うために。こうしたシーンを通してジョンモウ・スンが言いたいことは、そうした家庭料理が彼らの手で調理されることによってひとつの文化の再生産が見事に行われているということなのだ。そしてそうした食文化はこれからも継承され続けていく必要があるということだ。
作中、同じ街出身の学生たちが10人ほど集まり一緒になって食事をするシーンが随所に差し挟まれるのは、そのような社会的交流を通して感覚的な絆を改めて意識することが重要なのだということを強調する意図ゆえであろう。オーストラリアの社会学者、ユリディス・T・シャロン・カルドナはシドニー在住のキューバ系移民たちのディアスポラ(民族的離散)を論じた記事のなかで、キューバという故郷から離れた彼らが自らのルーツを確認し合うために共に集まる頻度の高さを強調しつつ、その会合では焙煎したてのキューバコーヒーが供され、その他にもタマルという、鶏肉や野菜をベースにしたものをトウモロコシの葉で包んで蒸した伝統的な郷土料理、さらにはピルリンと呼ばれるカラフルなキャラメルでできた棒つきキャンディーといったものを皆で食すことで自分たちのアイデンティティを再認識していることを紹介している。しかしながらそうした集まりのなかで彼らは同じ食習慣を共有しながらも、年配者たちにとってはそれらが移住と離散のショックをやわらげるためのものとしてある一方で、若者たちは他とはちがうキューバ独自の食文化を実践することで自らの文化的アイデンティティを表現しようとしている、といったそうした世代間での目的意識あるいは態度のちがいも見受けられる。
したがってしがたってこのような場面では必ずしもノスタルジーであったりとか、何か失われてしまったものを取り戻そうとすることが問題となってくるわけではない。そのことはイギリスの社会学者、アレックス・リース=テイラーも認めており、問題となってくるのはむしろ「今現在の状況にしっかりと根を下ろし、目の前の現実に適応したい」という切実な願いなのではないか、と自身の著書『フード・アンド・マルチカルチャー』(ブルームスバリー・アカデミック出版、2017年刊、未仏訳)のなかに記している。これと同様のことをデザイン人類学者、オーストラリア・モナーシュ大学教授のサラ・ピンクも指摘しており、同教授は、ここで彼らが必要としているのは「感覚の社会化」なのだ、という言葉でこれを言い換えている。
払拭しがたい固定観念
ある人がその人だけの私的な空間内で好んでいるものが、しかし公的な空間でも許容されるとは限らない。人類学者のマーティン・F・マナランサン4世は論集『ザ・スメル・カルチャー・リーダー』(バーグ・パブリッシャーズ、2006年刊、未仏訳)のなかでグロリアという名前のフィリピン人女性を取り上げ、彼女が料理の匂いに対して抱えている不安を紹介している。アメリカで暮らしている彼女が恐れているのは、家庭内の料理で生じた匂いがドアの敷居をまたいで外の世界へと漏れ出てしまうのではないかということであった。たとえ漏れ出ることはなかったとしても、彼女の「衣服や、壁や、体に」付着しこびりつくその匂いは、彼女が移民女性であるということを周囲に向けて宣言し、彼女にとって社会的に不利となるマーカーとなってしまうからだ。このように、いくつかの民族グループや社会階級にスティグマを与えるためにこうした嗅覚的アイデンティティが引き合いに出されることは確かによくあることである。実際、地理学者のジョン・ダグラス・ポーテアスは労働者たちを描写する際、「彼らの仕事は汚く、たくさん汗をかくような重労働であるにもかかわらず衛生設備は不十分で、彼らはとてもじゃないが清潔とは言いがたかった」とする一方で、「それとは対照的に富裕層は汗をかく機会自体あまりなく、体を洗う頻度もより多かった」と続け、見事なまでのステレオタイプを示している。しかしながらジョージ・オーウェルが言うように、感覚にまつわるこのような固定観念の背景にはもう少し複雑な何かがあるのかもしれない。自伝的要素を含むエッセイ『ウィガン波止場への道』(1937年)のなかで、オーウェルは労働階級者たちが「悪臭を放つ者たちである」という考えは本能的なものではなく、あくまでも後天的に植えつけられたものであるということを強調している。「社会階級の低い者たちは匂うということ、それこそが私たちが徹底的に教えこまれ叩きこまれてきたことであった。そしてそれはまさに決して乗り越えることのできない障壁のごときものであった。なぜなら、それが良い感情であれ悪い感情であれ、身体的・生理的なものにまつわる感情は何よりも根深いものとして存在しているからだ。[...]ある人にどんなに好感を抱いていたとしても、その人の口臭がきついと分かったが早いか、とたんにこれ以上ないほど恐ろしい人物に思えてきて、その男を心の底から憎むことになるだろう。[...]そのようなわけで私たちがまだ若く幼かったころ、ありとあらゆる教育が私たちに対し、彼らは汚いものであるとしきりに納得させようとしてきたのであった」。
もはや悪臭それ自体が労働者たちのアイデンティティの一部なのである、とするようなそうした考えが強く押し通され強化されるにつれ、「非常に強力な象徴的力が生み出されることになる。その力によって階級を隔てる境界や民族間を峻厳と線引きする区分が創出され、人々はその境界を尊重し、その領分を遵守するよう求められるだろう」と、そう述べるのは文化史研究者のコンスタンス・クラッセンだ。なお引用は共著書『アロマ、匂いの文化史』(ラウトレッジ出版、1994年刊、未仏訳)からである。したがってここでクラッセンが示唆しているように、匂いもまた皮膚の色などと同様に不変の人体的特徴、動かしがたいひとつの事実としてのアイデンティティとなり得るということなのだ。